障がい者の働くを力強く支援する就労移行と継続支援の違いと活かし方。障害や難病のある方が「働きたい」という希望を叶えるために、国が定めている福祉サービスが就労移行支援と就労継続支援です。それぞれのサービスは、目的や働き方、利用期間などに大きな違いがあり、ご自身の「働く」の目標によって選ぶべき道が異なります。
「一般就職」を目指す就労移行支援と「働く機会」を提供する就労継続支援
障害を持つ方の「働く」を支える就労移行支援と就労継続支援は、障がい者総合支援法に基づいた福祉サービスです。
就労移行支援は、「一般企業への就職」を目指すための訓練やサポートを行うサービスです。具体的には、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方が対象となります。
一方、就労継続支援は、現時点では一般企業での就労が難しい方へ「働く場」を提供し、生産活動を通じて知識や能力の向上を支援するサービスです。こちらはA型(雇用型)とB型(非雇用型)の二種類に分かれています。
- 就労移行支援(一般企業への就職を目指す)
- 目的:就職に必要な知識や能力の向上、職場定着支援。
- 対象者:一般企業等への就職を希望する65歳未満の障がい者。
- 就労継続支援A型(企業との雇用契約に基づく働き方)
- 目的:雇用契約に基づき働く機会を提供し、一般就労に必要な知識や能力を高める。
- 対象者:一般企業への就労が困難で、雇用契約に基づき継続的に働ける原則18歳から65歳未満の障がい者。
- 就労継続支援B型(雇用契約なしでマイペースに働く):
- 目的:雇用契約を結ばずに、働く機会と生産活動の機会を提供し、能力向上を支援する。
- 対象者:一般企業への就労が困難で、雇用契約に基づく就労も難しい方(年齢制限なし)。
このように、就労移行支援は「一般就職」が明確なゴールであり、就労継続支援は現在の状況に応じた「働く機会の確保」と「能力向上」が主な目的となります。ご自身の「働きたい」の目標レベルに応じて選択することが重要です。
特に就労継続支援A型は企業との雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の賃金が支払われることが大きな特徴です。対してB型は雇用契約がないため、作業量に応じた工賃が支払われます。
就労移行支援は原則2年間の「就職特化型トレーニング」
就労移行支援のサービスは、一般企業への就職に必要なスキルを身につけるための職業訓練が中心です。
例えば、ビジネスマナーやパソコンスキル、コミュニケーション能力を向上させる訓練などが行われます。また、事業所による求職活動の支援や、個人の適性に応じた職場の開拓も重要なサービスです。
- 利用期間:原則2年間(標準利用期間)です。市町村の審査を経て最大1年間延長が可能な場合があります。
- 報酬:原則として賃金や工賃は発生しません。訓練の場であるため、労働の対価としての給与は支払われません。
就労継続支援は期間制限のない「働く機会の提供」
就労継続支援は、働く機会の提供と、それに必要な知識・能力の向上のための訓練が主なサービスです。A型とB型で雇用契約の有無が異なります。
- 利用期間:制限はありません。自分のペースで長く利用し続けることができます。
- A型(雇用型):雇用契約を結ぶため、都道府県の最低賃金以上の賃金が支払われます。
- B型(非雇用型):雇用契約はありません。生産活動に応じた工賃が支払われます。工賃は事業所や作業内容によって異なり、賃金より低くなることが一般的です。
この報酬の違いは、生活設計に直結する重要なポイントです。就労移行支援は無報酬ですが、一般就労というゴールを見据えた投資と考えられます。一方、就労継続支援は、働きながら賃金や工賃を得られる点が魅力です。
就労移行支援が向いている人と具体的な訓練内容

就労移行支援は、将来的に一般企業で働きたいという強い意欲を持つ方、また、働くためにスキルアップや体調管理の方法を身につける必要がある方に特に向いています。具体的には、次のような方が挙げられます。
- 就職意欲が高く、一般就労を目指している方。
- 就職経験が少なく、ビジネスマナーや職業スキルを一から学びたい方。
- 体調や障害の特性に合わせて、働くためのリズムや自己管理方法を確立したい方。
- 障害者雇用枠や、自分に合った職種・企業の情報を集め、就職活動のサポートを受けたい方。
- 一度就職したが、休職中で復職に向けたリハビリや準備が必要な方(市区町村の判断による)。
就労移行支援で受けられる主な訓練
事業所によって提供される具体的なプログラムは異なりますが、一般的に次のような訓練が受けられます。
- 職業スキル訓練:パソコン操作(Word、Excelなど)、データ入力、プログラミング、デザインなどの実務スキルを習得します。
- ビジネスマナー:電話応対、来客応対、報連相(報告・連絡・相談)など、社会人としての基本動作を学びます。
- グループワーク:コミュニケーション能力の向上、協調性を養うためのディスカッションや共同作業を行います。
- 企業実習・職場体験:実際の企業で就業体験をし、職場の雰囲気に慣れたり、自身の適性を見極めます。
- 疾病理解・セルフケア:自身の障害や病気について正しく理解し、体調を安定させて働くための対処法を身につけます。
これらの訓練を通じて、利用者は就職に必要な自信と具体的なスキルを身につけ、安心して次のステップである就職活動へ進むことができます。
就労継続支援A型(雇用型)が向いている人

A型事業所は、雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金が支払われる「働く場」です。労働者として働くため、ある程度の安定した出勤や作業能力が求められます。そのため以下のような方に向いています。
- 体調が比較的安定しており、決まった時間に継続して通所できる方。
- 雇用契約を結び、給与を得ながら社会参加をしたい方。
- 将来的な一般就労を目指し、雇用契約の下で実践的な経験を積みたい方。
- 就労移行支援を利用したが、一般就労に結びつかなかった方。
提供される仕事内容は、パンやお菓子の製造カフェ・レストランでの接客、パソコンでのデータ入力、清掃、部品の組み立てなど、多岐にわたります。事業所が企業として運営されているため実社会に近い環境で働く経験が得られます。
就労継続支援B型(非雇用型)が向いている人
B型事業所は、雇用契約を結ばないため、自分のペースで無理なく働きたい方に適しています。
体調の波があり、長時間働くのが難しい方や、体力に不安がある方、年齢の上限がないため高年齢の方も利用しやすいのが特徴です。得られるのは工賃ですが、比較的自由に利用できます。
- 体調の波があり、週に数日や短時間から働きたい方。
- 体力や集中力に自信がなく、無理のない範囲で働く経験を積みたい方。
- 就労移行支援やA型の利用が難しかった、または年齢的に対象外となった方。
- 創作活動やリハビリを兼ねて、社会との繋がりを持ちたい方。
仕事内容としては、軽作業(内職、部品加工、製品の袋詰めなど)、農作業、手工芸品の制作、清掃などが多く、利用者の健康状態や能力に応じた作業が提供されます。B型は働くことを通じたリハビリや社会参加の側面が強いと言えます。
サービス利用開始までの基本的な流れ
これらのサービスは、障害福祉サービスの一環として提供されるため、お住まいの市区町村への申請が必要です。基本的な流れは以下の通りです。
- 相談:まずは、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当課など)や相談支援事業所に相談します。サービスの種類や利用条件について詳しく聞きましょう。
- 利用申請:市区町村に利用申請を行い、現在の生活状況や働く上での課題を伝えます。
- サービス等利用計画の作成:相談支援専門員が個別支援計画(案)を作成します。ここで希望するサービスや訓練内容が具体化されます。
- 支給決定・受給者証の発行:市区町村が審査し、利用が認められると「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。これがサービスの利用券となります。
- 事業所との契約・利用開始:ご自身で選んだ事業所と契約を結び、個別支援計画を完成させてサービス利用をスタートします。
サービスの利用には、障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば可能な場合もあります。まずは窓口で相談することが最初の一歩です。
自分に最適なサービスを選ぶためのポイント
最適なサービスを選ぶためには、まずご自身の「働く」の目標を明確にすることが大切です。
- 一般企業への就職が最終目標なら:就労移行支援が最適です。原則2年間という期限を設け、集中的に就職に必要なスキルと知識を身につけ、就職活動のサポートを受けられます。
- 給与をもらいながら働く機会が欲しいなら:就労継続支援A型を検討しましょう。雇用契約の下で働き、一般就労に必要な知識や能力を高めます。
- 体調優先でマイペースに働きたいなら:就労継続支援B型が適しています。雇用契約なしで、体力や体調に合わせて無理なく働くことができます。
迷った場合は、市区町村の窓口や相談支援事業所、または各事業所の見学や体験利用を通じて、専門家や実際に働く人の意見を聞き、比較検討することが、自分に最も合った道を見つけるための最善の方法です。
まとめ

就労移行支援は、一般企業への就職を目標に、原則2年間で集中的な職業訓練と就職活動支援、そして職場定着サポートを行う就職特化型のサービスです。訓練の場であるため、原則として賃金は発生しません。
就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方へ働く機会を提供し、能力向上を支援するサービスで、利用期間に制限がありません。
A型(雇用型)は企業と雇用契約を結び最低賃金以上の賃金を得ながら働き、B型(非雇用型)は雇用契約なしで、体調や体力に合わせて工賃を得ながらマイペースに働くことができます。
あとがき
自分自身、今年の夏に役場でA型就労の相談をして現在A型就労継続でお世話になってます。その時はA型就労の意味も分からず、相談支援員の方に助けて頂きました。事業所では身体の事を御理解頂いて、とても働きやすく助かってます。
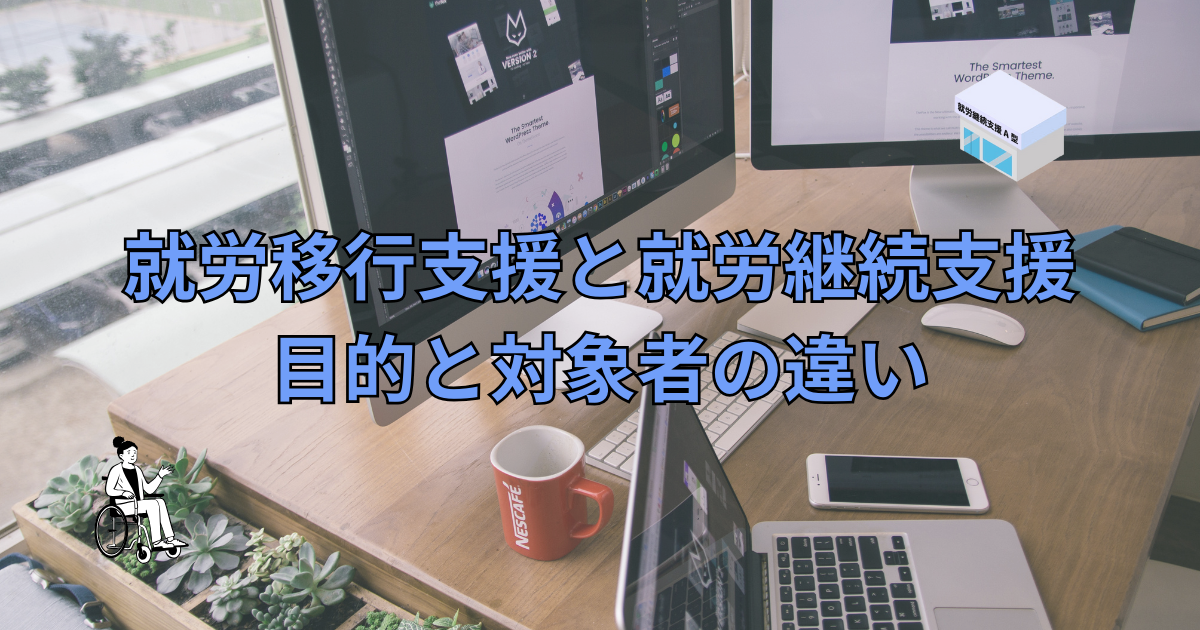
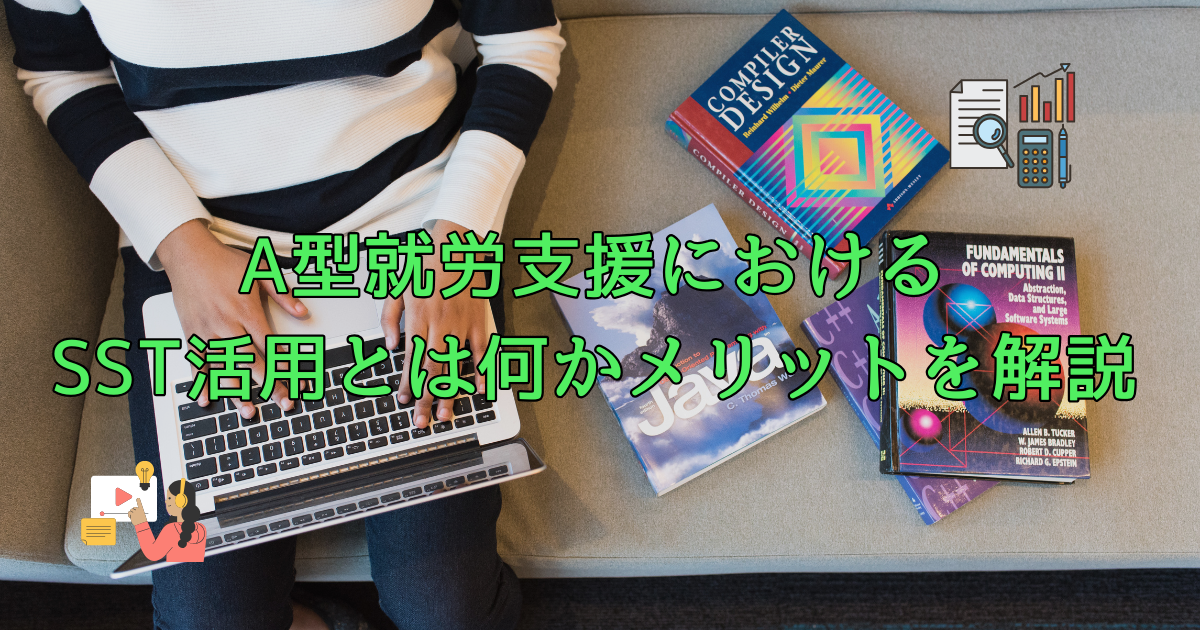
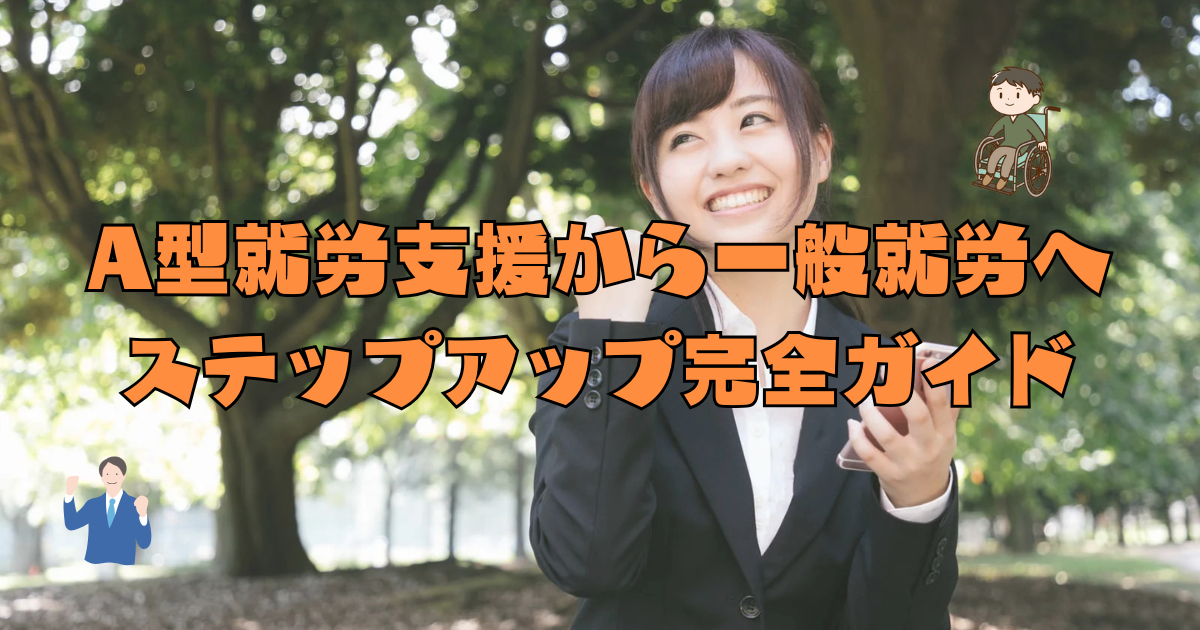
コメント