SDGsという言葉を耳にする機会は増えていますが、それが具体的に何を意味するのか、そして私たちの生活や社会にどう関わっているのか、十分に理解している人は少ないかもしれません。特に、福祉や障がい者支援に関心のある方にとっては、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現は、重要なテーマの一つです。本記事では、SDGsと福祉のつながりについて掘り下げ、私たちができることを考えていきます。
SDGsとは?持続可能な開発目標を知ろう
SDGs(エスディージーズ)は、2030年までに達成を目指す「持続可能な開発目標」です。2015年の国連サミットで採択された、17の目標と169のターゲットからなる世界共通の取り組みです。
SDGsの大きな特徴は、経済、社会、環境という3つの側面を統合的に解決しようとしている点です。
これにより、貧困や飢餓、教育といった社会課題だけでなく、気候変動や生物多様性の保全といった環境問題、そして経済成長のあり方まで、幅広いテーマが網羅されています。
それぞれの目標は、独立しているわけではなく、お互いにつながりあっています。例えば、貧困をなくすためには、健康や教育、そして働きがいのある仕事が必要です。
このように、SDGsは社会の複雑な問題を総合的に捉え、解決を目指すための羅針盤となっています。
重要なポイントは以下の通りです。
- 2030年までの目標: 国際社会全体で達成を目指しています。
- 17の目標と169のターゲット: 貧困や飢餓、教育など多岐にわたります。
- 「誰一人取り残さない」: 最も重要な理念の一つです。
この「誰一人取り残さない」という理念は、福祉や障がい者支援の分野と深く結びついています。
障がいのある人も、性別や年齢、人種にかかわらず、誰もが社会に参加し、自分らしく生きられる社会を目指すことこそが、SDGsの目指す姿の一つと言えるでしょう。
福祉とのつながり「誰一人取り残さない」という理念

SDGsの理念である「誰一人取り残さない」は、福祉と密接な関係にあります。障がい者や高齢者など、社会的に弱い立場の人々も置き去りにせず、誰もが共に生きる社会を目指す考え方です。
この理念は、福祉が目指す包摂的で、すべての人が自分らしく生きられる社会の実現と一致します。SDGsの17の目標の中には、直接的に福祉や障がい者支援と関連するものが多くあります。
たとえば、目標1「貧困をなくそう」や目標3「すべての人に健康と福祉を」は、誰もが安心して暮らせる社会の基盤づくりを目指しています。
目標4「質の高い教育をみんなに」は、障がいの有無にかかわらず、誰もが学びの機会を得られることを目指しています。
また、目標8「働きがいも経済成長も」や目標10「人や国の不平等をなくそう」は、障がいのある人が社会で活躍するための機会を創出すること、そして差別や偏見のない社会を築くことを求めています。
具体例として以下の取り組みが含まれます。
- 貧困からの脱却: 障がいのある人も安定した収入を得られるようにする。
- インクルーシブ教育: 障がいの有無にかかわらず共に学ぶ機会を設ける。
- バリアフリー化: 誰もがアクセスしやすい社会インフラを整備する。
このように、SDGsは福祉のあり方を再定義し、より包括的な視点から社会課題を解決しようとしています。
これは、福祉分野で働く人々や、障がい者支援に関心のある人々にとって、自身の活動が世界的な目標とつながっていることを示す重要な指標となるでしょう。
SDGsの具体的な目標と障がい者支援
SDGsには17の目標がありますが、その中でも特に障がい者支援と深く関わる目標がいくつかあります。
これらの目標を理解することは、福祉分野の専門家や支援に関心のある人々にとって、日々の活動をSDGsの枠組みと結びつける上で役立つかもしれません。
たとえば、目標4「質の高い教育をみんなに」のターゲットには、障がいのある子どもたちが、質の高い教育を受ける機会を保障することが含まれています。
また、目標8「働きがいも経済成長も」では、障がいのある人々の完全かつ生産的な雇用と、働きがいのある仕事の実現を目指しています。
目標10「人や国の不平等をなくそう」は、障がいや性別、人種などによる差別をなくすことを求めています。特に社会的に弱い立場に置かれやすい障がいのある人々の権利を保障することに焦点を当てています。
これらの目標は、障がいのある人々が社会のあらゆる側面に参加し、その能力を最大限に発揮できるような環境を整えることを目指していると言えます。それぞれの目標には、具体的なターゲットが設けられています。
- 目標4: 障がいのある子どもを含む、すべての子どもが公平に質の高い教育を受ける。
- 目標8: 障がいのある人々を含むすべての人が、生産的で働きがいのある仕事に就く。
- 目標10: 障がいのある人々に対する差別的な法律や政策を撤廃する。
これらの目標は、障がい者支援が単なる福祉活動ではなく、SDGsが目指す持続可能な社会を築くための重要な要素であることを示しているといえます。
私たちにできること:身近な行動が社会を変える

SDGsと福祉のつながりを理解した上で、私たちが日常生活でできることはたくさんあります。
大きなことをする必要はありません。日々のちょっとした行動が、SDGsの達成、そして「誰もが自分らしく生きる社会」の実現につながるかもしれません。
たとえば、身近な人や社会の多様性について考えてみることです。障がいのある人や、異なる背景を持つ人々と積極的に交流してみたり、社会のバリアフリーについて想像してみることも一つの方法です。
障がい者雇用に取り組んでいる企業の商品を選んでみたり、福祉施設で作られた製品を購入してみるのも良いでしょう。これは、障がいのある人々の経済的な自立を支援することになり、目標8「働きがいも経済成長も」に貢献します。
具体的にできることは、以下の通りです。
- 心のバリアフリー: 偏見をなくし、多様な人々との交流を心がける。
- ウェルフェアトレード: 障がい者支援施設などで作られた商品を選ぶ。※1
- 啓発活動: SNSなどでSDGsや福祉の情報を発信する。
- ボランティア活動: 障がい者支援のNPOなどで活動に参加してみる。
※1 「ウェルフェアトレード」は日本で使われる呼び方で、国連の公式用語ではありません。
これらの行動は、SDGsの理念を個人的なレベルで実践することになります。一人ひとりの小さな行動が積み重なることで、社会は少しずつ良い方向に変わっていくのかもしれません。理想とする社会を築くための、着実な一歩と言えるでしょう。
SDGsと福祉の未来:共生社会の実現に向けて
SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現は、まさに福祉分野が長年掲げてきた目標でもあります。SDGsの達成期限である2030年に向けて、福祉とSDGsのつながりはますます強まっていくことが考えられます。
これからの社会では、障がいのある人々がただ支援されるだけでなく、社会の担い手として活躍できるような環境を整えることが求められるでしょう。それは、インクルーシブ社会と呼ばれる、誰もがその人らしさを発揮できる社会です。
SDGsの目標達成に向けて、企業や行政だけでなく、私たち一人ひとりも主体的に行動することが重要です。
福祉施設やNPOといった組織と連携したり、地域コミュニティの中で共に支え合う仕組みを作ったりすることも、SDGsの目標達成に貢献するかもしれません。
SDGsと福祉の未来を考える上で、重要なポイントをまとめました。
- インクルーシブ社会: 誰もが参加し、活躍できる社会を目指す。
- 多様性の尊重: 個々の違いを強みとして捉え、活かす。
- 連携の強化: 企業、行政、市民が一体となって取り組む。
障がいのある人も、そうでない人も、お互いの違いを認め合い、尊重し合うことで、より豊かで持続可能な社会が生まれるはずです。
SDGsという大きな目標を道しるべに、私たちは「共生社会」の実現に向けて、着実に歩んでいくことができるでしょう。
まとめ

SDGsは、2030年までに達成を目指す「誰一人取り残さない」持続可能な開発目標です。この理念は、障がい者や高齢者を含むすべての人が共に生きる、福祉の目指す社会と深く結びついています。
貧困、教育、働きがいといった目標は、障がいのある人々の社会参加を促すものです。私たちの身近な行動が、この大きな目標の実現につながります。
あとがき
私自身、福祉の現場を訪れたことがあります。その時、利用者の方々の笑顔やひたむきな姿に触れ、誰もが自分らしく生きる社会の重要性を強く感じました。SDGsの「誰一人取り残さない」という理念は、そうした日常の光景の中にあるのです。
大きな目標ですが、私たちの身近な優しさや声かけといった小さな行動が、確実に社会を変える力になると信じています。この記事が、皆さんと共に「誰もが自分らしく生きる社会」を考えるきっかけとなれば幸いです。

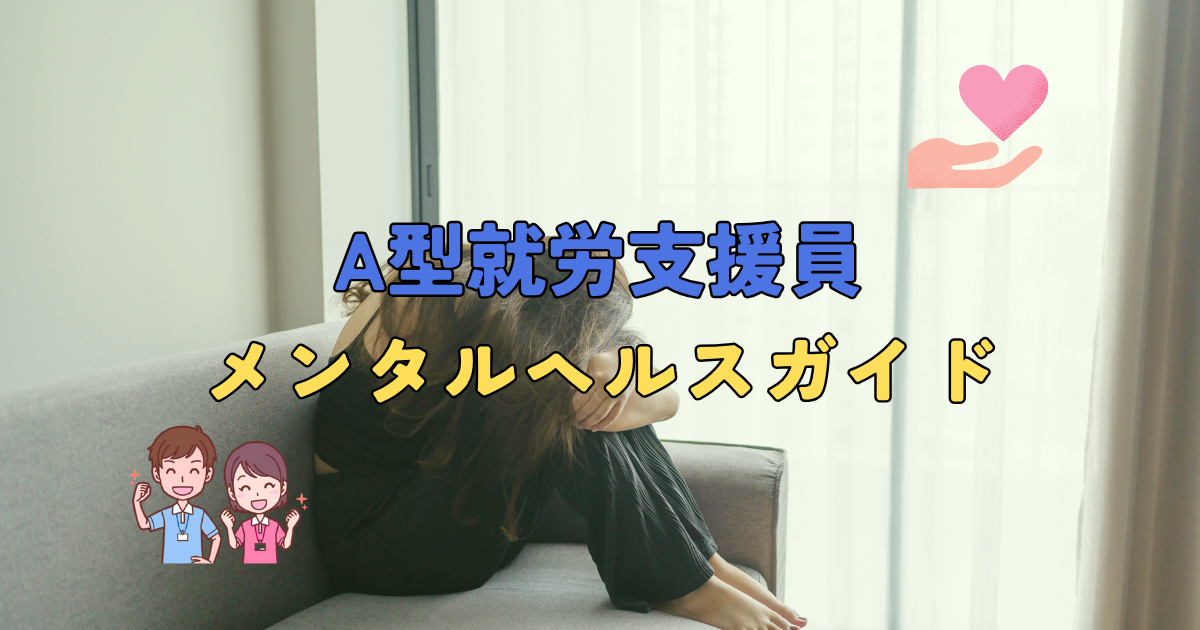

コメント