福祉の現場では、利用者の氏名や住所、病歴や障がいの状況など、極めて繊細な個人情報を取り扱います。そのため、サイバー攻撃のようなデジタルな脅威だけでなく、日常業務に潜む物理的なセキュリティリスクへの対策も非常に重要です。この記事では、特に見落とされがちな「紙ゴミからの情報漏えい」「業務引き継ぎのミス」「古い端末の初期化忘れ」という3つのリスクがあります。具体的な対策方法を分かりやすく解説していきましょう。
福祉現場に潜む!見落としがちなセキュリティリスク
福祉の現場における情報管理は、利用者の尊厳と安全を守る上で最も重要な業務の一つです。私たちは、ウイルス対策ソフトの導入やパスワードの強化など、デジタルな脅威には比較的注意を払っているかもしれません。
しかし、情報漏えいの危険は、もっと身近な場所に潜んでいます。例えば、日々の業務で発生する書類の廃棄、職員の異動や退職に伴う業務の引継ぎ、そして使わなくなったパソコンやスマートフォンの処分などです。
これらの物理的な管理の甘さが、思わぬ形で重大な情報漏えい事故に繋がる可能性があります。
様々な立場の人が業務に関わるA型就労継続支援事業所などでは、誰にとっても分かりやすく、実践しやすいルールを整備することが、トラブルを未然に防ぐ基本となります。
「ゴミ」が「宝」に?紙ゴミからの情報漏えいの恐怖

日々の業務で必ず出る紙ゴミですが、処理を誤ると個人情報流出の原因となります。何気なく捨てた書類が第三者の手に渡れば、利用者や事業所に深刻な被害を与える恐れがあります。
ゴミ捨て場は誰でも出入りできる場所であり、安全ではないことを常に意識する必要があります。特に福祉施設で扱う書類には高度な機密情報が含まれるため、廃棄時には細心の注意が欠かせません。
裁断せずに捨てる危険性
福祉事業所のゴミ箱には、利用者名簿、ケアプランの草案、面談メモ、業務報告書などが入る可能性があります。これらを裁断せずに捨てるのは、情報を無防備にさらす行為と同じです。
外部に流出すれば、特殊詐欺に悪用されたり、ストーカー被害を招く恐れもあります。シュレッダーを省く一瞬の判断が、大きなリスクにつながります。
A型事業所で徹底したいシュレッダーのルール
A型就労継続支援事業所のように、職員だけでなく多くの利用者が事務作業などに関わる環境では、情報廃棄に関する明確なルール作りが不可欠です。誰が、いつ、どのように書類を廃棄するのかを具体的に定め、全員で共有することが重要です。
- シュレッダーの設置場所
シュレッダーは、部外者が簡単に入れないよう、施錠可能な事務室などに設置するのが望ましいです。 - 分別の徹底
個人情報や機密情報を含む書類を捨てるための「シュレッダー行きボックス」を各所に設置し、通常のゴミと明確に区別するよう周知徹底します。 - 処理担当とタイミング
「毎週金曜日の終業前に担当職員がまとめて裁断する」など、処理のタイミングを具体的に決め、責任の所在を明確にしておきます。
また、裁断後のゴミの捨て方にも工夫が必要です。裁断した紙くずは、複数のゴミ袋に分けたり、他の燃えるゴミと混ぜてから廃棄します。復元されるリスクをさらに低減させることが可能です。
「うっかり」では済まされない業務引継ぎの落とし穴
職員の退職や人事異動は、どの事業所でも起こりうることです。その際の業務引継ぎが不十分だと、大きなセキュリティリスクを生み出す原因となります。
特に、パソコンやクラウドサービスなどのアクセス権限の設定ミスは、悪意がなくとも重大な情報漏えいに繋がりかねません。「あの人は信頼できるから大丈夫」といった性善説に頼るのではなく、「仕組みとして安全を確保」する意識が重要です。
引継ぎ業務は煩雑になりがちですが、ここでの一手間が、事業所全体の信頼を守ることに直結するのです。
権限設定ミスが招く重大な結果
退職した職員のアカウントが、事業所の共有フォルダや利用しているクラウドサービスにアクセスできる状態のまま放置されているケースは、少なくありません。これにより、退職後も内部情報にアクセスできてしまう状況が生まれます。
たとえ元職員に悪意がなかったとしても、そのアカウント情報が第三者に流出してしまえば、不正アクセスされる可能性があります。また、在職中の職員に対する権限設定が適切でない場合も問題です。
本来閲覧する必要のない利用者の個人情報にアクセスできてしまう状況は、内部不正のリスクを高めます。さらに、誤操作による情報流出の原因ともなり得ます。
安全な引継ぎのためのチェックリスト
職員の入れ替わりが多い職場環境では、業務引継ぎのプロセスを標準化することをおすすめします。誰が対応しても漏れがないようにすることが重要です。そのために有効なのが、引継ぎ専用のチェックリストを作成し活用することです。
A型事業所などでは、このチェックリストを職員全員で共有し、退職者と後任者、そして管理者が一緒に確認しながら進めることで、引継ぎミスを大幅に減らすことができます。
- アカウントの棚卸し
退職者が使用していた社内システムや外部サービスのID、パスワードを全てリストアップし、速やかに削除または変更します。 - アクセス権限の見直し
共有フォルダやデータベースなど、退職者のアカウントに紐づいていたアクセス権限を全て削除します。後任者には、業務に必要な最低限の権限のみを付与します。 - 貸与物品の返却確認
パソコン、スマートフォン、USBメモリ、社員証など、貸与していた物品が全て返却されたかを確認します。 - 紙媒体の管理
担当していた利用者のファイルや重要な書類が、後任者に確実に引き継がれ、所定の場所に保管されているかを確認します。
古い端末は情報の宝庫?初期化忘れのリスク

事業所で使用していたパソコンやスマートフォン、タブレットなどを廃棄したり、リース返却したり、あるいは他者に譲渡したりする際、端末内のデータを完全に消去することは絶対に必要な作業です。
多くの人は、ファイルをゴミ箱に入れて空にすればデータは消えると考えていますが、それは大きな間違いです。その行為は、あくまでOSからファイルへの道しるべを消したに過ぎません。データ本体は記録媒体に残り続けているのです。
これらの残存データが、情報漏えいの温床となる危険性を正しく理解する必要があります。
削除したつもりが…復元されるデータ
パソコンのゴミ箱を空にしたり、スマートフォンの「初期化」機能を使ったりしただけでは、データは完全には消えていません。
市販されているデータ復元ソフトを使えば、専門知識がない人でも比較的簡単に、削除されたはずのファイルや画像、メールなどを復元できてしまいます。
もし、廃棄したパソコンに利用者の個人情報や支援記録、事業所の財務情報などが残っていたらどうなるでしょうか。それらの情報が外部に漏れれば、事業所の信頼失墜に繋がるだけでなく、利用者の方々を危険に晒すことになりかねません。
古い端末は、情報の詰まった「箱」であるという認識を持つことが重要です。
福祉事業所が遵守すべき正しいデータ消去法
福祉事業所として、端末内のデータを確実かつ安全に消去するためには、適切な方法を選択する必要があります。
A型事業所などで使用していた古いパソコンを、リサイクル業者に引き渡したり、福祉施設に寄付したりする場合でも、データ消去のプロセスは決して省略してはなりません。
専門業者への依頼も含め、最も確実な方法を検討することが、最終的に利用者を守ることに繋がります。
- 専用ソフトの利用
データを復元不可能な形に上書き消去する、専用のソフトウェアを使用する方法です。フリーソフトもありますが、信頼性の高い有料ソフトの導入を検討するのが賢明です。 - 物理的な破壊
ハードディスクやSSDなどの記録媒体を、ドリルで穴を開けたり、ハンマーで叩き割ったりして物理的に破壊する方法です。最も確実な方法の一つですが、安全には十分配慮する必要があります。 - 専門業者への依頼
データ消去を専門に行う業者に依頼する方法です。費用はかかりますが、消去作業証明書を発行してくれる業者もあり、確実性と信頼性の面で最も推奨される方法と言えるでしょう。
まとめ

福祉現場では、デジタルだけでなく紙ゴミや引継ぎの不備、古い端末の初期化忘れといった物理的なリスクにも注意が必要です。紙は必ずシュレッダーにかけ、処理ルールを明確にすることが重要です。
退職者のアカウント削除や権限見直しを徹底し、業務引継ぎチェックリストを活用することで漏れを防げます。また、古い端末は専用ソフトや物理破壊、専門業者依頼などで確実にデータを消去することが、利用者と事業所を守る最善策です。
あとがき
この記事を書きながら、改めて福祉現場における情報管理の難しさと重要性を強く感じました。普段の業務の中で出る紙ゴミや、退職者の引継ぎ、古い端末の処分などは、つい見落としがちな部分ですが、一つの油断が重大な事故につながりかねません。
特にA型事業所のように多くの人が関わる場では、誰にでも分かりやすいルール作りが欠かせないと実感しました。この記事が、日常業務を見直すきっかけになれば嬉しいです。
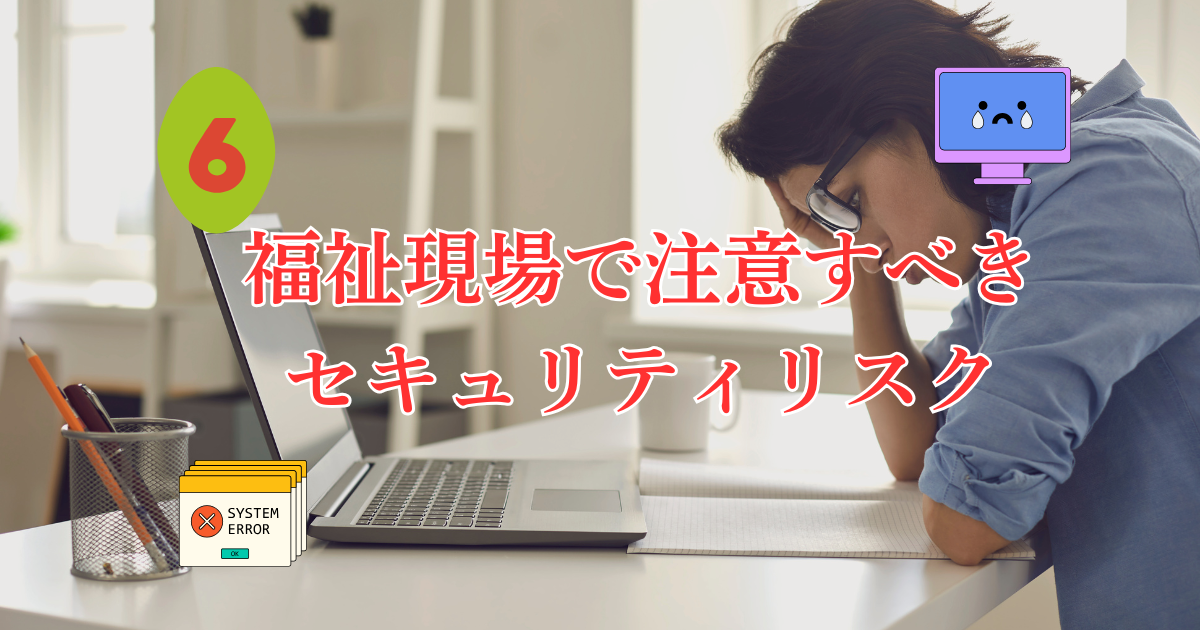
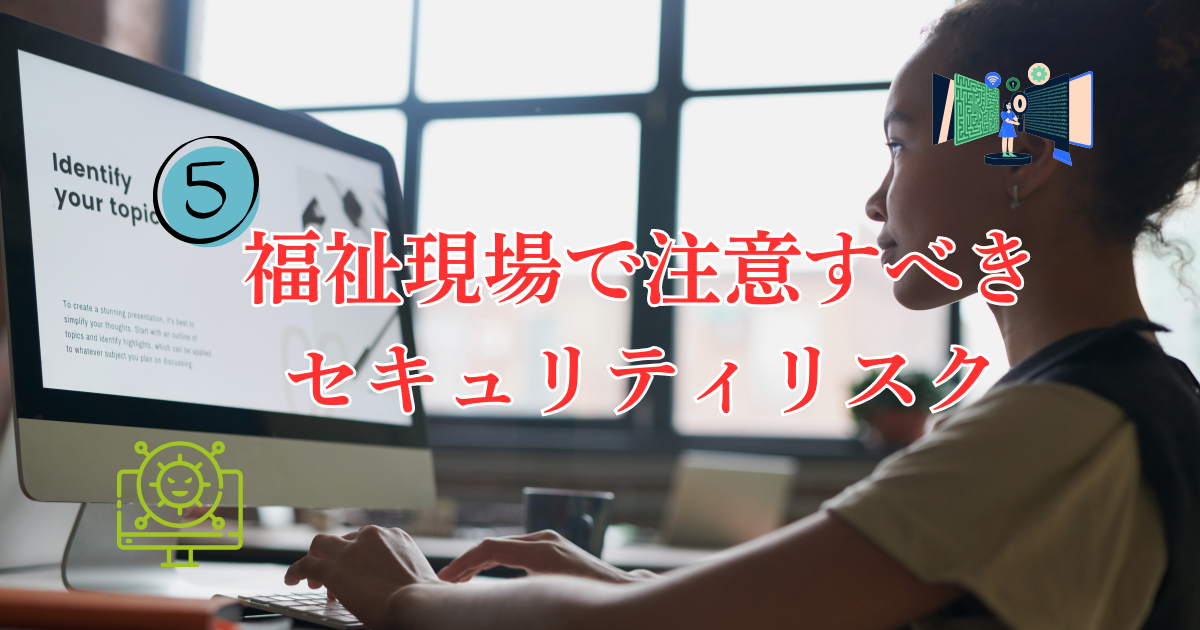

コメント