福祉の現場では、業務の効率化やコミュニケーションの円滑化のために、スマホやクラウドサービスといった「デジタルツール」の活用が急速に進んでいます。しかし、その利便性の裏側には、これまでとは異なる新たなセキュリティリスクが潜んでいます。この記事では、A型就労継続支援事業所などの福祉現場で起こりやすい、モバイル端末の紛失やLINEの誤送信、クラウドサービスの共有設定ミスといった、身近に潜む危険性と、その具体的な対策について詳しく解説していきます。
福祉現場に潜む身近な危険!モバイル端末紛失のリスク
福祉の現場では、スマホやタブレットは欠かせない存在になっています。訪問先での記録や職員同士の情報共有、利用者とのやり取りなど、活用の場面は多様です。
A型就労継続支援事業所でも職員や利用者が業務でタブレットを使うことが増えています。常に持ち運ぶため紛失や盗難のリスクがつきまといます。端末を落としてしまったとき、どのような危険があるのでしょうか。
端末内には、利用者の氏名や住所、障がいの詳細や支援計画など、非常に重要な情報が保存されている可能性があります。職員の連絡先や業務マニュアル、事業所のデータが含まれることも少なくありません。
第三者に渡れば悪用や公開につながり、利用者や家族に迷惑をかけるだけでなく、事業所の信頼を損なう恐れがあります。
他にも、漏れた情報を使った「特殊詐欺」や「SNSでのなりすまし」といった二次被害も考えられます。だからこそ、端末をなくさないための日頃の意識が大切です。
定位置管理を徹底する、不要な持ち出しを避けるなど、施設全体でルールを共有し、情報流出を防ぐことが求められます。
「しまった」では遅い!スマホ紛失時の情報流出を防ぐ具体的な対策

どれだけ注意しても、端末を紛失する可能性はあります。大切なのは、事前の「備え」で被害を最小限に抑えることです。万が一の時に慌てず、冷静に対応できるかどうかで結果は大きく変わります。
ここでは情報流出を防ぐために、今すぐ設定しておくべき対策を紹介します。一度行えば済むものが多いので、必ず確認しておきましょう。
紛失に気づいたら、まず責任者に報告し、携帯会社に連絡して回線を停止します。その後は、事前に準備した遠隔操作での端末保護が有効です。これにより第三者の不正利用を防げます。
- パスコードロックと生体認証
画面ロックは必須です。「1234」など単純な番号や誕生日は避け、6桁以上の複雑なコードを設定します。それから指紋や顔認証を併用して安全性を高めます。
- 遠隔ロック・データ消去機能
iPhoneの「探す」やAndroidの「デバイスを探す」を有効にして、位置特定・遠隔ロック・データ消去(リモートワイプ)を使える状態に準備します。
- データの暗号化
最近の端末は標準で暗号化されていますが、設定画面で有効か確認します。暗号化されていれば、内部データを抜き取られても解読されにくく安心です。
LINE誤送信が引き起こす重大な個人情報漏洩
福祉現場では、LINEが職員同士の連絡や利用者・家族とのやり取りに広く使われています。手軽で便利な反面、その気軽さゆえに誤送信のリスクを常に抱えています。
宛先を少し間違えただけで、大切な個人情報を誤った相手に送ってしまう可能性があるのです。例えば、利用者の体調や支援内容を誤って別のグループに投稿してしまったり、職員の連絡先を無関係な第三者に送ってしまったりすることが考えられます。
送信後に取り消し機能を使っても通知が残る場合があり、スクリーンショットを撮られれば拡散の危険もあります。こうした誤送信は単なる「ミス」では済みません。
受け取った相手に不安や不信感を与え、事業所と利用者・職員との信頼を一瞬で壊すこともあります。場合によっては個人情報保護法に抵触する恐れもあるため、LINEを使う際は常に個人情報を扱っている意識を持ち、細心の注意を払う必要があります。
LINE誤送信を防ぐための3つのチェックポイント

LINEの誤送信は誰にでも起こり得るミスです。だからこそ、失敗を前提にした仕組みや習慣づくりが大切です。これから紹介する3つのチェックポイントを意識するだけで、誤送信のリスクを大幅に減らせます。
【大原則】3つのチェックポイントに共通する心構え
「慣れているから大丈夫」と油断せず、送信前のワンクッションを習慣にしましょう。小さな確認が大きな事故を防ぎます。
特に複数の相手と同時にやり取りしている時や、急いで返信する場面では注意が散漫になりやすいです。一度立ち止まり深呼吸をして、本当に正しい操作かを確認してください。
「送信ボタンは必ず最後に見直してから押す」というルールを徹底することが、自分や事業所、利用者を守ることにつながります。
1. 宛先の再確認を徹底する
送信直前に宛先を必ず確認しましょう。トーク画面上部の名前やグループ名を指差し確認するくらい慎重さが必要です。同姓の相手がいる場合は、アイコンも要チェックです。思い込みは大きなリスクにつながります。
2. 送信内容に個人情報がないか確認する
送信前に内容を見直し、個人情報が含まれていないか確認しましょう。「本当にLINEで送る必要があるか?」を考えることも大切です。氏名や病状など機微な情報は、電話や対面など適切な手段で伝えるようにしましょう。
3. プライベートと仕事用アカウントを分ける
可能であれば、仕事用LINEアカウントを用意しましょう。プライベートな内容を誤送信するリスクを減らせるだけでなく、気持ちの切り替えも容易になります。事業所として運用ルールを決めることも忘れないでください。
知らないうちに情報が丸見え?クラウド共有リンクの誤設定
Google DriveやOneDriveなどのクラウドストレージは、資料共有や共同編集を簡単にし、福祉現場の業務効率を大きく高めます。ペーパーレス化やどこからでもアクセスできる利便性は、多忙な職員にとって大きな助けになります。
しかし共有設定を誤ると、事業所の機密情報や利用者の個人情報が誰でも見られる状態になる危険があるのです。
特に注意すべきは「リンクを知っている全員」という設定です。この場合、URLを知っているだけで誰でもファイルにアクセスできるため便利ですが、大きなリスクを伴います。
SNSやメールでリンクが漏れれば、無関係の第三者に閲覧される恐れがあります。成果物や利用者情報が知らない間に世界中へ公開される可能性もあるのです。
さらに厄介なのは、情報が漏れても管理者が気づきにくい点です。不正アクセスがあっても警告はなく、知らない間に情報が流出してしまいます。便利な機能だからこそ、リスクを理解し慎重に利用することが必要です。
安易なリンク共有は、取り返しのつかない事態を招くことを忘れないでください。
安全なファイル共有を実現するクラウド設定の見直し方
クラウドサービスを安全に使うには、共有設定の管理が欠かせません。一度設定したまま放置せず、定期的に見直す習慣をつけましょう。特に職員の異動や退職、プロジェクト終了のタイミングは設定を見直す良いタイミングとなります。
まずは、現在共有しているファイルやフォルダを一覧で確認し、意図しない相手に共有されていないか、範囲が広すぎないかを点検しましょう。不要な共有リンクは削除し、常に最小限のアクセス権に保つことを心がけてください。
手間に感じるかもしれませんが、地道な確認作業こそが情報漏洩防止につながります。事業所全体で定期的に棚卸しを行うルール化も効果的です。
「限定公開」を基本にする
共有は「限定公開(特定のユーザーのみ)」を基本にしましょう。許可されたアカウント以外はアクセスできず、リンクが漏れても安全性が高まります。不特定多数と共有する必要がある場合を除き、この方法を徹底してください。
アクセス権の定期的な見直し
誰にどのファイルの権限を与えているかを定期的に確認しましょう。退職者のアカウントや不要な権限が残っていないかをチェックし、必要最小限のアクセス権に絞る「最小権限の原則」を徹底することが大切です。
まとめ

福祉現場ではスマホやLINE、クラウドの活用が進む一方で、紛失や誤送信、共有設定の誤りによる情報漏洩リスクが常に潜んでいます。
端末には暗号化や遠隔ロックを設定し、LINEは宛先や内容を慎重に確認、クラウドは限定公開と権限の見直しを徹底することが重要です。小さな対策の積み重ねが、利用者や事業所を守り、信頼を失わないための確かな備えにつながります。
あとがき
この記事を書きながら、改めて福祉現場でのデジタル活用が便利である一方で、情報漏洩の危険と常に隣り合わせであることを強く実感しました。スマホの紛失やLINEの誤送信、クラウド設定ミスは誰にでも起こり得る身近な問題です。
だからこそ、日々の小さな確認やルール作りが重要であり、意識を持ち続けることが利用者や事業所を守る最も確実な方法だと感じました。
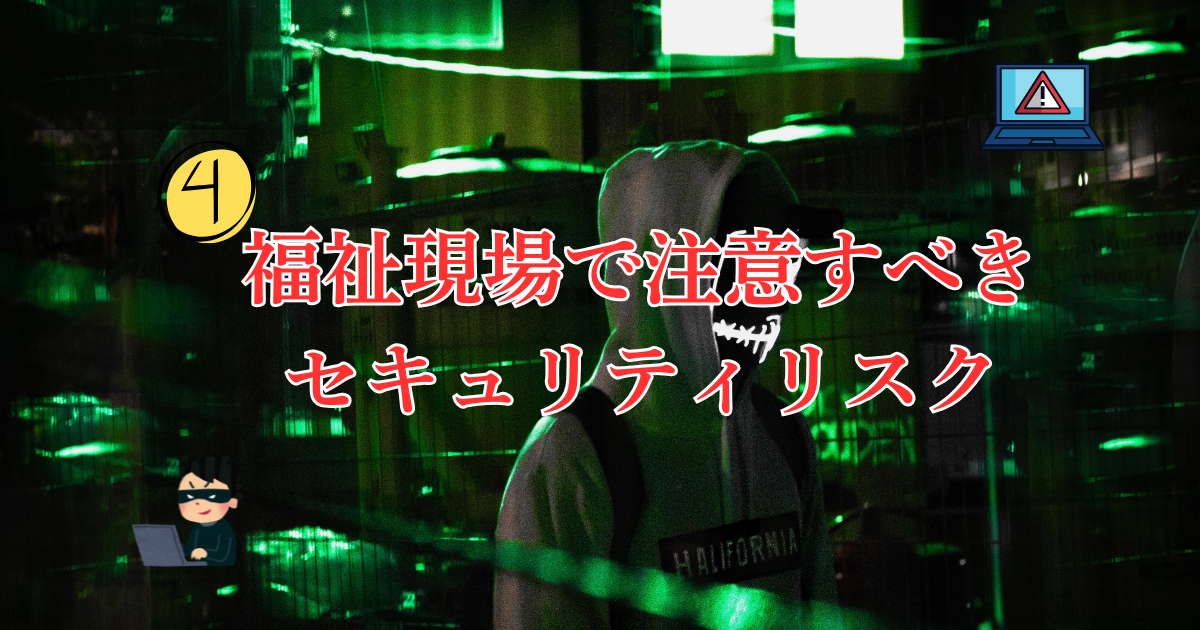

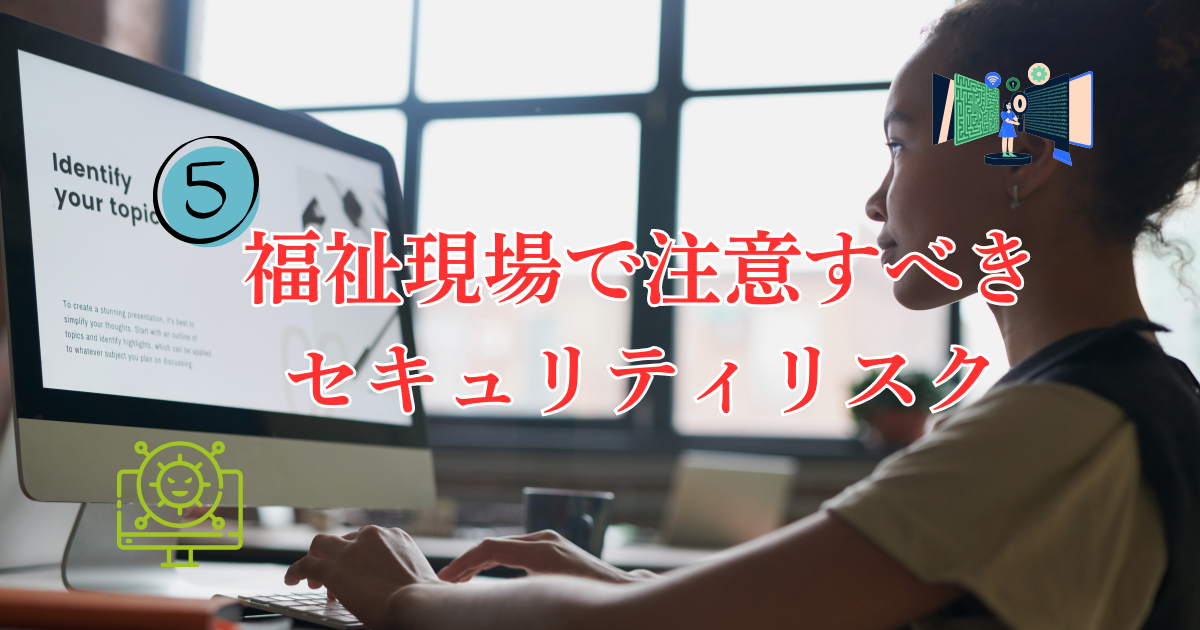
コメント