読書はしたいけれど、なかなか続かない。そんな悩みを抱えていませんか?特に、A型就労支援事業所を利用している方や、これから利用を考えている方の中には、集中力や自己管理に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、読書は日々の生活を豊かにし、スキルアップにも繋がる素晴らしい習慣です。本記事では、読書が苦手な方でも無理なく始められる、簡単な読書習慣の作り方をご紹介します。
読書習慣がない人が最初にやるべきこと
読書習慣を身につけるための第一歩は、いきなり大きな目標を立てないことです。たとえば、「毎日1冊読む」や「1時間読書する」といった目標は、挫折する原因になりがちです。最初はごく小さな目標から始めてみましょう。
たとえば1日1ページだけ読む、10分だけ読む、というように、自分にとって負担にならない程度の量から始めるのがおすすめです。
なぜなら、読書習慣の定着に必要なのは継続だからです。読書を「楽しい」と感じる前に「面倒くさい」と感じてしまうと、そこで終わってしまいます。最初は読書に対するハードルをできる限り下げることが重要です。
また読書する時間と場所を決めることも有効です。朝起きた後の10分、通勤中の電車の中、寝る前のベッドの上など、特定の時間と場所をルーティン化することで、意識しなくても自然と本を開く可能性があります。
さらに、どんな本を読むか悩む人も多いかもしれません。一番大切なのは、自分が「読みたい」と心から思える本を選ぶことです。ベストセラーや話題の本にこだわる必要はありません。
大事なポイントを以下にまとめてみました。
- 目標を小さく設定する: 毎日1ページ、1日10分など、無理のない範囲で始めましょう。継続することが最も重要です。
- 時間と場所を決める: 決まった時間に決まった場所で読むことで、読書を生活の一部に組み込めます。
- 好きな本を選ぶ: 漫画や雑誌など、自分が興味を持てる本なら何でもOKです。
以上のことを実践することで、読書を「面倒なこと」から「楽しいこと」へと変えられる場合もあります。無理なく、そして楽しく読書を続けていきましょう。
読書習慣がひらく新たな扉

A型就労支援事業所を利用、またはこれから利用を考えている方、読書は日々の生活に彩りを加え、スキルアップにも繋がる素晴らしい習慣の可能性があります。
たとえば、業務に必要な知識を学ぶために専門書を読んだり、コミュニケーション能力を高めるために小説やエッセイを読んだり。読書を通じて、興味の幅を広げたり、新しい働き方や生き方を発見したりできるかもしれません。
事業所内で読書会を開いたり、読んだ本を紹介し合う時間を設けてもらうのも良いアイデアです。本を通じて仲間と話すきっかけができれば、より良い人間関係を築くことにも役立つでしょう。
もし「どんな本を読んだらいいかわからない」と迷ったら、まずは事業所の職員さんに相談してみるのもおすすめです。きっとあなたにぴったりの一冊を見つける手伝いをしてくれるはずです。読書を通じて、あなたの可能性を広げていきましょう。
環境を整えるだけで読書は捗る
読書習慣を定着させるためには、読書に集中できる環境を整えることも大切です。たとえば、スマートフォンやテレビ、タブレットが近くにあると、通知や誘惑に気を取られて読書に集中できなくなってしまいます。
読書をする際には、なるべくそうしたデジタル機器から離れた場所を選ぶようにしましょう。また、読書の質を上げるために、場所にもこだわってみましょう。
カフェや図書館、公園のベンチなど、家とは違う場所で読書をしてみるのも良いアイデアです。いつもとは違う環境に身を置くことで、新鮮な気持ちで本と向き合えます。
自宅で読む場合は、お気に入りの椅子や照明を用意するだけで、読書時間をより快適なものにできます。
大事なポイントを以下にまとめてみました。
- 誘惑を遠ざける: 読書中はスマートフォンやテレビを視界に入れないようにしましょう。
- 場所を変えてみる: カフェや図書館など、気分転換になる場所で読書をするのも効果的です。
- お気に入りの空間を作る: 自宅で読む場合は、居心地の良い読書スペースを作ってみましょう。
さらに、本を持ち歩く習慣も身につけてみましょう。通勤中や待ち時間など、ちょっとしたスキマ時間も有効活用できます。小さなカバンにも入る文庫本や電子書籍を活用するのも良いかもしれません。
読書仲間を見つけてモチベーションを維持する
読書習慣を続ける上で、モチベーションの維持はとても重要です。一人で読書を続けるのが難しいと感じる人もいるかもしれません。そんなときは、同じ読書好きの仲間を見つけてみるのも良い方法です。
友人や家族と読んだ本の感想を話し合ったり、SNSで読書アカウントを作成して、他の人と交流したりする可能性もあります。読んだ本の感想を共有することで、新たな発見があったり、次読む本を見つけるきっかけになる可能性があります。
読書会に参加してみるのも良いでしょう。共通のテーマの本について語り合うことで、読書に対する興味がさらに深まるかもしれません。誰かと一緒に楽しむことで、読書がより楽しいものになるでしょう。
大事なポイントを以下にまとめてみました。
- SNSを活用する: 読書アカウントを作って、他の読書家と交流してみましょう。
- 読書会に参加する: 同じ本を読んだ人と感想を共有することで、新たな発見があります。
- 友人や家族と語り合う: 身近な人と本の感想を話し合うだけでも、読書の楽しみは広がります。
一人で黙々と読むのも良いですが、誰かと共有することで読書の楽しみは倍増します。モチベーションを維持しやすくなり、自然と読書量も増えていくかもしれません。
読書はインプットだけでなく、アウトプットの場も持つことで、より豊かなものになるでしょう。
読書記録で成長を実感する

読書習慣を長く続けるためには、自分がどれだけ本を読んだかを可視化することも有効です。読んだ本のリストを作る、読書ノートをつける、アプリで記録するなど、方法はたくさんあります。
読んだ本のタイトル、読了日、簡単な感想などをメモしておくだけでも、後から見返したときに自分の読書の足跡をたどることができます。
特に読書ノートは、単に読んだ本を記録するだけでなく、気になった言葉や考えを書き留めることで、読んだ内容がより深く記憶に残る可能性があります。
読書記録を振り返ることで、「こんなにたくさんの本を読んだんだ」「こんなに成長できたんだ」と、達成感を感じられるかもしれません。この達成感が、次の読書へのモチベーションにつながる場合もあるでしょう。
大事なポイントを以下にまとめてみました。
- 読書記録をつける: 読んだ本のタイトルや感想をノートやアプリに記録しましょう。
- 読書ノートを活用する: 気になった言葉や考えを書き留めることで、理解が深まります。
- 達成感を味わう: 自分が読んだ本の数を可視化することで、モチベーションが維持しやすくなります。
読書記録は、自分の読書傾向を知る良い機会になるかもしれません。どんなジャンルの本をよく読むのか、どんな作家が好きなのかといったことが客観的に見えてくる場合もあるでしょう。
読書記録をつける習慣は、ただ読むだけでなく、読書を通じて自分自身と向き合う時間にもなるでしょう。
読書がメンタルに与える良い影響
読書は、心を落ち着かせ、メンタルヘルスにも良い影響を与えます。A型事業所を利用されている方にとって、日々のストレスを軽減し、自己肯定感を高めるための有効な手段の一つになり得ます。
物語の世界に没頭することは、現実の悩みから一時的に離れる現実逃避の時間となります。これにより、気分転換ができ、心の負担を軽くする可能性があります。
また、ノンフィクションや自己啓発書を読むことで、新しい知識や考え方を学び、視野を広げる可能性があります。これは自分自身の可能性を再認識し、自己肯定感を高めることにもつながるでしょう。
さらに、読書は集中力を高める効果も期待できます。毎日少しずつでも本を読む習慣をつけることで、一つのことにじっくりと向き合う力が養われる可能性があります。
読書を通じて、登場人物の感情に共感したり、困難を乗り越える姿に勇気づけられたりすることもあるでしょう。このように、読書は単なるインプットの行為ではなく、心を豊かにする大切な時間となり得ます。
まとめ

読書習慣を身につけるには、まず小さな目標から始め、無理なく続けることが大切です。誘惑の少ない環境を整え、読書時間を楽しむ工夫をしてみましょう。
また、仲間と感想を共有したり、読んだ本を記録したりすることで、モチベーションを維持するのに役立つかもしれません。紙と電子書籍を上手に使い分け、自分に合ったスタイルを見つけることも重要です。
これらの方法を実践すれば、読書はきっとあなたの生活に自然と溶け込み、豊かな毎日を送るきっかけになるでしょう。
あとがき
あまり読書をしなかった私が、無理なく本を読めるようになりました。特に効果を感じたのは「1日10分、好きな本を読む」という小さな目標と、「スマホから離れてカフェで読む」という環境づくりでした。
読書記録をつけ始めたら、「こんなに読めた!」と自信がつき、今では読書がすっかり習慣に。本を通じて新しい世界と出会う喜びを、ぜひ皆さんも体験してみてください。
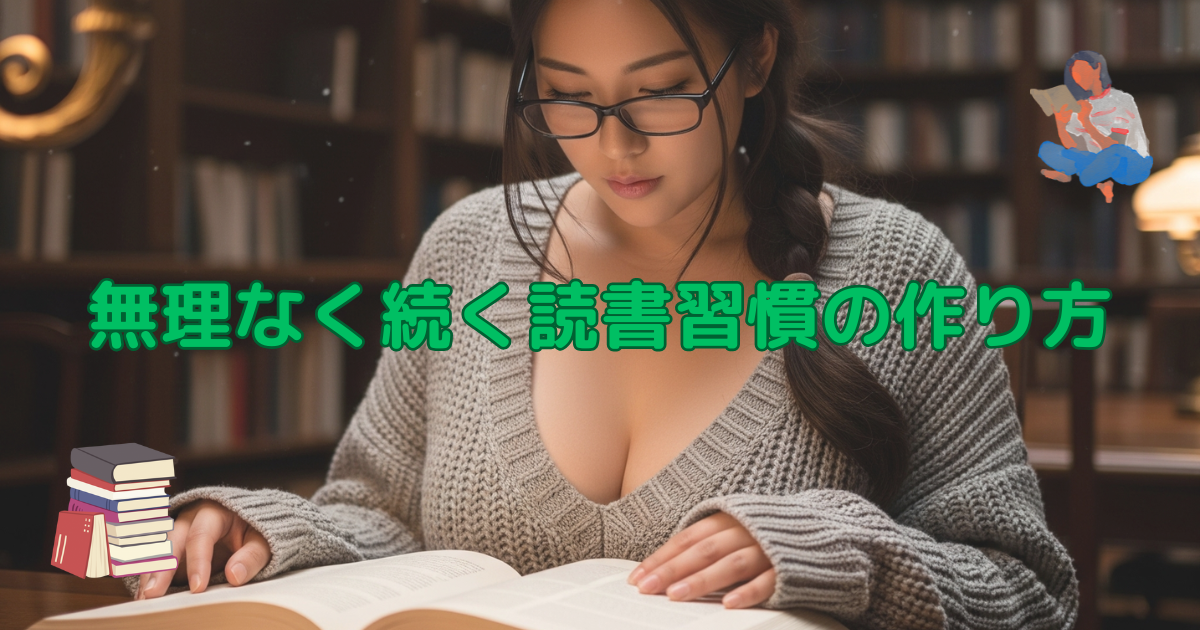


コメント