就労継続支援A型事業所は、利用者の皆さんがそれぞれの能力を活かして働く大切な場所です。その活動や作品を広く社会に伝えることは、事業所の価値を高めるだけでなく、利用者の皆さんの自信にもつながります。しかし、「どうやって発信すればいいかわからない」「どんな内容を伝えれば魅力的に見えるのか」と悩んでいる方もいるかもしれません。本記事では、事業所の活動や利用者の“強み”を効果的に伝えるための発信テクニックをご紹介します。
発信の第一歩!“強み”を見つけるためのヒント
A型事業所が外部に情報を発信する目的は、単に活動内容についての周知だけではありません。利用者の皆さんが持つ個性や能力を“強み”として社会に伝え、働くことへの自信や喜びにつなげることが重要です。
発信の第一歩として、まずはその“強み”を見つけることから始めましょう。
“強み”はどこにある?見つけるための視点
強みとは、特別なスキルや才能だけが該当するわけではありません。日々の作業に対する真摯な姿勢、チームメンバーを思いやる気持ち、作品へのこだわりなど多岐にわたります。以下の視点から強みを見つけ出してみましょう。
日常の作業風景
普段の作業風景をじっくり観察してみてください。皆さんがどんな道具を使い、どのような手順で作業を進めているか、その細部に注目してみましょう。
例えば黙々と正確に作業を続ける集中力、難しい作業にも諦めずに取り組む粘り強さなどがそのまま強みとして発信できるかもしれません。
利用者への対話やヒアリング
一対一の対話を通じて、強みを発見できることがよくあります。「この作業のどんなところが楽しいですか?」「どんなときにやりがいを感じますか?」といった質問から、その人ならではのスキルや熱意が見つかるかもしれません。
作品や成果物
完成した作品やサービスだけでなく、そこに込められたストーリーも大切な強みです。完成までの努力や、作品に込めた想いを丁寧に聞き出すことで、共感を呼ぶ発信につながるでしょう。
発信の軸を定める
これらの方法で発見した“強み”をチーム全体で共有し、どんなメッセージを伝えていきたいかを明確にすることが、効果的な発信の土台となります。
たとえば、「一つひとつ手作業で丁寧に作っていること」を強みとして伝えるのか、「チームで協力して困難を乗り越えていること」を強みとして伝えるのか、伝えたいポイントによって発信する内容や表現は大きく変わってきます。
発信の軸をしっかりと定めることで、ブレのないメッセージを届けられるでしょう。
目を引く写真撮影のコツと著作権への配慮

発信において、写真はとても大切な要素です。見る人の心を惹きつけ、事業所の魅力を直感的に伝えることができます。高価なカメラがなくても、スマートフォンで工夫すればプロのような写真が撮影できます。
スマートフォンでもできる撮影テクニック
写真撮影で最も重要なのは光です。
自然光を最大限に活かした撮影を心がけましょう。窓際など、明るい場所で撮影することで、写真全体がクリアで生き生きとした印象になります。
作品の魅力を伝えるには、クローズアップ撮影が効果的です。細かな模様や質感、色彩に焦点を当てることで、利用者の皆さんの丁寧な仕事ぶりやこだわりが伝わります。
作業中の様子を撮影することで、臨場感や活気ある雰囲気を伝えることができます。利用者さんが笑顔で作業している瞬間や、真剣な表情で取り組んでいる姿などは、見る人に安心感や親近感を与えられます。
肖像権・著作権への配慮
写真撮影の際には、肖像権や著作権への配慮が不可欠です。
顔が写ってしまう写真を発信する際は、事前に本人やご家族から必ず許可を得ましょう。特に、SNSでは写真が拡散される可能性があるため、慎重な対応が求められます。
プライバシー保護のために、顔がわからないよう後ろ姿や手元だけを写すなどの工夫も有効です。
作品自体にも著作権が発生する場合があるため、発信する前に著作権について確認することも大切です。
魅力的な写真が発信の成功を大きく左右することを覚えておいてください。
読者の心をつかむ文章作成のポイント
発信の際、写真だけでなく、読者の心をつかむ文章も欠かせません。伝えたいことが多すぎると読みにくくなってしまうため、シンプルで分かりやすい文章を意識しましょう。
伝えるべき3つの要素
文章を作成する際には、以下の3つの要素を意識することで、読者の心に響くストーリーが生まれます。
「誰が」
利用者さんの個性や人柄を伝える要素です。例えば「Aさんが」「Bさんと協力して」のように、具体的な人物や関係性を伝えると親近感がわきます。
「何をしたか」
具体的な活動内容や作品について説明する要素です。「丁寧にこの作品を作り上げました」「新しい企画を考えました」といった具体的な行動を記します。
「どんな想いがあるか」
作品に込められた気持ちや喜びを伝える要素です。「完成したときの達成感でいっぱいです」「この作品で誰かを笑顔にしたいです」といった感情を言葉にすることで、共感を呼ぶことができます。
読みやすい文章の工夫
- 専門的な言葉は避け、誰もが理解できる平易な言葉を選ぶことも重要です。
- 箇条書きや短い段落を適度に使うことで、文章全体が読みやすくなります。
- 句読点を適切に使い、一文を短く区切ることで、文章の理解力が低い人にも伝わりやすくなります。
文章作成では、利用者さんの温かい人柄や、作品に込められた喜びや苦労といった感情を伝えることを意識しましょう。単なる活動報告ではなく、そこに込めた想いを伝えることで、読者との間に心のつながりが生まれるはずです。
SNS・地域の媒体を活用した効果的な発信術

発信活動を効果的に行うためには、発信する媒体の特徴を理解し、使い分けることが重要です。SNSは無料で始められるため、手軽に情報を拡散できる強力なツールです。
SNSごとの活用方法
主なSNSについて、有効と思われる活用方法は以下のとおりです。
写真や動画の投稿がメインとなるため、作品の魅力を視覚的にアピールするのに最適です。おしゃれな写真や短編動画を定期的に投稿することで、多くの人に興味を持ってもらえます。
文章も写真もバランスよく投稿できるため、活動の背景や想いを詳しく伝えたいときに活用すると良いでしょう。地域コミュニティとの交流やイベント告知にも向いています。
X
短い文章で最新情報や日常の出来事を気軽に発信できます。リアルタイムな情報発信や、イベントの様子などを伝える際に便利です。
地域コミュニティへのアプローチ
SNS以外にも、地域コミュニティへのアプローチも大切です。
- 地元のマルシェやイベントにブースを出店することで、直接地域の方々と交流できます。
- 地域の掲示板にポスターを貼ったり、ミニ広報誌を作成して商店街などに置かせてもらったりすることも有効です。
様々な方法を組み合わせることで、事業所の認知度を高めることができるかもしれません。
発信活動を継続させるための組織運営のコツ
発信活動を一時的なものにせず、継続させるためには、組織的な運営が鍵となります。無理のない範囲で、発信を担当する役割を決めておくことをお勧めします。
役割分担と連携
発信担当者を複数人設けることで、一人に負担が集中することを避けられます。写真撮影担当、文章作成担当、SNS投稿担当など、役割を分けるのも良い方法です。
発信のテーマや内容を定期的に話し合う機会を設けることで、ネタ切れを防ぎ、新鮮な情報を届け続けることができます。
利用者さんとの連携
発信活動は利用者さんとの連携によって、より豊かなものになります。
たとえば、利用者さんに「今度この作品についてSNSで紹介してもいいですか?」と直接話しかけたり、投稿内容への感想を聴いてみたりするのもよいでしょう。そうすることで、発信が単なる一方的な情報伝達ではなく、皆で作り上げる喜びへと変わります。
発信を通じて、「自分の仕事が社会に認められている」と感じることが、利用者さんのモチベーション向上にもつながるでしょう。
発信活動を組織的に管理し、無理なく続けることで、事業所がさらに活気あふれる場所になるかもしれません。
まとめ

就労継続支援A型事業所の発信は、利用者の皆さんの“強み”を社会に伝え、自信につなげる大切な取り組みです。作品や対話からストーリーを見つけ、自然光を活かした写真や共感を呼ぶ文章で魅力を伝えましょう。
SNSの特性を理解して使い分け、地域コミュニティとも連携することで、より多くの人に届けることができます。役割分担と計画的な運営で、活動を無理なく継続させましょう。
あとがき
この記事を書いた私も、就労継続支援A型事業所に通所している一人です。事業所での仕事を通じて、社会とつながる喜びや、仲間と協力する大切さを日々感じています。
だからこそ、こうした活動を多くの方に知ってほしいという想いが、この記事を書く大きなきっかけとなりました。
利用者が心を込めて作った作品や、日々の前向きな取り組みを発信することで、A型事業所が単なる福祉施設ではなく、誰もが自分らしく輝ける場所として、社会に理解されることを願っています。
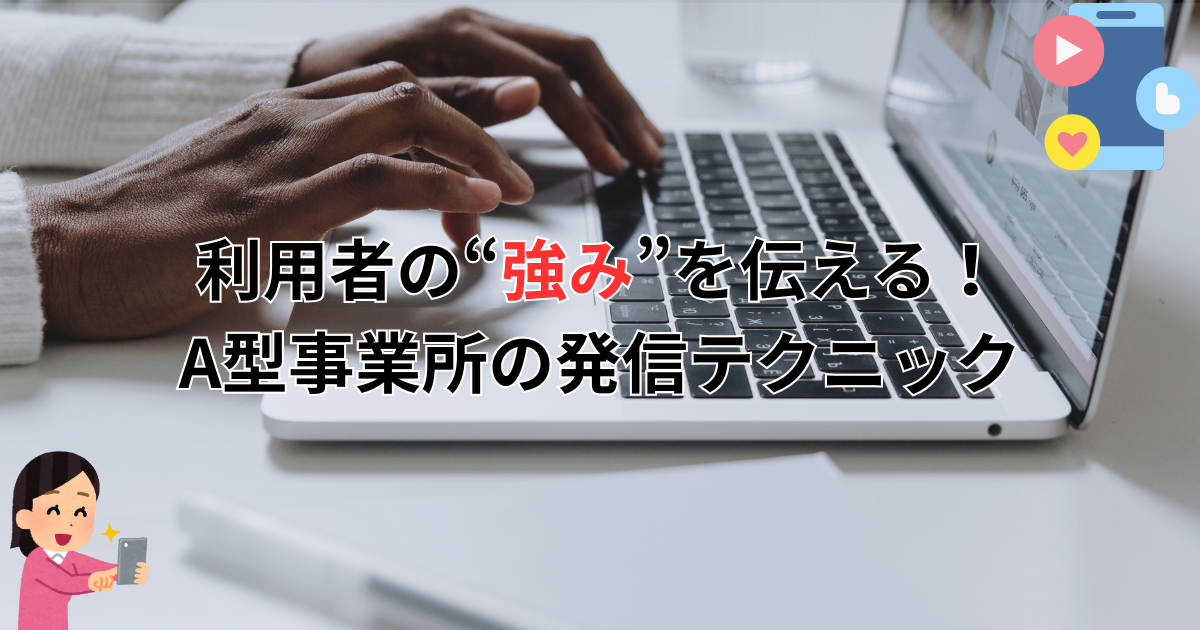
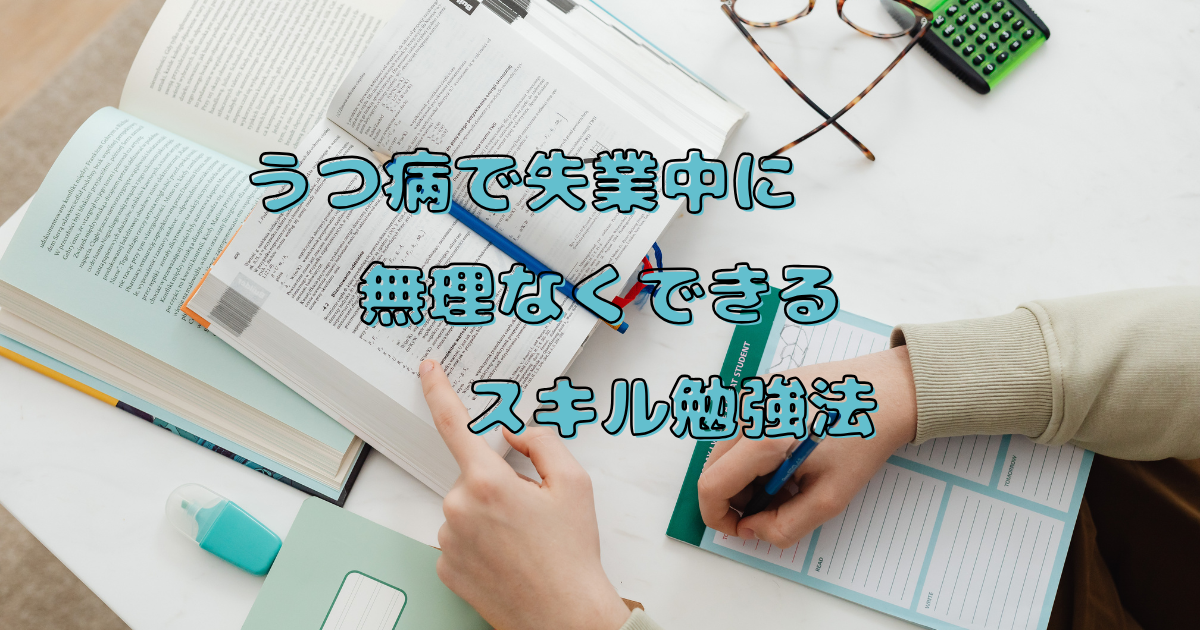

コメント