ボーダーラインパーソナリティ症(境界性パーソナリティ障害)を抱えていると、感情や人間関係に悩みながら働くことも多いです。この記事では、就労継続支援A型の利用者として、自分の特性と折り合いをつけながら、無理なく仕事に取り組むためのヒントをお届けします。
第1章:ボーダーラインパーソナリティ症とは?
ボーダーラインパーソナリティ症、よく使われる言い方では「境界性パーソナリティ障害(BPD)」といいます。
聞いたことはあっても、どんな特徴があるのか実はよく知らないという人も多いかもしれません。その特徴について見ていきましょう。
境界性パーソナリティ障害(BPD)ってどんなもの?
BPDには、精神的なストレスに対してとても敏感に反応してしまう傾向があります。そのため、ちょっとしたことで強い怒りや悲しみ、不安を感じやすく、自分でも感情がコントロールできずに戸惑ってしまうことがあるんです。
感情が不安定になりやすいのはなぜ?
自分の中の「自信のなさ」や「孤独感」が根っこにあることが多く、相手の言動に過剰に反応してしまう場面も出てきます。「嫌われたかも」「もうダメかも」と思い込んでしまうのも、特性の一部です。
対人関係が極端になりやすい特徴
「この人しかいない!」と一気に依存してしまったり、逆にちょっとしたすれ違いで「もう無理!」と極端に距離を取ってしまうなど、白か黒かで人を見てしまいやすいのも特徴のひとつです。
「見捨てられ不安」とは?
もっとも大きなキーワードが「見捨てられ不安」です。相手にちょっとでも冷たくされたと感じると、「嫌われた」と思い込んでしまい、パニックや自傷に走ってしまうこともあります。
こうした特性が生活や仕事にどう影響するか
これらの特徴は、日常生活だけでなく、職場でも大きな影響を与えがちです。たとえば、ちょっとした注意に過剰反応してしまったり、人間関係で疲れ切ってしまうこともあります。
ただし、特性を理解し、少しずつ対処法を見つけていくことで、無理のない働き方も可能になります。
第2章:就労継続支援A型とは?

ボーダーラインパーソナリティ症を抱えている方が、社会とのつながりを保ちながら自分らしく働く場として注目されているのが、就労継続支援A型事業所です。ここでは、安心して働けることが何よりも大切にされています。
A型事業所ってどんなところ?
就労継続支援A型とは、障がいなどのある方に福祉的なサポートを提供しながら働く場所を与えるサービスです。特徴的なのは、A型では実際に雇用契約が結ばれ、最低賃金が支払われる点です。
つまり、単なる作業場ではなく、仕事の場として位置づけられています。
支援員がそばにいる安心感
職場には「支援員」と呼ばれるスタッフがいて、困ったときにすぐ相談できる環境が整っています。人間関係や作業の進め方について悩んだときも、ひとりで抱えずにすむのがA型の良さです。
ボーダーライン症の人に向いている理由
感情の波が激しい方にとって、「サポートがある場所で働ける」という安心感はとても大きな力になります。就労継続支援A型は、そうした人にとって、自分を大切にしながら社会とつながるための貴重なステップとなるのです。
第3章:日々の中で感じやすい「困りごと」とその対処法
ボーダーラインパーソナリティ症とうまく付き合っていくためには自分の特性を理解することが大切です。自分でできる工夫から始めてみましょう。
感情が急に落ち込むときのセルフケア
ボーダーラインパーソナリティ症の特性のひとつに、感情の急な落ち込みがあります。そんなときは、まず無理に明るくなろうとせず、深呼吸や小休憩を取り入れて、心をクールダウンさせてみましょう。
急にイライラしてしまったときの対応策
作業中に他人のちょっとした行動に強い怒りが湧いてくることもあります。そんなときは、自分を責めるのではなく、「今、疲れているかも」と内面に目を向けてみましょう。イライラは環境や体調のサインでもあります。
「見捨てられたかも」と思ったときに意識したいこと
支援員さんや同僚に少しそっけない態度を取られただけで、「嫌われた?」「見捨てられた?」と不安になることはありませんか。
そんなときは、「事実と感情を切り分ける」ことを意識してみましょう。相手の気持ちは自分の想像と違う場合も多いのです。
スケジュールや業務量に振り回されないコツ
作業が詰まってくると焦りが強くなり、パニック状態になることもあります。そんなときは、今日やるべきことを紙に書いて一つずつ確認し、優先順位をつけることで落ち着きを取り戻せます。
第4章:職場での人間関係を穏やかに保つコツ
就労継続支援A型の業務で、感情の波をうまく乗りこなしながら周囲の方々と関係性を築いていく方法について見ていきましょう。
支援員さんとの関係を良好に保つコツ
支援員さんは、あなたの心強い味方です。だからこそ、距離が近すぎてすれ違いが起きることもあります。
もしも支援員さんに対して「なんか違うな」と感じたら、感情的にぶつかる前に「少しお話しできますか?」と落ち着いて声をかけてみましょう。そうすれば、関係が悪化することなく、きっとお互いの理解を深められます。
苦手な相手がいるときの距離感の取り方
苦手な人と無理に仲良くしようとすると、かえってストレスが増します。「適度な距離を保つ」ことは自分を守る手段です。あいさつや必要な会話はしつつも深入りしすぎない関係を意識してみましょう。
衝動的に言ってしまったあとにできるリカバリー
感情が先走って、つい強い言葉を使ってしまったということもあるでしょう。そんなとき「さっきはごめんなさい」と短く一言伝えるだけで、関係は修復できます。言い過ぎたことを認める勇気は、信頼を築く一歩です。
感謝やねぎらいの言葉を忘れずに伝える習慣
どんなに小さなことでも、「ありがとう」「助かりました」と声に出して伝えることは、人間関係の潤滑油になります。言葉にすることで、自分の心もあたたかくなり、相手も笑顔になりやすくなります。
「相手の気持ちもある」と一歩引く意識を持つ
思い通りにいかないとき「なんでわかってくれないの?」と思うのは自然なこと。でも、少し立ち止まって「相手にも事情があるかも」と考えてみると、感情が落ち着くことがあります。一歩引くことで、よりよい関係を築くことができます。
第5章:うまく働くための「仕組みづくり」

挫折せずお仕事を続けていくには、そうするための仕組みづくりが有効と言えるでしょう。どういった工夫が考えられるか見ていきましょう。
作業を細かく区切ることで達成感アップ
大きな作業は小さなステップに分けて取り組むと、ひとつひとつ終わるたびに「できた!」という達成感を味わえます。これが自信の積み重ねにつながり、モチベーション維持にも効果的です。
「できたこと」を記録して自信を積み重ねる
日々の業務でできたことをノートやアプリに書き留めておく習慣を持つと、自分の成長が見える化されて気持ちが前向きになります。自己否定に陥りそうなときも、振り返って自分を認めやすくなります。
支援員さんに気軽に相談できる関係性の作り方
職場にいる支援員さんは、働くうえでの心強い味方です。困ったことや不安を感じたときは、遠慮せずに話しかけてみましょう。日頃からコミュニケーションをとることで、相談しやすい関係が築けます。
第6章:周囲に頼る力を育てるという選択肢
業務に携わる際ひとりで抱えないことが長く働くコツとも言えます。どのような立ち振舞が有効と言えるのか、考えていきましょう。
自分だけで解決しようとしない
困りごとや悩みを一人で抱え込むと、心身の負担が大きくなります。無理をせずに、まずは周囲の支援員さんや家族に気持ちを伝えることから始めましょう。助けを求めることは弱さではありません。
支援員さんや主治医に伝えるコツ
「どう伝えたらわかってもらえるか」と悩むことも多いでしょう。具体的に「いつ」「どんな状況で」「どんな気持ちになったか」を伝えると、理解が深まります。メモを用意しておくのもおすすめです。
「助けて」が言えるのは立派なスキル
困ったときに「助けて」と言えることは、働き続けるうえでとても大切なスキルです。自分ひとりで抱え込まず、支援を受けることで安心して仕事に取り組めます。
まとめ

ボーダーラインパーソナリティ症の特性を理解し、無理せず続けられる「仕組みづくり」と「周囲への頼り方」を身につけることが、就労継続支援A型で働くうえでのポイントです。
がんばりすぎず、支援者と連携しながら自分らしいペースで歩んでいきましょう。少しずつできることを増やしていくことで、安定した職場生活が実現します。
あとがき
ボーダーラインパーソナリティ症といっても、一人一人の特徴は異なるため、一括りにこれが正しい対処法とは言えないだろう、と筆者は思います。
自分自身と向き合い、自分に合った対処法とはどんなものなのか、考えていく姿勢が一番大切なのではないでしょうか。

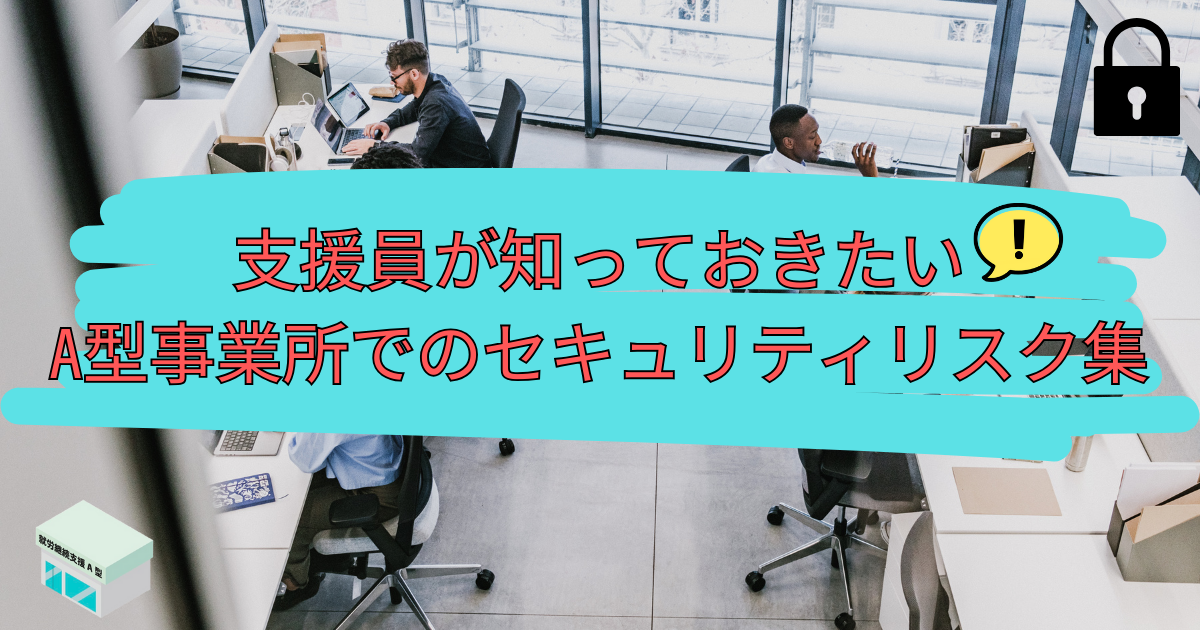

コメント