A型事業所の運営において、利用者の安全と安心を守ることは支援員の最も重要な役割の一つです。しかし、その環境には私たちが想像する以上に多くのセキュリティリスクが潜んでいます。この記事では、支援員が知っておくべきセキュリティリスクを具体的に解説します。事業所全体の安全性を高めるためにぜひ参考にしてみてください。
A型事業所に潜むセキュリティリスクとは?
A型事業所は、障がいのある方々にとって、安定して働ける場所と支援が提供される職場環境です。しかし、支援の現場という側面も持ち合わせているからこそ、多様な人と情報が交錯し、セキュリティリスクが多角的に存在します。
利用者の個人情報や健康状態、事業所が預かる委託企業のデータなどは、すべてが機密性の高い情報です。これらを守ることは、利用者の生活基盤や信頼だけでなく、事業所自体の社会的信用や将来にも直結します。
利用者ついて、障がい特性によって情報リテラシーに差が生じることもあります。また支援員やスタッフも入れ替わりが多い職場では、セキュリティ教育の徹底が特に難しくなる場合もあるでしょう。
油断や慣れや思い込みによるミスから、標的型のサイバー攻撃や悪意ある外部者による侵入まで、危険は様々なかたちで現れます。A型事業所で働くすべての人が「自分ごと」としてリスクに向き合い、日々の行動・意識の積み重ねで、安全と信頼を守っていく姿勢が求められます。
【情報漏洩】個人情報や業務データの管理不備

A型事業所で扱われる利用者の個人情報は、氏名・住所・電話番号など基本情報だけに留まりません。さらに詳細な情報が管理されることになります。
例えば、障がいの内容や支援内容、日々の記録や健康状態、さらにはご家族の連絡先や支援先の医療・福祉機関の情報まで、日常的に数多くの機微な情報がやりとりされているのです。
また、利用者情報のみならず、取引先企業や委託元からの業務データを扱うこともあります。もしこれらが外部に漏洩すれば、信用失墜や損害賠償、さらには法令違反の問題にも発展しかねません。情報漏洩リスクは、いわゆる「サイバー犯罪」だけが原因ではありません。
たとえば日常業務の中で、書類を机上や共用スペースに出しっぱなしにしてしまったり、USBメモリやノートPCの紛失、メールやFAXの送信ミスなど、ほんの些細な油断や確認不足が、大きな事故につながるケースが多いのです。
また、「このくらい大丈夫だろう」「自分が見ているから平気」という油断や慣れが、情報管理の最大の落とし穴となります。
書類やデータの徹底管理
書類の放置や持ち出しのルール違反は、外部からの侵入者だけでなく、内部の関係者による誤閲覧・誤持ち出しも引き起こします。机の上や棚の上に書類を放置せず、離席や終業時には必ず鍵付きキャビネットや引き出しにしまう習慣を徹底しましょう。
不要になった書類は必ずシュレッダーで細断し、裏紙利用時も表面に個人情報や機密データが含まれていないか確認が不可欠です。
さらに、外部に持ち出すデータはUSBメモリなど外部媒体の暗号化を義務付け、持ち出しの許可や返却の履歴も明確に記録しておくことが大切です。
- 書類・データの施錠管理
離席時や終業時に必ず施錠・管理し、裏紙利用時も内容を確認する - 外部媒体の管理
持ち出しは管理台帳や許可制とし、データは原則暗号化する
メールやFAXの送信ミス対策
メールやFAXでの誤送信も、情報漏洩リスクの大きな原因です。
特に、アドレスの手入力やアドレス帳からの選択ミス、似た名前の利用者や企業への送信間違いは珍しくありません。添付ファイルの誤送付も含め、「送信前に宛先・本文・添付ファイルの内容を指差し確認」するくらい慎重さを意識しましょう。
重要な情報や個人データを送信する際は、パスワード付きファイルや暗号化の工夫を併用し、パスワードは別経路(電話や別メール等)で伝えるとより安全です。
【不正アクセス】サイバー攻撃による脅威
A型事業所もサイバー攻撃のターゲットになりうる時代です。規模が小さいから大丈夫、個人情報の量が多くないから平気という油断が危険を招きます。攻撃者には、むしろセキュリティ対策が甘い小規模事業所を狙う傾向もあります。
保有するデータは、犯罪グループにとっては十分な価値があるため、不正アクセス・情報窃取・業務妨害の標的になりかねません。
フィッシング詐欺・ウイルス感染
近年、実在する銀行や行政機関を装ったメールで、アカウントやパスワード、個人情報を盗み取るフィッシング詐欺が横行しています。「アカウント停止」「セキュリティ警告」などの文言で焦らせ、偽サイトへ誘導し情報入力を促します。
また、添付ファイルを開かせてウイルスに感染させたり、業務PCやサーバー内のデータを勝手に暗号化して身代金を要求するランサムウェアも広がっています。
- 不審メールの対応
怪しいメールや添付ファイルは絶対に開かず、管理者へ必ず相談する
システム・ソフトの脆弱性対策
パソコンやシステムの「脆弱性(セキュリティの穴)」を放置しておくと、外部から不正侵入しやすい状態となって危険です。OSや業務ソフト、ウイルス対策ソフトのアップデート通知がきたら、面倒でも速やかに適用し、常に最新の状態を保ちましょう。
また、不要なアプリケーションやサービスは削除しておくことも大切です。
【物理的脅威】部外者の侵入や盗難リスク
デジタルだけでなく、物理的なセキュリティ対策も欠かせません。施錠忘れや出入り口管理の甘さが、部外者の侵入や盗難、悪意ある第三者による情報流出のきっかけになることもあります。
また、現金や高価な備品、職員・利用者の私物などの盗難も現実的なリスクです。
出入り管理・来訪者チェック
来訪者には必ず用件確認と名札着用を徹底し、受付を通さずに勝手に入れるスペースを作らないよう気を付けます。職員も、見慣れない人物を見かけた際は声掛けし、不審者を近づけないことが大切です。
現金・備品・私物の管理
工賃や経費で扱う現金、ノートパソコン・タブレットなどの高価な備品は、盗難のターゲットになりやすいものです。
金庫や鍵付きのキャビネットを利用し、出し入れは必ず管理台帳で記録しましょう。また、更衣室や休憩室には鍵付きロッカーを用意し、私物は施錠を徹底します。
- 物品と現金の管理
施錠・来訪者管理を徹底し、現金や備品・私物は台帳管理やロッカー保管する
【内部リスク】利用者・職員のうっかり情報漏洩

セキュリティ事故の多くは、悪意ある外部者だけでなく、内部の職員や利用者による「うっかりミス」「知識不足」「ルールの未理解」が原因で起きています。
日々のコミュニケーションや業務の中で、ついルールを逸脱してしまったり、「これくらいなら」と軽く考えて行動してしまうことが、思わぬ事故につながります。
SNS・口頭による漏洩防止
スマートフォンやSNSの普及により、手軽な情報発信ができる反面、無意識のうちに写真やコメントで個人情報や事業所の内部情報が外部に漏れてしまうリスクもあります。イベント写真への写り込みや、業務内容から取引先が特定されるケースも考えられます。
撮影や投稿はルールを明確化し、業務上知り得た情報はたとえ家族や友人にも絶対に口外しない意識を全員が持つことが重要です。
私物端末利用のリスク
個人スマホやタブレット、パソコンで業務データを扱うと、端末の紛失やウイルス感染、アカウント乗っ取りなどにより、情報が外部に流出する恐れが大きくなります。
原則として私物端末で業務データを管理しない・保存しない方針を明確にしましょう。
【情報リテラシーと継続的な教育の必要性】
セキュリティルールは「なぜ必要か」「自分の行動がどう影響するか」を職員・利用者全員が理解してはじめて機能します。
ルールを守らせるだけでなく、実際の事故事例やヒヤリハット体験を共有し、「こうすれば安全だった」「こういう事例で危なかった」など、現場の声を活かした教育を継続的に行うことが大切です。研修や定例ミーティングで、日常の小さな不安や疑問を自由に話せる雰囲気を作りましょう。
- 事例共有と意識向上
職員・利用者全員で事故事例や体験談を定期的に共有し、知識と意識をアップデートする
【セキュリティを守る日常のチェックポイント】
セキュリティを守る最強の対策は、日々の小さな積み重ねです。誰か任せにせず「自分の行動がリスクになる」ことを常に意識し、日常的な基本動作を徹底しましょう。
- 机上と情報の施錠管理
離席・終業時は机上を整理整頓し、書類・データの施錠と管理を必ず実施する - パスワード管理と報告体制
パスワードを管理・定期更新し、紛失や盗難時は迅速に報告できる体制を整える - 相談・報告の文化
気になることや心配なことはすぐに相談・報告する文化をつくる
全員の地道な意識と行動が、安全で安心なA型事業所づくりの“土台”となります。
まとめ

A型事業所では、情報漏洩やサイバー攻撃、盗難、うっかりミスなど様々なセキュリティリスクがあるため、書類やデータの厳重管理・送信時の確認・来訪者や端末管理・定期的な教育や情報共有が重要です。全員の意識と日々の行動で安全な環境を守りましょう。
あとがき
この記事を書きながら、改めてA型事業所の日常には多くのセキュリティリスクが潜んでいること、そして一人ひとりの意識や行動がいかに大切かを実感しました。
特別な対策だけでなく、毎日の小さな気配りや確認の積み重ねが、利用者やスタッフの安心・安全につながるのだと強く感じます。現場で働く皆さんが、この記事をきっかけに「自分ごと」としてセキュリティに向き合うヒントになれば嬉しいです。
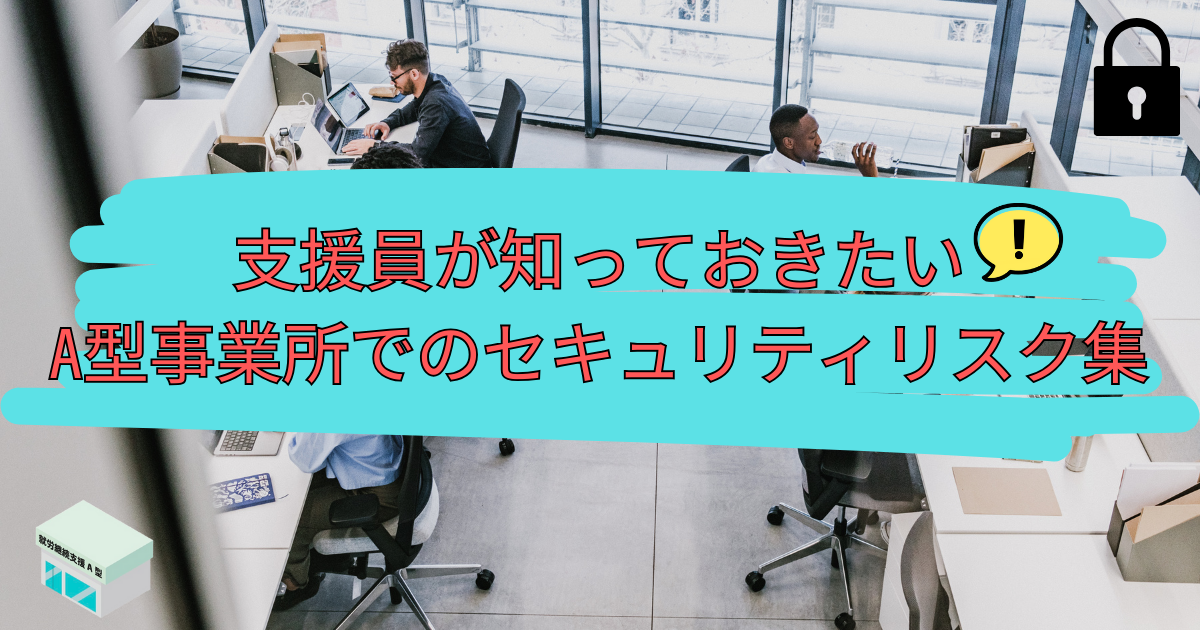
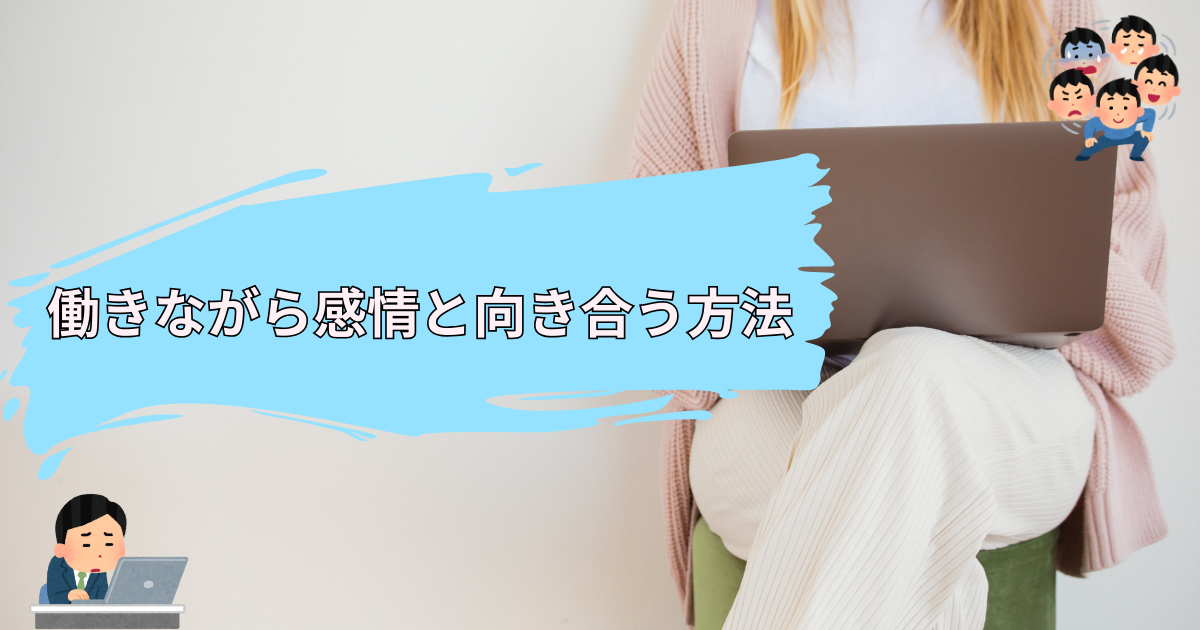

コメント