最近「物忘れが増えたかな?」「親の様子が少し心配」と感じていませんか?認知症は特別な病気ではなく、誰もがなり得る可能性のある身近な病気です。しかし、正しく理解し、日々の生活で適切な予防と対策を行うことで、発症のリスクを減らしたり、進行を緩やかにしたりできる可能性があります。不安を抱えるご本人やご家族が、前向きな一歩を踏み出すために、本記事では、認知症の基礎知識と予防・対策に役立つ情報をご紹介します。
認知症とは?正しく理解する第一歩
認知症という言葉を聞くと、漠然とした不安を感じるかもしれません。しかし、認知症は単なる「加齢による物忘れ」とは根本的に違う病気だと理解することが、最初の一歩です。
認知症とは、病気や怪我によって脳の細胞が破壊されたり働きが悪くなったりすることで、記憶や思考、判断力などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。
単なる物忘れは、体験の一部を忘れても、体験したこと自体は覚えているものです。例えば、「昨日の夕食のおかずを思い出せない」といった場合です。
一方で、認知症による物忘れは、体験したこと自体をすっぽりと忘れてしまい、その事実を指摘されても思い出せないことがあります。例えば、「昨日の夕食を食べたこと自体を覚えていない」といった状態です。
認知症は、特別な人だけがなる病気ではありません。不安に思うかもしれませんが、「私だけではない」と知ることが大切です。適切な知識と準備があれば、過度に恐れる必要はないのです。
大切なのは、もしもの時に備えて、「予防と対策」に意識を向けることです。認知症は治らない病気と思われがちですが、早期発見と適切なケアで進行を遅らせ、自分らしい生活を長く続けることができるのです。
知っておきたい四大認知症の種類と特徴

認知症にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。代表的なものを知っておくことで、症状に気づきやすくなるかもしれません。
アルツハイマー型認知症
認知症の中で最も多く、初期には記憶障害が目立ちます。新しいことを覚えられなくなったり、ものの名前が出てこなくなったりすることがあります。多くは緩やかに進行するとされています。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血など、脳の血管の病気によって引き起こされます。症状の現れ方が、ダメージを受けた脳の部位によって異なり、まだら認知症と呼ばれることもあります。手足の麻痺など身体症状を伴うこともあります。
レビー小体型認知症
特徴的な症状として、実際にはないものが見える幻視や、パーキンソン病のような症状(手足の震え、動作が遅くなるなど)が現れることがあります。症状に波があり、調子の良い時と悪い時があるのも特徴です。
前頭側頭型認知症(FTD)
主に前頭葉や側頭葉の萎縮によって起こり、人格の変化や社会性の低下、同じ行動を繰り返すといった特徴的な症状が見られることがあります。比較的若い世代で発症することもあります。
これらの違いを知ることは、適切な診断と治療に繋がります。不安を感じたら、「どのタイプだろう?」と心配するよりも、まずは専門家への相談を考えてみましょう。
脳を育む!今日からできる生活習慣の改善
認知症の予防に最も重要なのは、日々の生活習慣を見直すことです。特別なことではなく、「運動」「食事」「睡眠」の三本の柱を意識することが、脳の健康を守る鍵となります。
運動で脳を活性化する
適度な運動は、脳の血流を良くし、神経細胞の成長を促すことが分かっています。ウォーキングやジョギングといった有酸素運動は特に有効です。
週に数回、少し汗をかく程度の運動を習慣にしてみましょう。「運動をすると頭がスッキリするなぁ」と感じたら、それが脳への良いサインかもしれません。
脳が喜ぶバランスの良い食事
食事では、地中海食と呼ばれるような、野菜や魚、オリーブオイルなどを多く含む食事が認知症予防に良いとされています。
特に、DHA・EPAを多く含む青魚や、抗酸化作用のある緑黄色野菜を意識的に取り入れると良いでしょう。塩分や脂肪分の摂りすぎには注意が必要です。
質の良い睡眠と社会的な繋がり
十分な睡眠は脳の疲労回復と、記憶の整理に欠かせません。また、友人や家族との積極的な交流は、脳に良い刺激を与え、認知機能の低下を防ぐと言われています。
趣味のサークルに参加したり、地域活動に参加したりして、社会的な孤立を防ぐことも大切な予防策です。
「もしかして?」と思った時の早期受診の重要性

もし、自分や家族の様子に「おかしいな」と感じることがあれば、それは早期受診のサインかもしれません。不安を抱えたまま過ごすよりも、専門家の意見を聞くことが大切です。
早期受診がもたらすメリット
認知症は早期に発見し、適切な治療を開始することで、進行を遅らせることができる可能性があります。
また、中には甲状腺機能の低下や慢性硬膜下血腫など、治療可能な原因で認知症のような症状が出ている場合もあり、早期に治る可能性もあります。
受診の目安となるサイン
単なる物忘れではない、以下のようなサインが続く場合は、受診を検討してみましょう。
- 仕事や家事の段取りが悪くなった
- 時間や場所が分からなくなることが増えた
- 以前はできていた複雑な作業が難しくなった
- 意欲がなくなり、好きなことにも興味を示さなくなった
これらのサインは、「疲れているのかな?」と見過ごされがちです。しかし、専門家に相談することで、適切な診断と今後の見通しを得ることができます。
家族や周囲の人ができる「寄り添う」サポート
家族が認知症と診断された時、戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。大切なのは、ご本人を責めず、その人の気持ちに優しく寄り添うことです。
認知症の方への接し方(3つの原則)
温かいコミュニケーションのために、以下の3つの原則を意識してみましょう。
- 驚かせない:急な変化や大きな声で驚かせないように、ゆったりとしたペースで話しましょう。
- 急がせない:動作や判断に時間がかかっても、焦らせずに待ちましょう。
- 自尊心を傷つけない:失敗を責めたり、子ども扱いしたりせず、一人の大人として尊重しましょう。
介護者が孤立しないためのヒント
介護は一人で抱え込まず、地域の介護保険制度や地域包括支援センターなどの公的なサービスを積極的に活用することが大切です。
家族が心身ともに健康でいることが、結果的にご本人の安心にもつながります。介護者も、自分の時間や休息を大切にしましょう。
認知症と障害を抱える家族がともに活きる道
認知症と診断されても、人生は終わりではありません。他の障害を抱えながら生活している方々と同じく、大切なのは「今、できること」や、これまでの「得意なこと」に焦点を当て、前向きに生活を続けることです。
希望を持って未来を築くために
認知症の治療やケアは進化しており、早期に適切な療法を始めることで、生活の質(QOL)を維持できる可能性が高まっています。複数の課題を抱える家族の場合、それぞれの状況を考慮した柔軟なケアプランが必要です。
診断はショックかもしれませんが、これは人生の「新たなスタート」と捉えることもできます。
地域の当事者会や家族の会で悩みを共有し、支え合うことは大きな力になります。福祉サービスを統合的に利用し、社会全体で支える意識を持つことが、家族全員が希望を持ってともに活きる道に繋がります。
まとめ

認知症は、単なる物忘れとは異なり、日常生活に支障をきたす病気ですが、過度に恐れる必要はありません。アルツハイマー型や血管性などの種類を知り、適切な予防と対策を行うことが重要です。
ご家族や周囲の人は、ご本人を責めずに優しく寄り添い、公的な支援サービスを上手に活用しましょう。認知症があっても、自分らしく活き活きと生活を続けるために、希望を持って前向きな一歩を踏み出すことが、何よりも大切です。
あとがき
今回の記事を作成する中で、認知症に対する正しい知識と、予防・対策の重要性を改めて実感しました。特に、認知症があっても希望を持って生活できるというメッセージを伝えることに、大きな意義を感じています。
「自分らしく生きる」というテーマは、私たちすべての人にとって大切なことです。
この記事が、認知症に不安を感じている方や、ご家族の支えとなっている方にとって、「心を軽くする」きっかけになり、「そうなんだぁ、少し安心した」と前向きな気持ちになれる一助となれば嬉しいです。
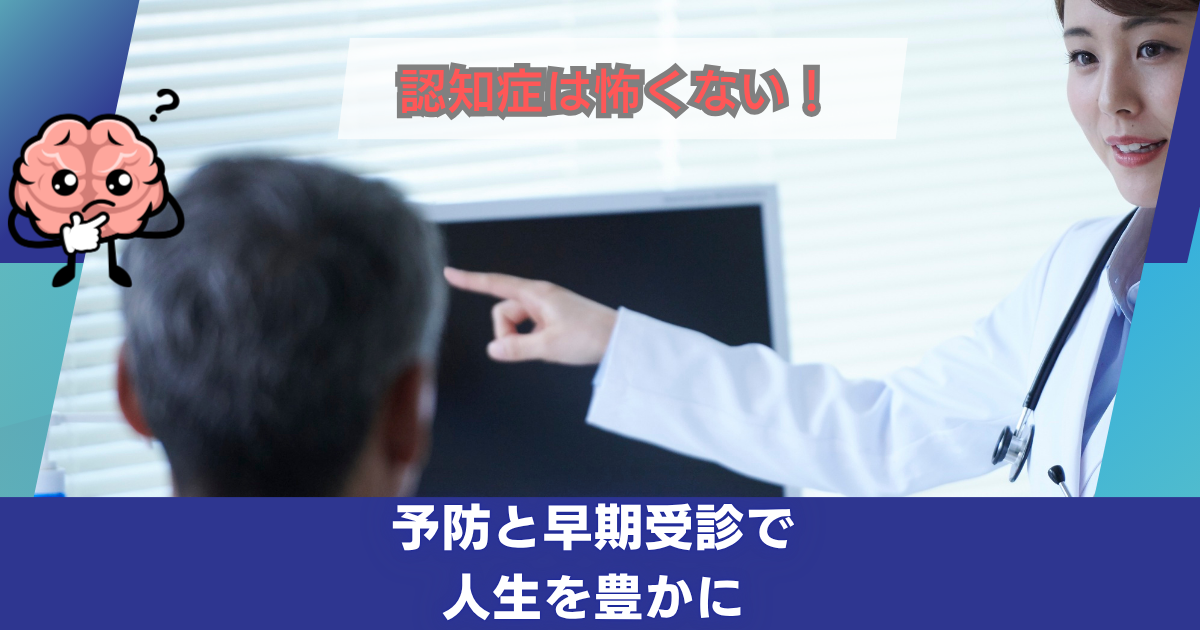
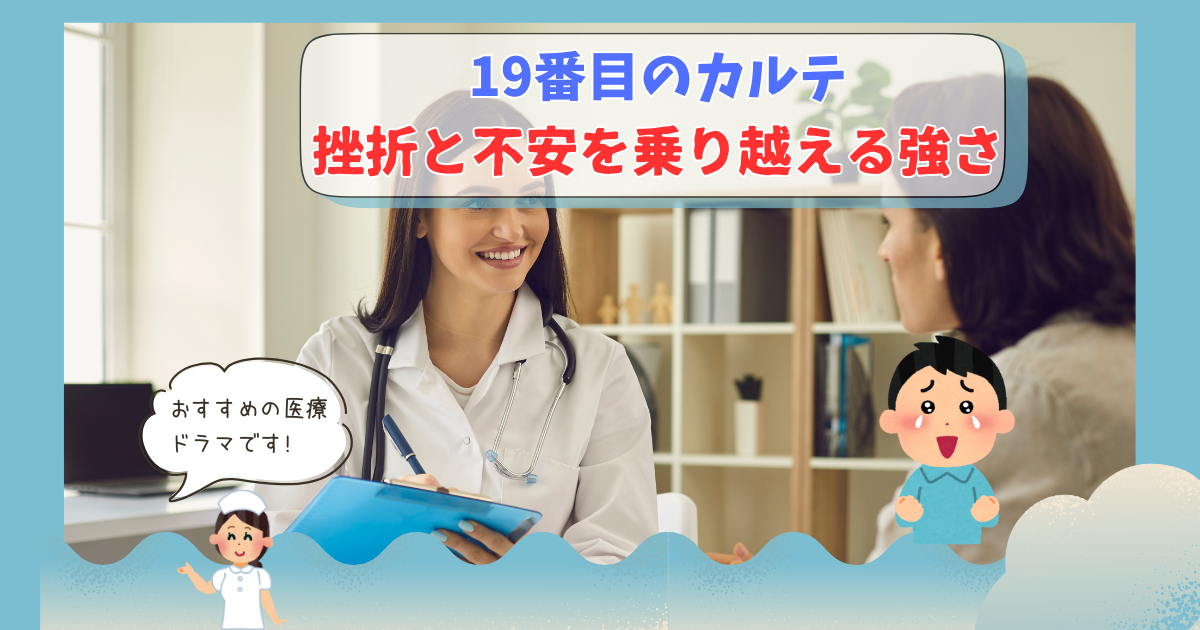

コメント