TBS系日曜劇場で放送されたドラマ「19番目のカルテ」は、松本潤さん演じる総合診療医が、身体の病だけでなく、患者の心や生活背景にある苦しみにも向き合う物語です。このドラマは挫折や不安、自信を失った方にとって希望の物語になるでしょう。本記事では、ドラマの背景にある医療の課題と、登場人物たちの成長が示すメッセージについて深掘りします。
総合診療医とは 細分化された医療への挑戦
ドラマ「19番目のカルテ」の舞台は、魚虎総合病院に新設された「総合診療科」です。この科は、特定の臓器や専門にとらわれず患者を総合的に診察する、いわば19番目の専門科として位置づけられています。
患者の全てを診る専門医
現在の日本の医療は、臓器や分野ごとに専門医が細分化されていますが、その結果、複雑な症状を抱える患者がどの科にかかれば良いのか分からず「たらい回し」にされるという課題も生じています。
総合診療医である徳重晃(松本潤さん)は、問診を武器に徹底的に患者の話を聞き、その苦しみの根源にある心や生活、社会的な背景まで見つけ出そうとします。
病名や診断だけでなく、患者の「生き方そのもの」に手を差し伸べることが総合診療科の使命と言えるでしょう。
理想と現実のギャップに悩む新米医師
ドラマのもう一人の主人公である滝野みずき(小芝風花さん)は、整形外科の新米医師から総合診療科に転科します。
彼女は「なんでも治せるお医者さん」に憧れる志を持ちながらも、現実の医療のシステムや壁に突きつけられ、理想と現実のギャップに葛藤します。
徳重と出会うことで、彼女は医師として真に大切なことを見つけ、大きく成長していきます。
このように、徳重と滝野という二人の医師が向き合う姿は、医療ドラマというだけでなく、私たちに大切な何かを教えてくれているように思えます。
そして、彼らが向き合う患者たちもまた、目に見えない様々な苦しみを抱えています。
見えない痛みと孤立 様々な障害を抱える患者

ドラマ「19番目のカルテ」では、様々な症状や困難を抱える患者が登場します。徳重が向き合う患者の中には、身体的な問題だけでなく、精神的な苦しみや社会的な孤立を抱えている人も多く描かれています。
目に見えない病との闘い
作中では、「線維筋痛症(せんいきんつうしょう)」という難病を患う患者の物語が描かれています。
線維筋痛症は、目に見えにくい全身の慢性的な痛みを伴う病気です。患者は周囲に理解されにくく、「怠けているのではないか」と誤解される苦しみに直面します。
この病を演じた俳優も、「見えない苦しみを知ってほしい」という思いを込めて役に挑んだと報じられています。
ドラマを通して、目に見えない痛みへの社会の共感を広げることが期待されました。
心の葛藤と社会的な課題
身体の病の背後には、心臓疾患の弟を介護するヤングケアラーの兄が抱える喪失感や自己嫌悪、仕事のプレッシャーからくる体調の異変など、現代の社会が抱える問題が描かれています。
徳重は、検査で異常が見つからない患者に対しても「痛みを感じ、実際に生活に支障が出ていることは、大したことだ」と優しく語りかけます。
病名がない不安を抱える患者に対し、存在を認め、寄り添う姿勢は、挫折や不安を抱える全ての人へのメッセージとも言えるでしょう。
この物語で描かれる「精神的な苦しみ・社会的な孤立」には、以下のようなものがあります。
- 線維筋痛症など、目に見えない全身の慢性的な痛み。
- 誤解や偏見による社会的な孤立や苦しみ。
- ヤングケアラーなど、家族の介護による心の葛藤と喪失感。
- 検査で異常が認められないことによる病名のない不安。
ドラマは、病と障害の定義を広げ、人の苦しみを肉体・精神・社会的な側面から統合的に捉えることの大切さを訴えています。
失敗や挫折を力に 自信を取り戻すヒント
以前の就労経験で失敗や挫折を経験し、自分の能力に自信が持てない人にとって、ドラマに登場する医師や患者の再起の物語は大きなヒントになることでしょう。
理想と現実のギャップを認める勇気
新米医師の滝野は、患者を救いたいという理想と、細分化された病院の現実とのギャップに悩んでいました。
彼女は最初、総合診療医の徳重のやり方に戸惑いますが、問診を通し患者の心に寄り添う姿勢から多くを学びます。
失敗や挫折は、「理想と現実の差」を知ることであり、それを認め、新たな方向を見つけるための成長の機会と捉えることが大切だというメッセージが伝わります。
自分の存在を肯定する言葉
徳重の医師としての優しさは、患者が抱える「自分の苦しみは大したことではない」という自己否定の感情を打ち消します。
病名がつかない不調に苦しむ患者に対し、「痛みを感じ、実際に生活に支障が出ていることは、大したことだ」と断言する言葉は、自分の能力に自信が持てず苦しむ人にとって、自分の存在や感情を肯定する力を持っています。
過去の失敗を責めるのではなく、今の自分の苦しみや感情を認めることから再起が始まることを物語は伝えています。
挫折の経験は、他者の苦しみに共感し、より深く寄り添うための力に変えられる可能性をドラマは教えてくれます。
自分のペースを見つける不安との向き合い方

自分のペースで進むことが必要でありながら、うまく進めるか不安に感じることは、多くの人が経験する感情です。ドラマに登場する人物たちも、それぞれのペースで葛藤し道を探しています。
焦りを手放す勇気
徳重の診察は、時間をかけ、患者の話をじっくり聞くスタイルです。現代の病院経営では「効率」が重視され、時間をかけることは非効率と見なされがちです。
しかし、徳重は効率よりも患者にとっての「最善」を見つけることに価値を置きます。
彼の姿は、他人のペースや世間の評価に焦るのではなく、自分の信念とペースを守る勇気を教えてくれます。
沈黙の中に隠された本意
物語の終盤で、徳重の師匠である赤池が病に倒れ、治療を拒否するかのように一切話さなくなる場面があります。問診を武器とする医師にとって、師匠の沈黙は何よりの痛手です。
しかし、徳重は沈黙の中に隠された師匠の真の思いを冷静に見つけようと行動します。
彼の姿は、私たちが不安や困難に直面した時、焦って答えを出そうとするのではなく、あえて立ち止まり、状況を深く観察することの大切さを教えてくれます。
答えは沈黙の中や、一見無関係に見える生活の中に隠されているのかもしれません。
徳重の姿勢から学べる、不安との向き合い方のヒントを以下にまとめました。
- 効率よりも「最善」を追求し、焦りを手放す勇気。
- 患者の心や生活に耳を傾け、自分の信念を貫くこと。
- 不安な時こそ、あえて立ち止まり、状況を深く観察すること。
- 答えはすぐに見つからなくても、対話を通し見つけられると信じること。
徳重が患者と向き合う姿勢は、不安を抱えながらも自分の道を見つけるための「道標」のような役割を果たしています。
まとめ

総合診療という新しい領域は、病だけでなく「人」を診る医師の物語として、私たちに医療のあり方を問いかけています。
ドラマ「19番目のカルテ」は、総合診療医という新しい医療の領域を通して、身体の病だけでなく、様々な障害や社会的な課題を抱える患者の心に光を当てる物語です。
効率を求められる現代社会で、徳重が自分のペースを貫き、時間をかけて患者と向き合う姿勢は、不安を抱える私たちに「焦ることなく、自分の信念を大切に道を進むことが大切だ」というメッセージを伝えているのではないでしょうか。
あとがき
この物語の原作は漫画です。漫画を読んでより深く知ることもできます。
私は障害を抱えています。ドラマの中のセリフで「あなたのお話を聞かせてください」「どの道を選んでも、あなたの人生はこの先も続いていく」など患者さんに向けて、優しい言葉かけや目線をしているのがとても心に響き打たれました。
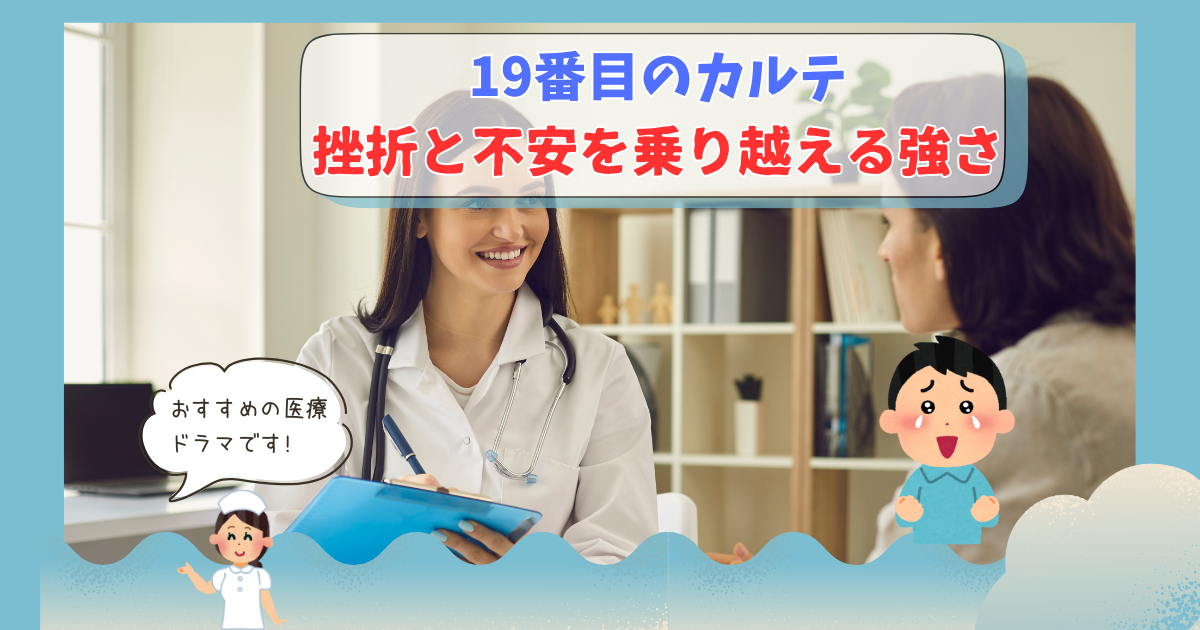
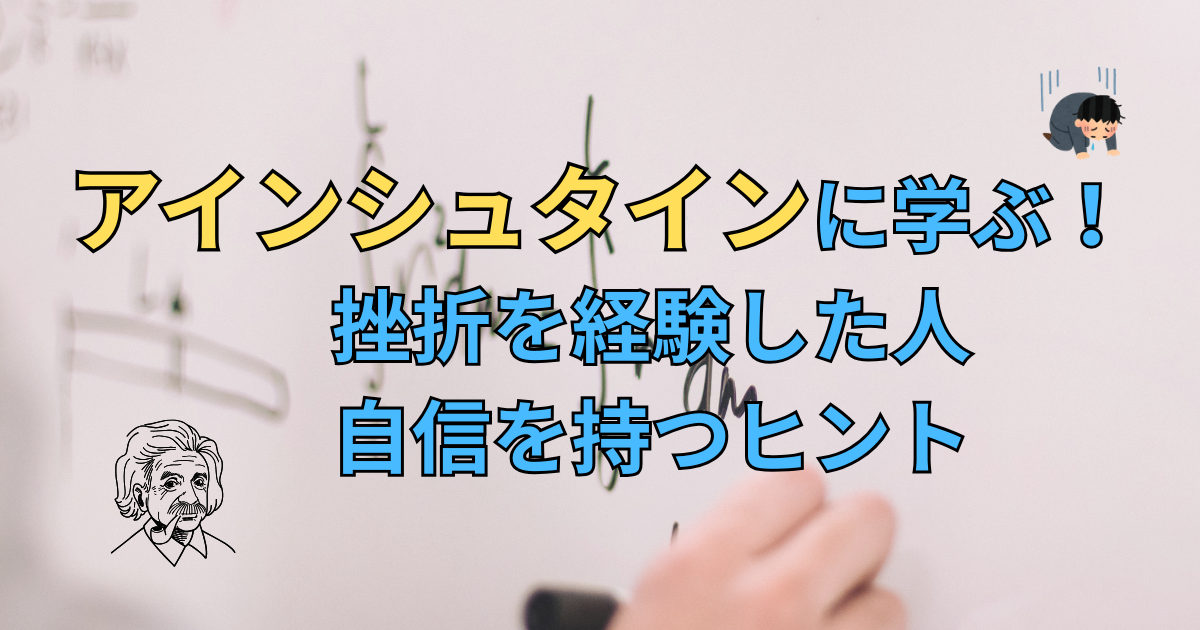
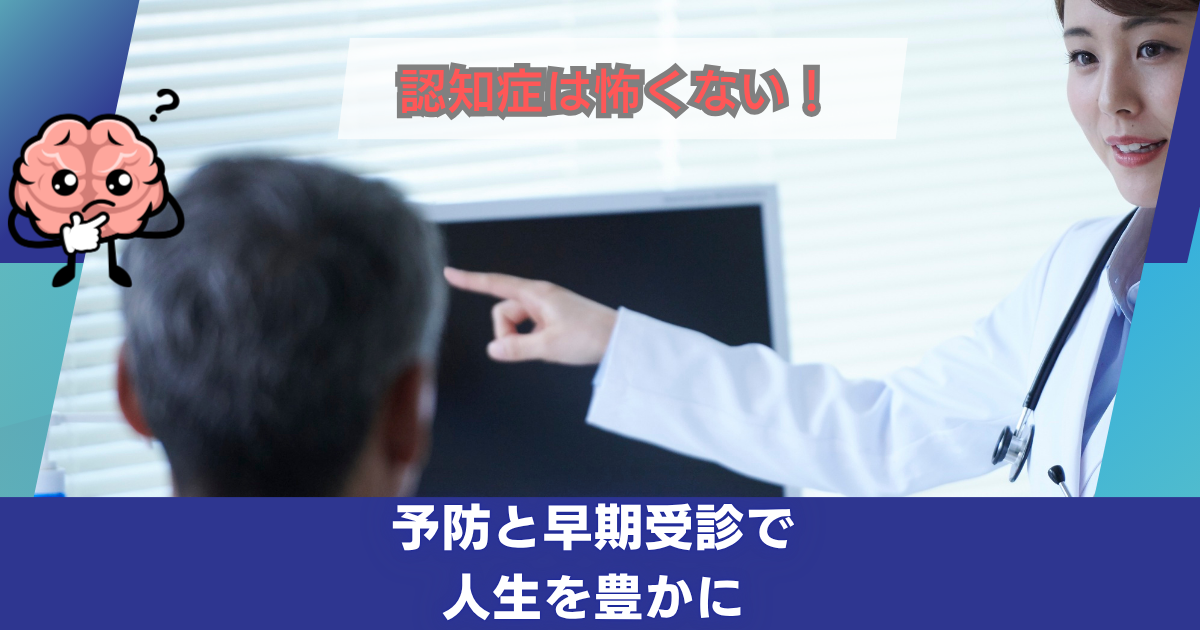
コメント