就労継続支援A型の職員さんや利用者さんの中には「Webサイト作成をお仕事にしたい」と思っている方もいらっしゃることでしょう。そんな方々に向けてWebサイト作成の基本から準備のポイントまで解説します。就労継続支援A型と関わりのない方でも参考になる内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。
第1章:Webサイトを作る目的を明確にしよう
まずは「そもそもなぜWebサイトを作るのか」という目的をはっきりさせることが大切です。この章ではWebサイトの種類や活用方法について紹介します。
そもそもWebサイトとは?ブログ・ホームページの違い
Webサイトとは、複数のWebページのまとまりのことを指します。
Webページにはいくつかの種類があり、一部を上げると日々の出来事や活動記録を発信するのがブログ、Webサイトの入口にあたるものがホームページとなるわけです。
就労支援A型で活用できるケース
就労継続支援A型の事業所がWebサイトを活用する場面はさまざまです。たとえば事業所の活動紹介を載せれば、地域の人や支援機関に取り組みを知ってもらえます。
さらに求人情報を掲載すれば、新しいスタッフや利用者の募集にもつながります。
第2章:Webサイト作成の前に準備すること

Webサイトを成功させるための最初のポイントは「目的を明確にすること」です。目的がはっきりしたら、次は実際にサイトを作る前の準備に入ります。ここを丁寧に進めることで、完成後の運営がスムーズになります。
目的とターゲットを整理する
誰に向けたサイトなのかを意識することはとても重要です。利用者や家族、地域の人、企業担当者など、ターゲットによって必要な情報は変わります。
「誰に見てもらいたいのか」を考えることで、伝えるべき内容や言葉づかいも変わってくるのです。
掲載する情報をリストアップする
次に「どんな情報を載せるのか」を整理します。事業所の基本情報やサービス内容、連絡先やアクセス方法などは必須です。
また活動内容の紹介やスタッフの想いを伝えるページを設けると、見る人に親しみを感じてもらいやすくなります。
写真・文章素材を準備する
Webサイトにとって写真や文章は欠かせません。写真は事業所の雰囲気や利用者の活動の様子を伝える大切な要素です。文章は長すぎず、簡潔で分かりやすくまとめることがポイントです。
素材を事前に集めておくことで、サイト作成の作業がぐっとスムーズになります。
A型事業所なら「利用者が関われる部分」を考える
就労継続支援A型の特色を活かすなら、利用者がサイト作成に関われる工夫を取り入れると良いでしょう。例えば写真撮影をお願いしたり、活動レポートを記事として書いてもらったりすることです。
そうすることで一緒に作り上げるWebサイトになり、利用者のやりがいやスキルアップにもつながるでしょう。
第3章:Webサイト作成に必要な基本ツールと環境
Webサイトを作るには、目的を明確にしただけでは十分ではありません。次に必要なのは、実際にサイトを運営するための環境やツールを整えることです。
この章では、初心者でも理解しやすい形で基本的なツールや選び方のポイントを解説します。
ドメイン(サイトの住所)の選び方
ドメインとは、インターネット上のサイトの住所のようなものです。わかりやすく覚えやすい名前にすると訪問者が迷わずアクセスできます。
また、事業所の名前やサービス内容を含めるとSEOにも有利です。ドメインの種類には「.com」や「.jp」などがあり、信頼性や目的に応じて選ぶことが大切です。
サーバー(サイトを置く場所)の種類と特徴
サーバーは、作ったWebサイトのデータを置いておく場所です。レンタルサーバーやクラウドサーバーなど、種類によって料金や管理の手軽さが変わります。
初心者には管理が簡単でサポートが充実したレンタルサーバーがおすすめです。サイトの規模やアクセス数に応じて最適なサーバーを選びましょう。
CMS(WordPressなど)の役割とメリット
CMSとは、Webサイトを簡単に作成・管理できるシステムのことです。
特にWordPressは無料で利用でき、多くのデザインテーマやプラグインが用意されていて便利です。専門知識がなくても本格的なサイトを作れます。更新作業も簡単で、ブログやニュース更新など、利用者が関わる運営にも向いています。
第4章:SEOを意識したWebサイトの基本設定
作ったWebサイトはただ置いておくだけでは、多くの人に見てもらえません。検索エンジンで見つけてもらうための設定を意識することが大切です。この章ではSEOの基本をやさしく解説します。
SEOとは?検索エンジンに見つけてもらうための仕組み
SEOとは「検索エンジン最適化」のことです。Googleなどの検索エンジンで上位に表示されるよう、サイトの内容や構造を整えることを指します。
正しいSEO設定を行うと、より多くの人にWebサイトを見てもらえるチャンスが増えます。
タイトルタグ・メタディスクリプションの書き方
タイトルタグは検索結果に表示されるサイト名やページ名のことです。わかりやすく、かつキーワードを含めることがポイントです。
メタディスクリプションはページの概要文で、検索結果に表示されます。文章は簡潔で魅力的に書くことで、クリック率が高まります。
見出し(H1〜H3)の正しい使い方
見出しタグはページの構造を整理するために使います。H1はページの主題、H2は章のタイトル、H3は小見出しというイメージで使い分けると、検索エンジンにも内容が伝わりやすくなります。読みやすさの面でも、利用者に優しい構成です。
内部リンク・外部リンクの基本
内部リンクは自サイト内の関連ページへのリンク、外部リンクは他サイトへのリンクです。内部リンクは訪問者の回遊率を高め、外部リンクは情報の信頼性を補強します。適切に設定することでSEO効果を高めることができます。
第5章:デザインとユーザビリティを意識した作り方

Webサイトを訪れる人が快適に使えるかどうかは、デザインや操作のしやすさに大きく左右されます。この章では、初心者でも押さえておきたい基本的なポイントをわかりやすく紹介します。
初心者でも押さえたいレイアウトの基本(シンプル・わかりやすい)
まず大切なのは、ページの構成をシンプルにすることです。情報が多すぎると訪問者が迷ってしまいます。
主要な内容はトップページにまとめ、重要なリンクやボタンは目立つ位置に配置しましょう。これだけでも訪問者の理解度は格段に上がります。
色・フォント・写真で印象が変わる
色やフォント、写真の使い方も印象を大きく左右します。色は統一感を持たせ、フォントは読みやすさを優先することがポイントです。写真は事業所の雰囲気や活動の様子を伝える重要な素材です。
適切に使うことで、訪問者に親しみや信頼感を与えられます。
スマホ対応(レスポンシブデザイン)は必須
近年はスマートフォンからアクセスする人が大半です。パソコン用のレイアウトだけでなく、スマホでも見やすいレスポンシブデザインに対応させることが必須です。
画面サイズに合わせて自動で調整されることで、どんな端末でも快適に閲覧できます。
アクセシビリティを意識した工夫(文字サイズ・色のコントラスト・読み上げ対応)
誰もが使いやすいWebサイトにするためには、アクセシビリティも意識しましょう。
文字サイズを読みやすくしたり、背景と文字のコントラストをはっきりさせたり、音声読み上げに対応させたりすることで、障がいのある方や高齢者にも配慮できます。
第6章:公開後の運用と改善のポイント
Webサイトは公開して終わりではありません。訪問者に価値を提供し続けるためには、運用と改善が欠かせません。この章では、日々の更新や改善のポイントを解説します。
定期的な更新が信頼感につながる(ニュース、活動報告、ブログ記事)
サイトに新しい情報を定期的に追加することで、訪問者に「活発な事業所だ」と印象づけられます。ニュースや活動報告、ブログ記事などを更新することは信頼感の向上につながります。
アクセス解析ツールで効果をチェックする(Googleアナリティクスなど)
どのページがよく見られているか、どのリンクがクリックされているかを知ることは改善の第一歩です。Googleアナリティクスなどの解析ツールを使うと、訪問者の行動を数字で確認でき、改善のヒントが見えてきます。
小さな改善を繰り返して「育てるWebサイト」にする
アクセスデータをもとに少しずつ改善していくことが大切です。文章の表現やボタンの位置、画像の差し替えなど、細かい改善を積み重ねることで、より使いやすく効果的なWebサイトに成長させられます。
まとめ

Webサイト作成は、目的を明確にし、必要なツールや環境を整え、デザインやSEO、運用のポイントを押さえることが重要です。
就労継続支援A型事業所での活用方法も含め、利用者が関われる部分を取り入れることで、より魅力的で実用的なサイトを作れます。
あとがき
webサイト作成の具体的な手順は、使用するCMSによって変わります。しかし、本記事で紹介してきたような、webサイトを作るにあたってやるべき項目はなんなのか、といった点を踏まえておけば、大きな問題はないでしょう。
例えばWordPressというCMSでメタディスクリプションを書く場合、具体的な入力方法に関しては、ネット等で調べればよいわけです。
やるべき事柄さえ把握しておけば、具体的な作業方法はネット情報から導き出せる、そんなIT社会ならではの利点を再確認できるとも言えるでしょう。
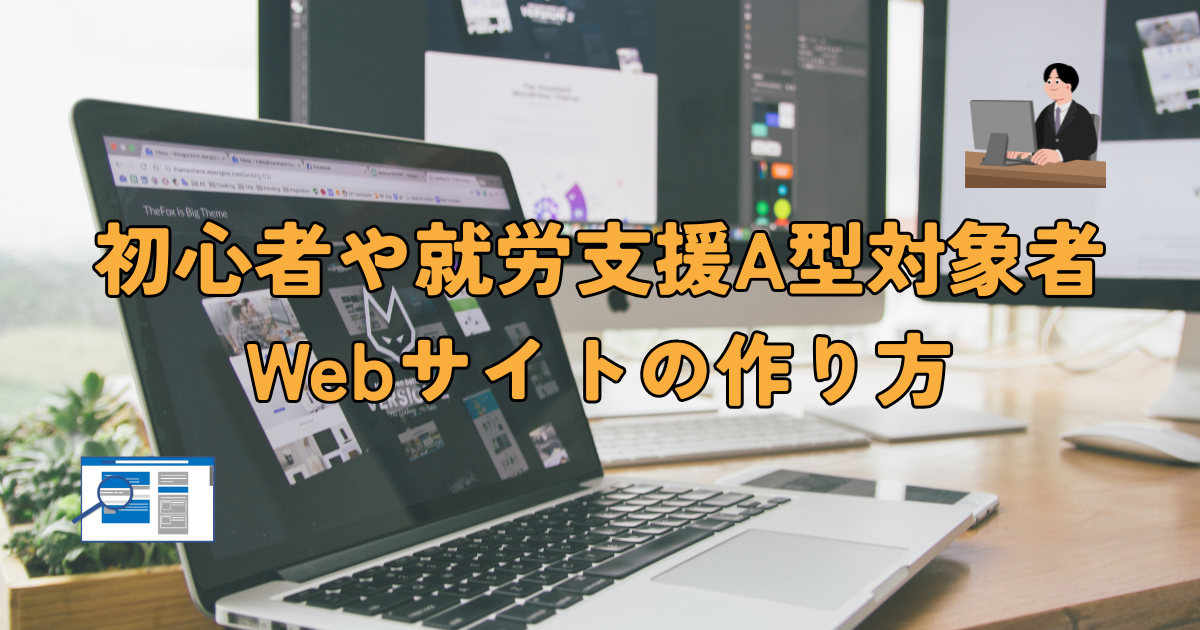

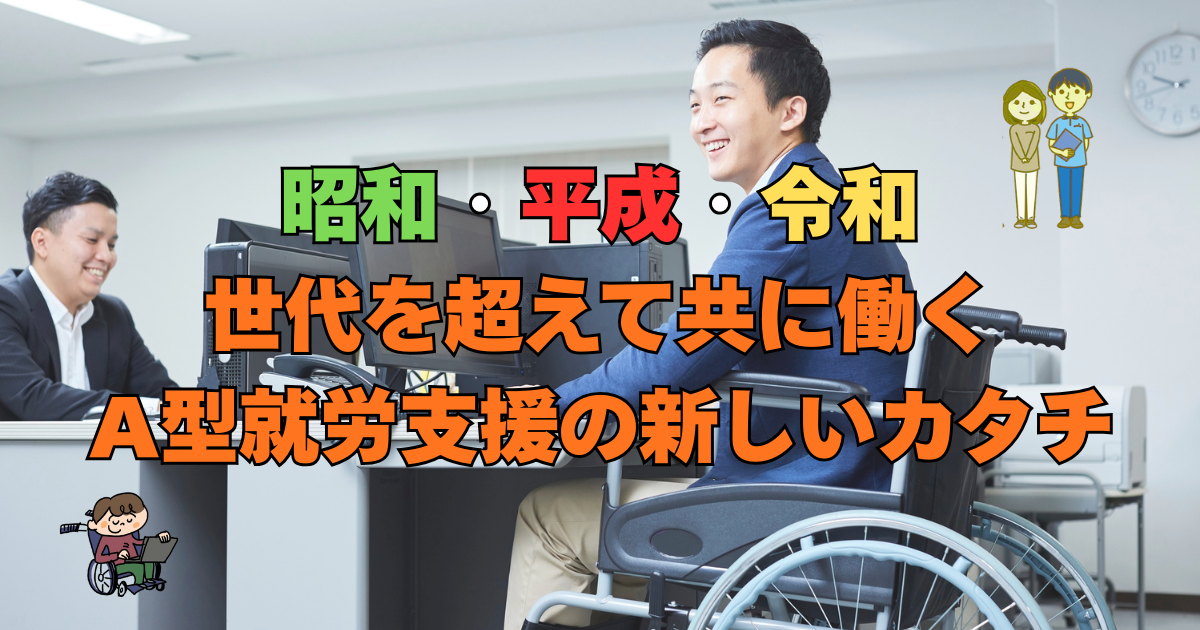
コメント