A型就労支援事業所の支援員にとって、アンガーマネジメントは、利用者様との関わりで生じる怒りやストレスを軽減するための必須スキルです。感情のコントロールを習得することは、職場全体の心理的安全性を守り、ハラスメントを未然に防ぎます。本記事では、怒りを「二次感情」として捉える基本概念や、衝動を抑える「6秒ルール」、建設的な指導のための「Iメッセージ」など、支援員が職場を健全に保ち、業務パフォーマンスの向上に繋がる具体的なテクニックを解説しました。
支援員にアンガーマネジメントが必要な理由
A型就労支援事業所の支援員は、利用者様の就労支援という責任重大な役割を担っています。しかし、その業務特性上、計画通りに進まないことや利用者様からの予期せぬ言動に直面することが多く、イライラや怒りの感情が溜まりやすい環境にあります。
この怒りの感情をそのままにしておくと、個人のストレスが増加するだけでなく、職場全体に深刻な問題を引き起こします。
アンガーマネジメントは、怒らないことを目的とするのではなく、「怒る必要のないことには怒らず」「怒るべきことには上手に怒る」ことを目指す心理トレーニングです。
支援員がこのスキルを身につけることは、業務パフォーマンスの向上や健全な職場づくりに直結します。
怒りが職場にもたらす3つの悪影響
- 支援員自身の集中力やモチベーションが低下し、業務の生産性が落ちる。
- 利用者様や同僚とのコミュニケーションの質が下がり、人間関係の摩擦が増える。
- パワハラやモラハラなどのハラスメント行為に繋がり、組織の心理的安全性を破壊する。
特に就労支援の現場では、感情的な指導は利用者様の信頼関係を損ない、支援の継続自体が困難になるリスクがあります。厚生労働省のハラスメント対策の中でも、管理職や指導者におけるアンガーマネジメントの習得が効果的であると紹介されています。
自身の感情を適切にコントロールし、理性をもって対応することが、支援員としてのプロフェッショナリズムの証明となるのです。怒りを負の感情として抑え込むのではなく、上手に付き合うことで、余計なストレスを抱え込まずに済みます。
怒りの正体を知る アンガーマネジメントの基本概念

怒りをコントロールするためには、まず「怒りとは何か」という感情の仕組みを正しく理解することが重要です。
アンガーマネジメントでは、怒りはしばしば「二次感情」として発生すると考えます。私たちは、最初に不安、悲しい、悔しい、寂しいといった感情(一次感情)を抱きます。
この一次感情が自分の許容範囲や期待を超えたときに、鎧のように、または蓋をするように二次感情である「怒り」が外側に溢れ出てしまうのです。
例えば、利用者様が約束を破ったとき、心の中では「また振り出しに戻るのか」という不安や「期待を裏切られた」という悲しみが先にあり、それが表面的な「怒り」として爆発するイメージです。
怒りは「二次感情」である理由
- 一次感情(不安・悲しみなど)を直視することが、怒りを根本的に解消する第一歩となる。
- 怒りの感情に流されるリスクを減らすことで、対人関係のトラブルや摩擦を減少させられる。
- 怒りの裏側にある本心(疲労や無力感)に気づくことで、自分を客観視し自己理解が深まる。
支援員がこのメカニズムを理解すれば、利用者様や同僚からの攻撃的な言動に対しても、「この人の怒りの裏にはどんな感情があるのだろう」と、一歩引いた視点で客観視できるようになります。
怒りをぶつけられた側も、無用なストレスを抱え込まずに済み、心身の不調の未然防止につながります。自分の怒りだけでなく、他者の怒りも構造的に捉えることが、円滑なコミュニケーションと良好な人間関係を築くための土台となるのです。
感情の爆発を防ぐ「6秒ルール」と衝動の制御
怒りを感じた瞬間に衝動的な言動を抑えることは、アンガーマネジメントのファーストステップです。強い怒りの感情は6秒ほどでピークを過ぎると言われています。
支援員はこの「6秒ルール」を習得することで、理性が働くまでの短い時間を乗り切ることが可能になります。
この衝動のコントロールこそ、反射的な言動を抑え、利用者様や同僚との関係を悪化させず、職場でのハラスメント発生を未然に防ぐ、最も効果的な即効性のあるテクニックです。
怒りのピークを乗り切る4つのテクニック
- 深呼吸をする:4~5秒かけて息を吸い、10秒程度かけてゆっくり吐き、リラックス効果を得る。
- カウントバック:心の中で100から3つずつ数を逆算し、怒りから意識をそらす。
- コーピングマントラ:心の中で「大丈夫」「落ち着こう」など魔法の言葉を唱える。
- グラウンディング:目の前のペンや壁など、怒りと関係ない物体に意識を集中させる。
これらのテクニックは、怒りの原因に目を向けるのではなく、呼吸やカウントなどの別の行動に集中することで、強制的に思考を停止させます。
また、怒りの強さを10段階で点数化する「スケールテクニック」も、自分を客観視する手助けとなります。物理的なタイムアウトとして、お手洗いなどで一時的にその場を離れることも、感情の増幅を防ぐ上で効果的な手法です。
怒りの傾向を掴む「思考のコントロール」と「べき」の線引き

怒りの衝動を抑えた後は、自分の怒りの傾向を分析し、根本的な原因に対処することがアンガーマネジメントの第2ステップです。
怒りの多くの原因は、自分の中にある「〜すべき」「〜であるはずだ」という固定観念や価値観と、現実との間にギャップが生じたときに生まれます。
支援員一人ひとりの持つ「べき」の基準は異なり、利用者様や同僚の「べき」と衝突することで、対立や摩擦が生じます。この「べき」の境界線を明確にし、許容範囲を広げることが、不必要な怒りを減らすための思考のコントロールです。
アンガーログ(怒りの記録)の活用法
- 怒りを感じた日時、場所、相手、出来事を具体的に記録する。
- 怒りの強度を10段階で点数化し、客観的な尺度で捉えることを習慣化する。
- 「なぜ怒ったか」の裏側にある「自分のべき」を言語化し、傾向を分析する。
このアンガーログを継続してつけることで、「自分は完璧主義の傾向があるから、報告の遅れに強く怒ってしまう」といった自己理解が深まります。
分析結果をもとに、許せるゾーンと許せないゾーンの境界線を明確化し、「まぁ許せる」ゾーンを意識的に広げる努力をしましょう。
また、自分の「べき」を同僚に開示・共有することで、相互理解が深まり、コミュニケーションが活性化し職場の心理的安全性が向上します。怒りを記録し分析することは、組織の生産性を高めるための重要なプロセスなのです。
ハラスメントを生まない指導法と職場環境の改善
アンガーマネジメントの最終目的は、怒りを建設的な行動に変えることです。支援員が怒りを感じた際、それを感情のまま部下や利用者様にぶつけることは、パワハラやモラハラのリスクとなり、指導の効果も下がります。
重要なのは、感情ではなく事実に基づいて指摘し、自分の要求を論理的かつ肯定的に伝えるスキルです。
感情をぶつけない「リクエスト」の伝え方
- Youメッセージ(あなたは〜)ではなく、Iメッセージ(私は〜)で自分の気持ちを伝える。
- 「なぜできないんだ」と責めるのではなく、具体的に「どうしてほしいか」を伝える。
- 非難や個人攻撃を避け、事実と改善点に焦点を当てて伝える。
例えば、「なんで報告が遅いんだ!」と怒るのではなく、「報告が遅れると、リスク管理がしづらいので、私は困ります。今後は○日前に中間報告をくれると助かります」とリクエストに置き換えます。
これにより、指導を受ける側は委縮せず、改善行動に集中できます。
アンガーマネジメントは、指導の効果を高めるだけでなく、多様性のある価値観を受け入れやすくなるというメリットもあります。
支援員全員が怒りのコントロールスキルを身につけることで、互いを尊重し合える職場環境が整い、離職率の低下や生産性向上に繋がります。アンガーマネジメントは、一時的な対処法ではなく、継続して取り組むべき組織文化なのです。
まとめ
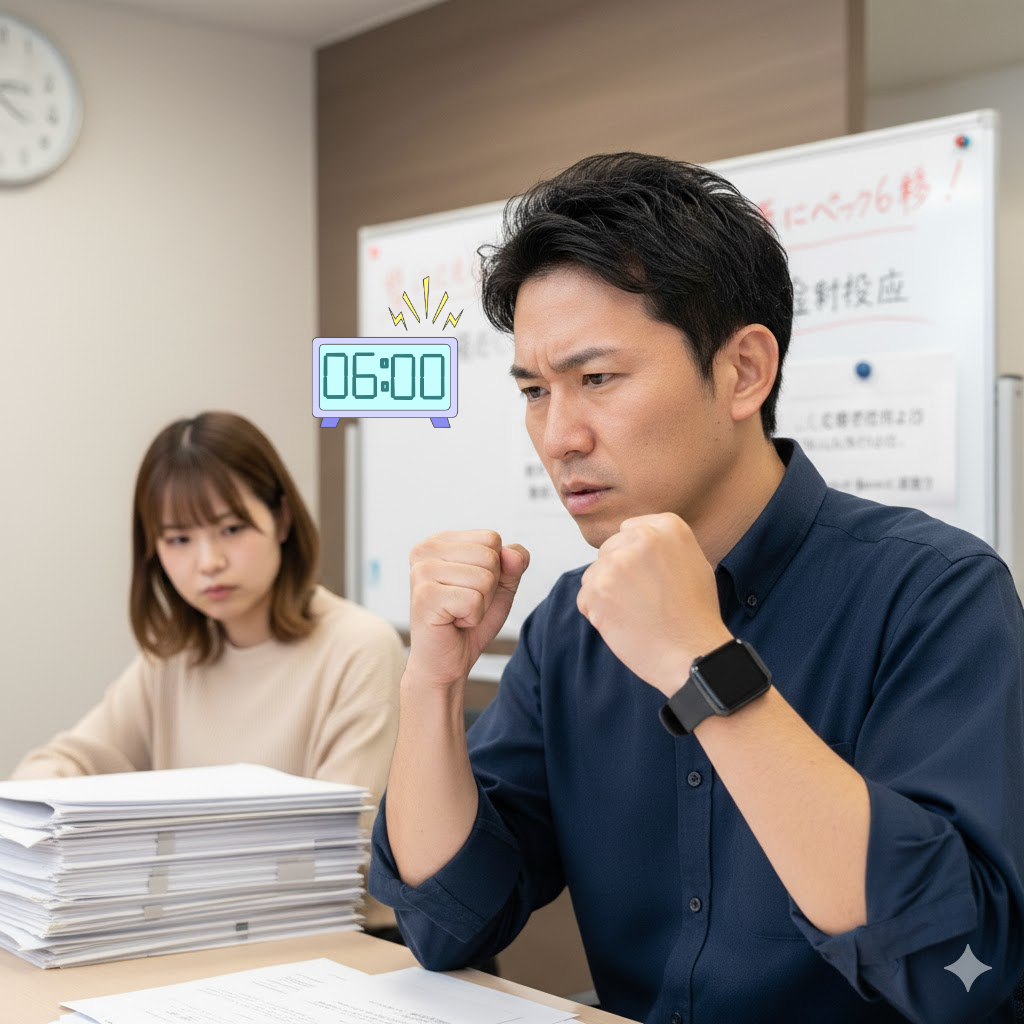
怒りを感じた瞬間に衝動的な言動を抑えることは、アンガーマネジメントのファーストステップです。強い怒りの感情は6秒ほどでピークを過ぎると言われています。
支援員はこの「6秒ルール」を習得することで、理性が働くまでの短い時間を乗り切ることが可能になります。
この衝動のコントロールこそ、反射的な言動を抑え、利用者様や同僚との関係を悪化させず、職場でのハラスメント発生を未然に防ぐ、最も効果的な即効性のあるテクニックです。
あとがき
本記事は、A型就労支援事業所の利用者である筆者が作成しました。日頃より、私たち利用者は支援員の皆様の手厚いサポートに心から感謝しています。支援という仕事は、計り知れないストレスや怒りに直面することもあると想像します。
このアンガーマネジメントの記事が、支援員の皆様の心身の負担軽減や、より良い職場環境の構築に少しでも役立てば幸いです。筆者自身も、学んだアンガーマネジメントを意識し、日々の行動に活かしていきたいと思います。
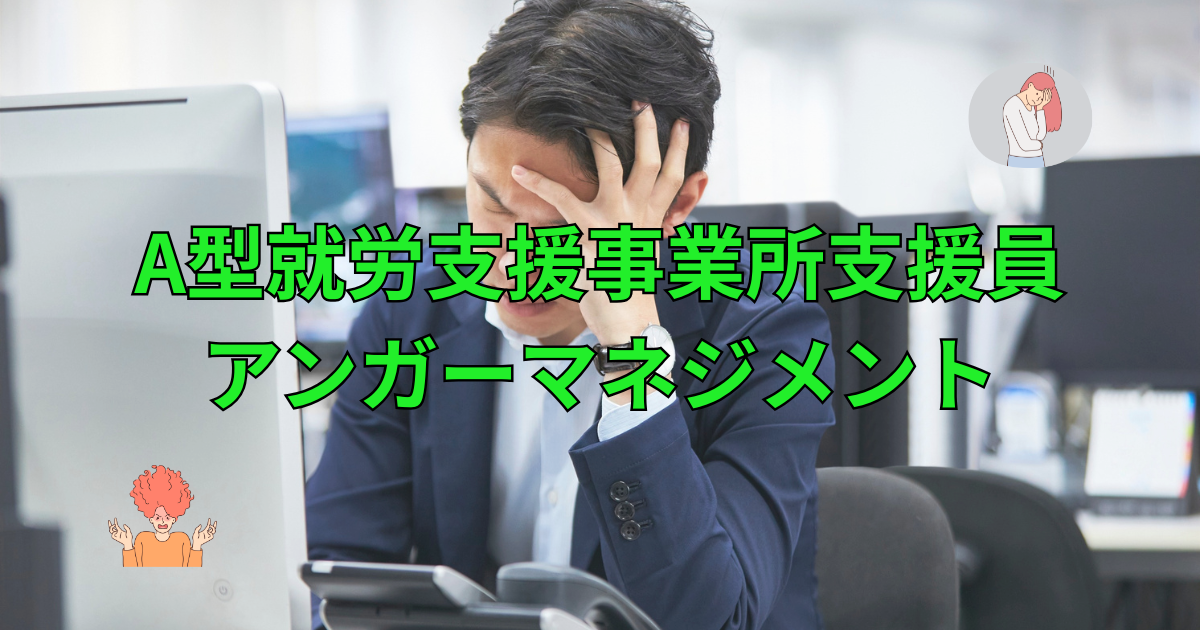

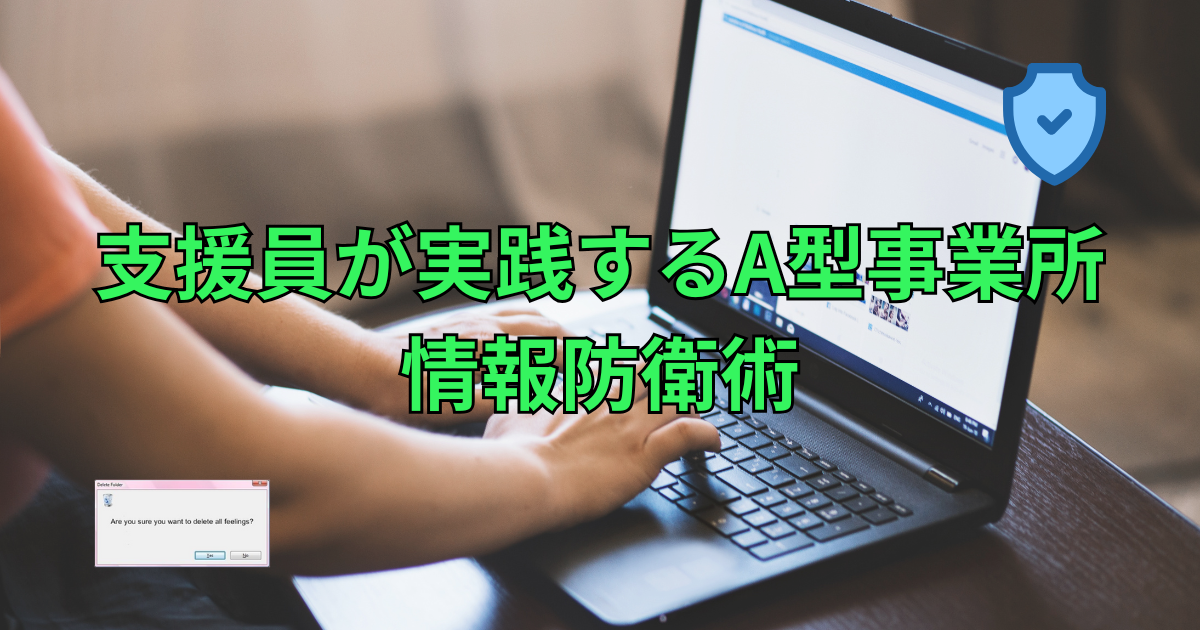
コメント