A型就労継続支援事業所は、利用者さんの個人情報や病歴など、最もデリケートな情報を日常的に扱っています。私たち支援員が情報の管理を間違えると、情報漏洩という重大な事態を招き、事業所の信頼だけでなく、利用者さんの社会生活にまで深刻な影響を及ぼしかねません。情報漏洩は未然に防ぐことが何よりも大切です。本記事ではA型事業所の支援員さんが情報漏洩から会社と利用者さんを守るために実践すべき予防と対策を分かりやすく解説します。
会社を守る情報セキュリティ支援員の義務とは
A型就労継続支援事業所の支援員として、私たちの使命は利用者さんの就労と社会参加をサポートすることです。しかし、この支援業務は情報セキュリティと表裏一体であるという高い意識が欠かせません。
A型事業所は、一般企業よりも機密性が非常に高いデリケートな情報、特に要配慮個人情報を多く扱っています。
情報漏洩と聞くと、外部からの悪質な攻撃のことと認識しがちです。しかし、約6割は私たち自身の不注意やうっかりミスから発生しているというデータがあります(※総務省や独立行政法人情報処理推進機構(IPA)などの公的機関が注意喚起しています)。
A型事業所が扱う特に守るべきデリケートな情報
- 利用者の氏名・住所・連絡先など基本的な個人情報
- 障害の種類や程度、病歴といった要配慮個人情報
- 通所や支援の記録、支援計画などの重要な業務情報
- 家族構成や生活状況などプライバシーに関わる情報
- 取引先や業務委託に関する機密情報
情報漏洩が起きてしまうと、事業所の社会的信頼は瞬時に失われ、利用者さんのプライバシー侵害や差別につながり、人権問題に発展しかねません。
個人情報保護法や障害者総合支援法といった法令遵守の観点からも、厳格な情報管理は支援員に課せられた義務です。情報が漏れることによる損害賠償や行政指導のリスクは、事業所経営に深刻な影響を及ぼしてしまいます。
支援員は、自分が取り扱う全ての情報が会社と利用者さんを守るための大切な資産であることを理解し、情報管理のゲートキーパーとして高い防御意識を持つ必要があります。
日常業務に潜む情報漏洩のヒューマンエラー対策

情報漏洩は悪意のある攻撃ではなく、うっかりや勘違いといったヒューマンエラーによって起こるケースが多く見られます。A型事業所の支援員という業務には、利用者さんのサポートに集中するあまり、情報管理がおろそかになってしまう瞬間があるかもしれません。
しかし、その一瞬の気の緩みが全体を危機に晒します。特に、メールや書類の取り扱いには細心の注意が必要です。
支援員が注意すべき具体的なリスクと予防の基本
- メール誤送信: 宛先や添付ファイルを送信前に必ずトリプルチェックする
- 書類の置き忘れ: 利用者記録などの重要書類は席を離れる際必ずしまう、社外に持ち出さない
- USBの紛失: 外部記憶媒体は使用を原則禁止とし、やむを得ない場合は暗号化を徹底する
- パスワードの推測: 誕生日や簡単な単語を避け複雑な組み合わせにする
- 私物PCの利用: 業務用の情報は私物のパソコンやスマートフォンでは扱わない
情報漏洩の約6割が内部からのミスによるという事実は、私たち自身が最大の弱点になり得ることを示しています。支援員一人ひとりが業務手順をマニュアルで確認し、ダブルチェックを徹底することが重要です。
例えば、メールを送る前に宛先と添付ファイルを別の支援員に確認してもらう、といった仕組みを導入するだけでもリスクは大幅に減らせます。
「ちょっとくらいなら」という安易な考えを捨て、業務の中で情報を扱う全ての瞬間に高い意識を持つことが、会社を守るための予防の鉄則です。
デジタル情報と物理情報を守る超基本ルール
A型事業所で扱う大切な情報には、パソコンの中のデータ(デジタル情報)と、書類やファイル(物理情報)の二種類があります。
情報漏洩を防ぐには、この両方をガードする超基本ルールを徹底しなければなりません。特にデジタルの世界では、パスワードが情報を守るための最初の鍵となります。
パソコンや書類の安全な管理方法
- PCの離席時ロック: 席を離れる際は数秒でも必ず画面をロックし、他者に見られないようにする
- 強固なパスワード: 複雑なパスワードを設定し使い回しをしない
- アクセス権限の制限: 業務で必要な支援員だけが情報を見られるようにアクセス権を細かく設定する
- 重要書類の施錠保管: 利用者記録などのデリケートな書類は鍵のかかるキャビネットに必ずしまう
- 情報の確実な廃棄: 不要になった機密書類は細かく裁断できるシュレッダーで処理する
デジタル情報においては、ウイルス対策ソフトを最新の状態に保つことも重要です。OSやソフトのアップデートを怠らないこともセキュリティを保つための基本中の基本です。
物理情報については、書類の持ち運びを極力避けること、会議室や休憩室など第三者が立ち入る可能性のある場所には情報を放置しないことが大切です。
支援員一人ひとりが情報を資産として大切に扱い、日々の管理を徹底することが、会社の情報を守るための堅実な土台となります。
利用者さんとの情報共有で守るべきライン

A型事業所における情報セキュリティは、支援員だけでなく、業務に携わる利用者さん全員が意識して取り組む必要があります。
利用者さんも業務の一環として顧客や製品に関する情報を取り扱うことがあるため、情報の重要性と守り方を理解してもらうことが不可欠です。
利用者さんの特性を考慮し、一方的な指導ではなく分かりやすい工夫で教育を進めることが成功の鍵です。
利用者さんへの分かりやすい教育とルールの統一
- 平易な言葉で伝える: 専門用語を使わず簡単な言葉で情報管理の重要性を繰り返し伝える
- 具体的な作業ルール: 情報の取り扱い手順を絵や図を多用した分かりやすいマニュアルにまとめる
- アクセス権限の最小化: 利用者さんがアクセスできる情報を業務に必要最小限にとどめる
- SNS等への注意喚起: 業務で知った情報をSNSや家族に話さないよう定期的に確認する
- 支援員の監督徹底: 情報を取り扱う業務は支援員が常時、見守る体制を確立する
利用者さんには、情報漏洩が自分自身や他の利用者さんの生活に悪い影響を与えることを具体例を挙げて説明することが効果的です。「うっかり話してしまうこと」も漏洩になるということを理解してもらいましょう。
また、情報の取り扱いルールは事業所全体で一つに統一し、全ての支援員が同じ基準で利用者さんを指導することが重要です。支援員は利用者さんの理解度に合わせて根気強く指導し、安全な作業環境を提供する責任があります。
情報セキュリティ体制を強化するチェックポイント
情報漏洩の予防対策は一度やったら終わりではありません。時間の経過と共にリスクは変化し、新しい脅威も生まれます。
だからこそ、A型事業所全体で定期的にチェックを行い、予防策を継続的に改善していく仕組みが欠かせません。この継続的な取り組みこそが、会社を長期にわたって守るための最大の鉄則です。
予防を継続するための組織的な取り組み
- 定期的な研修の実施: 全職員と利用者さんを対象に最低でも年一回は情報セキュリティ研修を行う
- マニュアルの定期見直し:マニュアルを毎年または半年に一度見直し更新する
- リスク評価の実施: 情報漏洩の可能性がある場所やプロセスを定期的に洗い出し、対策の優先順位を決める
- セキュリティ機器の導入: ファイアウォールやウイルス対策ソフトを最新のものに更新する
- 報告体制の確認: 「おかしいな」と思ったときにすぐに相談・報告できる風通しの良い組織を作る
特に重要なのは、ルールの見直しです。利用者さんの作業内容が変わったり、新しい情報機器を導入したりした際は、必ずその情報の取り扱いについて安全か確認し、マニュアルを改訂しなければなりません。
情報セキュリティは特別な誰かの仕事ではなく、事業所に関わる全ての人が主体性を持って取り組むべきテーマです。
支援員がリーダーシップを取り、これらのチェックポイントを定期的に実施することで、情報漏洩のリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
まとめ

今回の記事では、A型事業所の支援員として情報漏洩を防ぐための鉄則を解説しました。情報漏洩の約6割はヒューマンエラーが原因であり、利用者さんのデリケートな情報を守るためには、日々の業務での意識と行動が不可欠です。
デジタルと物理的な情報管理の基本を徹底し、利用者さんへの分かりやすい教育を行い、組織全体で継続的に予防体制を強化していくことが、会社と利用者さんを守る最善の防衛術となります。
あとがき
私自身、支援の現場を経験していた頃、紙の記録の置き場所にドキッとさせられたり、パスワード管理の難しさを痛感したりしたことが何度もあります。利用者さんの情報を守るという重圧は、支援員にとって常に付きまとう課題です。
本記事で解説した防衛術は、特別な技術ではなく、日々の意識と確実な行動の積み重ねです。利用者さんの安心と信頼を守るため、そして事業所の安定した運営のために、この記事が現場の支援員の方々の一助となれば幸いです。
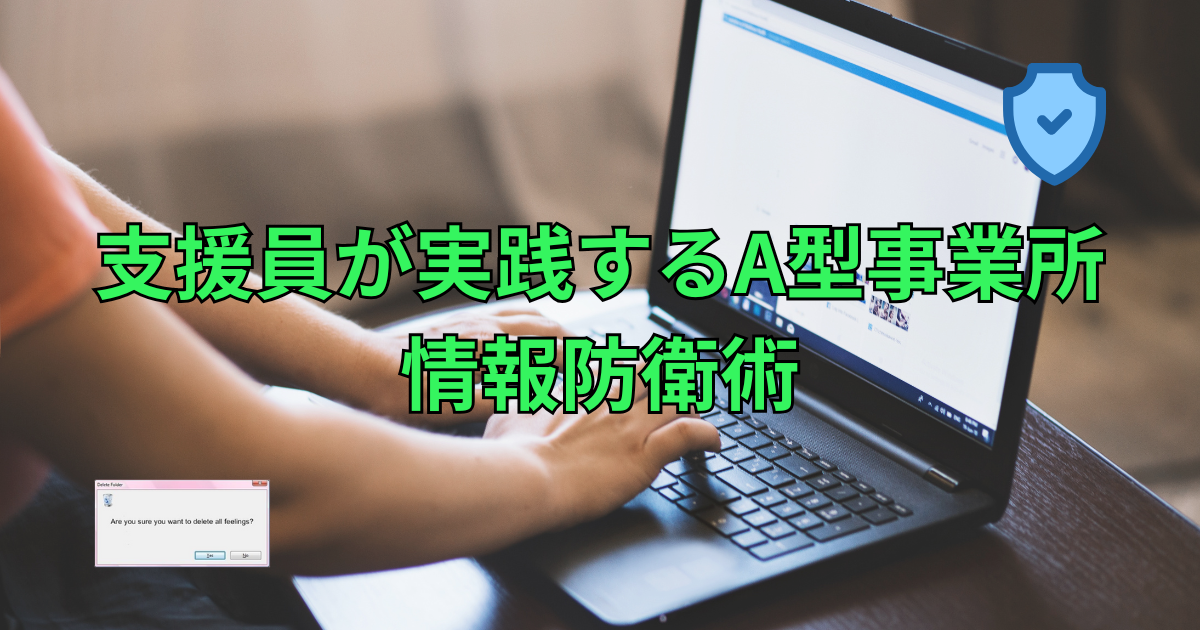
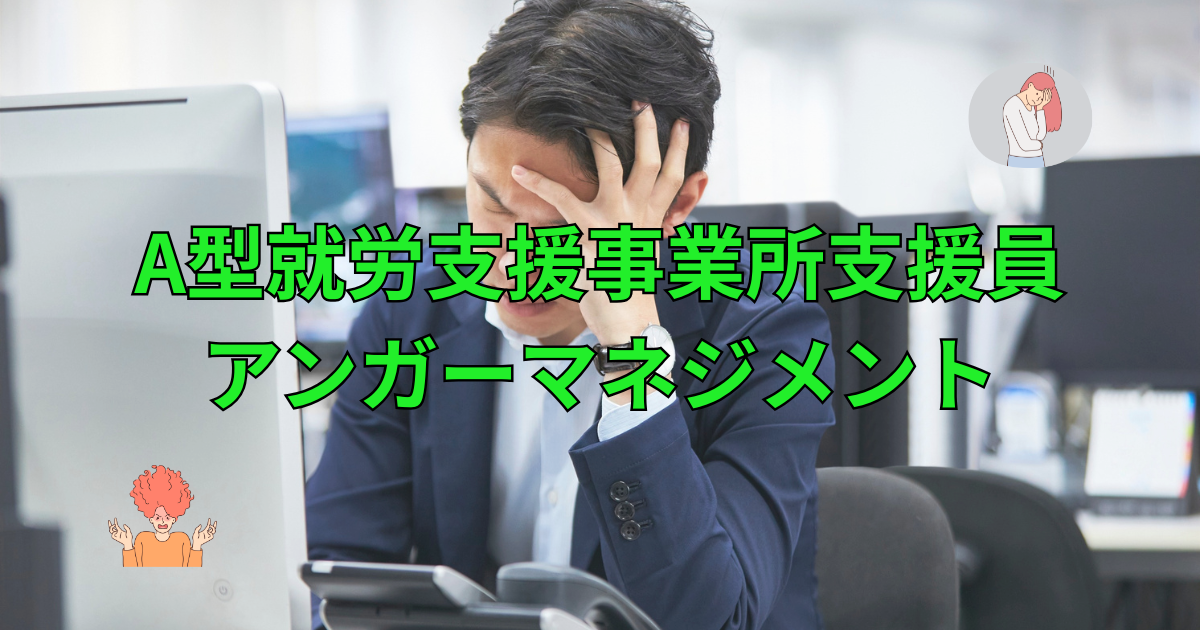

コメント