近年、サイバー攻撃は巧妙化し、福祉事業所も例外なくその脅威に晒されています。個人情報の流出やシステムの停止は、利用者の安全と事業所の信頼を大きく損ないかねません。この記事では、従来のセキュリティ対策の限界を克服する「ゼロトラスト」という新しい考え方を紹介します。ゼロトラストは、ネットワークの内部と外部を区別せず、すべてのアクセスを疑うことを前提とするセキュリティモデルです。
ゼロトラストとは?従来のセキュリティとの違い
ゼロトラストとは、「何も信頼しない」という原則に基づいたセキュリティモデルです。従来のセキュリティは、「社内ネットワークは安全」という前提に立ち、外部からの攻撃を防ぐことに注力していました。
しかし、この方法では内部ネットワークに侵入を許した場合、自由にアクセスされてしまうリスクがありました。その欠点をカバーする形でゼロトラストでは、ユーザーやデバイスがネットワークのどこにいるかに関わらず、すべてのアクセス要求を検証します。
これにより、たとえ内部ネットワークからのアクセスであっても、不正な行動を早期に検知し、被害を最小限に抑えることができます。
具体的には、ネットワークへの接続を試みるすべてのユーザーやデバイスについて、毎回厳格な本人確認を行います。例えば、多要素認証(MFA)を必須とすることで、パスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐことができます。
また、デバイスが最新のセキュリティパッチを適用しているか、不審なソフトウェアがインストールされていないかなど、セキュリティの状態も常にチェックされます。
この継続的な検証プロセスが、ゼロトラストの安全性の中核をなしています。従来の「一度入れば安全」という考え方を捨て去り、「常に疑う」ことで、より強固なセキュリティ体制を築いているというわけです。
なぜ福祉事業所にゼロトラストが必要なのか?

福祉事業所では、利用者の氏名、住所、病歴、障がいの状況など、機密性の高い個人情報が大量に扱われています。これらの情報は、一度流出してしまうと、利用者のプライバシーだけでなく、その後の生活にも深刻な影響を及ぼしかねません。
また、事業所の運営システムがサイバー攻撃によって停止した場合、サービスの提供が滞るリスクも生じてしまいます。そのような事態を回避すべく、高レベルのセキュリティ対策が必要とされるのです。
ゼロトラストは、このような福祉事業所の特殊な状況にこそ適しています。職員が在宅勤務や外出先でタブレット端末を使って業務を行う機会が増えており、事業所のネットワーク境界はもはや明確ではありません。
ゼロトラストを導入することで、どこからでも安全にデータにアクセスできる環境を構築できます。これにより、働き方の多様化に対応しつつ、情報漏洩のリスクを低減できます。
さらに、利用者の個人情報へのアクセスを厳格に管理し、不正なアクセス試行をリアルタイムで検知することで、万が一の事態に備えることができます。
ゼロトラストを実現する3つの基本原則
ゼロトラストモデルは、以下の3つの基本原則に基づいて構成されています。これらの原則を理解することが、適切なセキュリティ戦略を立てる上で非常に重要です。
一つ目は「すべてのアクセスを検証する」という原則です。これは、ユーザーやデバイスがどこからアクセスしているかに関わらず、常に本人確認やセキュリティ状態のチェックを行うことを意味します。
二つ目は「最小権限の原則」です。ユーザーには、業務遂行に必要最低限の権限のみを与え、過剰なアクセス権限を付与しないことで、不正アクセスによる被害範囲を限定します。
三つ目は「常に監視し、対策する」という原則です。ネットワーク上のすべての通信やアクティビティを継続的に監視し、不審な兆候を早期に発見・対処します。
この3つの原則が、ゼロトラストの堅牢なセキュリティ体制を支える柱となっています。
すべてのアクセスを検証する
この原則はゼロトラストの根幹をなすものです。従来のセキュリティモデルでは、一度認証を通過すれば、内部ネットワーク内での自由な活動が許されていました。しかし、ゼロトラストでは一度の認証だけでは不十分だと考えます。
アクセスするたびに、多要素認証(MFA)を要求したり、デバイスの状態をチェックしたりすることで、正当なアクセスであることを継続的に確認します。
例えば職員が利用者の情報を閲覧する際、毎回パスワードと生体認証を組み合わせた認証を求める、といった仕組みです。これにより万が一、職員のIDやパスワードが盗まれても、不正アクセスを防ぐことができます。
この徹底した検証プロセスは、情報漏洩のリスクを大幅に低減します。
ゼロトラスト導入に向けた具体的なステップ

ゼロトラストの導入は、一度にすべてを完璧に行う必要はありません。現状のセキュリティ対策を評価し、段階的に移行していくことが現実的です。
まずは、現状のネットワーク環境や情報資産を把握し、どのような情報がどこに保存されているのかを可視化することから始めます。次に、アクセス権限の見直しを行います。
誰がどの情報に、どのような権限でアクセスしているのかを明確にし、必要最小限の権限に絞り込みます。そして、多要素認証(MFA)の導入はゼロトラスト移行における最初の重要なステップです。
これにより、パスワード漏洩によるリスクを大幅に軽減できます。さらに、セキュリティログの監視体制を強化し、不審な挙動がないかを常にチェックする仕組みを構築します。
これらのステップを一つずつ着実に実行していくことが、ゼロトラストモデルへのスムーズな移行に繋がります。
ゼロトラスト導入で事業所に起こる変化
ゼロトラストを導入することで、福祉事業所のセキュリティは大きく向上します。これにより、利用者やその家族は、個人情報が厳重に管理されているという安心感を得ることができるでしょう。
また、職員は場所を選ばずに安全に業務を行えるようになるため、業務効率も向上します。
- テレワークの導入がスムーズになり、多様な働き方が可能になる。
- 外部委託先との情報共有も、厳格なアクセス制御の下で安全に行えるようになる。
さらにサイバー攻撃のリスクを低減することで、システム障害によるサービス停止を防ぎ、安定した事業運営に繋がります。これらの変化は、事業所の信頼性を高め、持続可能な運営を可能にするでしょう。
ゼロトラスト導入の課題と解決策
ゼロトラスト導入にはいくつかの課題があります。まず、初期の導入コストや、システムの運用・管理に必要な専門知識が障壁となる場合があります。
また、厳格な認証プロセスが職員の利便性を損ない、業務効率を低下させる可能性も指摘されています。しかし、これらの課題には解決策があります。
- 導入コストについては、クラウドベースのセキュリティサービスを活用することで、初期投資を抑え、運用負担を軽減できる。
- 利便性の低下に関しては、シングルサインオン(SSO)や生体認証を組み合わせることで、セキュリティと利便性を両立できる。
さらに、専門知識の不足を補うために、外部のセキュリティベンダーと連携し、運用・管理をアウトソースすることも有効な選択肢です。これらの解決策を適切に活用することで、ゼロトラスト導入のハードルを下げることができます。
デジタルデバイドを解消するゼロトラスト
福祉事業所では、職員のITリテラシーにばらつきがあることがあります。ゼロトラストは、このデジタルデバイドを解消する一助となります。
- 多要素認証の導入は、スマートフォンでの操作が必要になる場合があるが、職員研修を通じて習得可能。
- シンプルで使いやすい認証システムを選定することで、ITに不慣れな職員でもスムーズに利用できる。
ゼロトラストは、単なるセキュリティ技術ではなく、組織全体の意識改革を促すものです。すべての職員がセキュリティの重要性を理解し、主体的に取り組む文化を醸成することが、ゼロトラストを成功させる鍵となります。
こういった取り組みにより、職員一人ひとりのITリテラシー向上にも繋げられます。結果として事業所全体のデジタル化を推進する力となるでしょう。
まとめ

ゼロトラストは「何も信頼しない」を原則とし、社内外を問わず全てのアクセスを都度検証することで、不正侵入や情報漏洩を防ぐセキュリティモデルです。
福祉事業所は機密性の高い個人情報を扱うため特に有効で、在宅勤務や外出先からの業務にも安全に対応できます。
導入は段階的に進め、最小権限設定や多要素認証、監視体制強化を行うことで安全性と業務効率を両立し、組織全体の意識改革とITリテラシー向上にもつながります。
あとがき
この記事を書きながら、改めて福祉事業所におけるセキュリティの重要性を強く感じました。特にゼロトラストの考え方は、単なる技術導入にとどまらず、職員一人ひとりの意識や業務の在り方まで変える力があると実感しました。
福祉の現場は利用者の安心と信頼が基盤であり、そのためには情報を守る仕組みと文化が不可欠です。ゼロトラストはその両方を支える有効な手段だと確信しました。導入のハードルはあっても、小さな一歩から始める価値が十分にあると感じました。
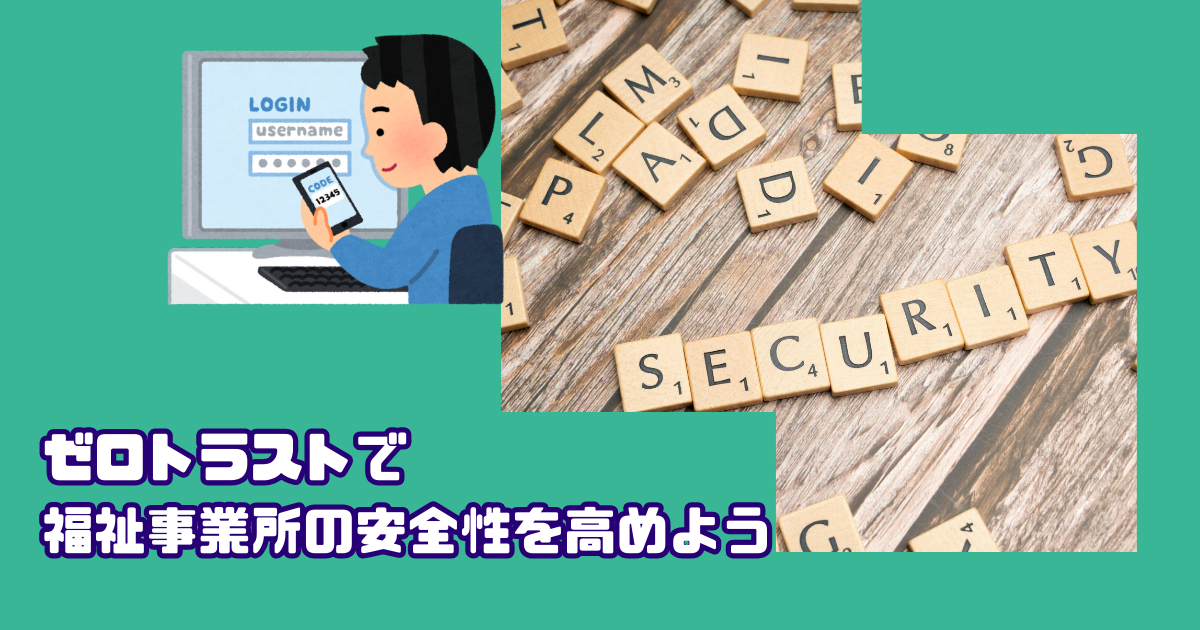

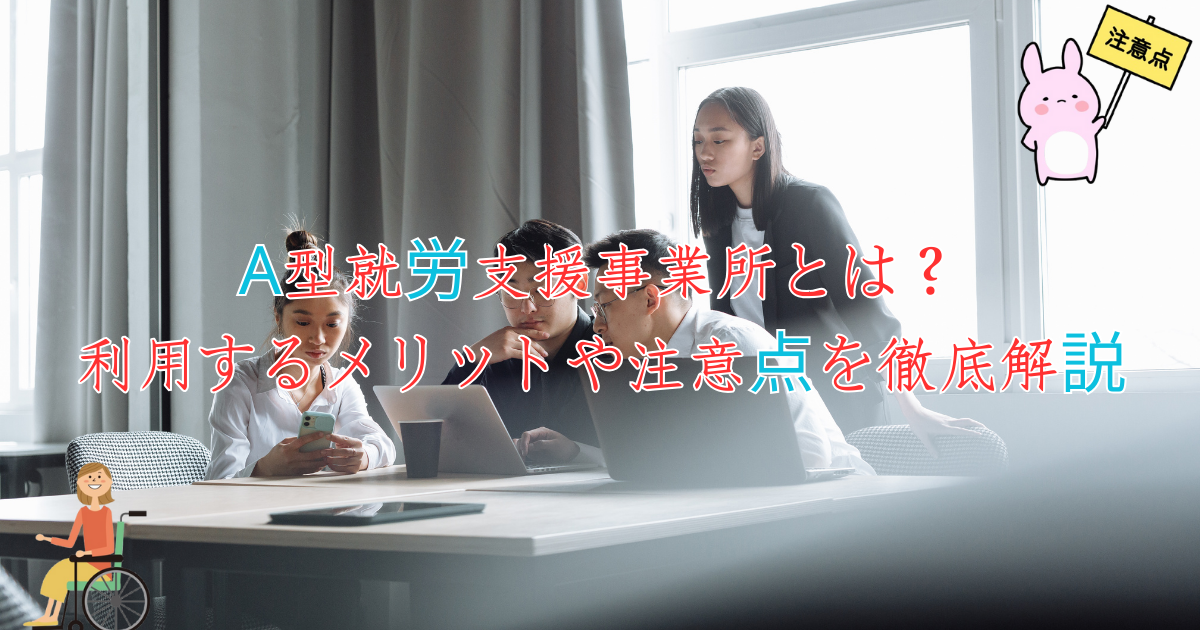
コメント