福祉や障がいに関わる事業所にとって、セキュリティ対策は今や避けて通れない重要な経営課題です。事業所のデータを人質にとる攻撃や、偽の警告画面で利用者を騙す手口、さらには信頼している取引先を経由した攻撃など、その方法は日々多様化、巧妙化しています。この記事では、福祉・障がい分野で働く皆様が知っておくべき、セキュリティの脅威と、その対策について解説します。
メールだけじゃない!多様化するセキュリティの脅威
福祉や障がい分野の現場では、さまざまなサイバー攻撃の脅威が日々高まっています。従来のフィッシング詐欺や標的型攻撃メールなどはもちろん、それ以外の攻撃への対策も欠かせません。
該当する攻撃の例としては、パソコンやサーバー内の大切なデータが突然暗号化され、元に戻す代わりに金銭を要求される「ランサムウェア」や、偽の警告画面を使い不安を煽ってお金を騙し取る「サポート詐欺」などがあります。
近年は、信頼している取引先を経由してウイルスや不正アクセスを仕掛ける手法も増加しており、外部だけでなく内部からの情報漏洩にも注意が必要です。
こうした脅威はもはや他人事ではありません。現場全体で幅広い視点のセキュリティ対策が求められています。
【データを人質に】事業継続を脅かすランサムウェア攻撃

ランサムウェアとは、パソコン内のデータを勝手に暗号化し、元に戻す条件として身代金の支払いを求める悪質なマルウェアのことです。そのネーミングは「Ransom(身代金)」と「Software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語となっています。
福祉事業所で被害に遭えば、利用者情報や支援記録、請求データなどすべての重要情報にアクセスできなくなり、日常業務が完全に止まってしまう危険性があります。事業継続に大きな影響を及ぼすため、日頃からの備えが欠かせません。
バックアップの重要性
最も有効な対策は、データのバックアップをこまめに実施することです。たとえ攻撃を受けても、バックアップがあればシステムを初期化して復旧できます。
ただし、バックアップの方法にも工夫が必要です。ネットワークに接続したままの外付けHDDやNASだけに頼ると、バックアップごと暗号化される恐れがあります。
- 「3-2-1ルール」の実践
データの原本と2つのコピー、計3つを2種類の異なる媒体に保存し、1つはネットワークから切り離した場所や遠隔地に保管する方法が推奨されます。 - 定期的な復元テスト
バックアップは取得するだけでなく、実際に復元できるかどうかを定期的にテストすることが重要です。緊急時に復元できなければ意味がありません。 - バックアップデータの保護
バックアップ用媒体やサーバーにもセキュリティ対策を施し、ウイルス感染や不正アクセスから守ることを忘れずに行いましょう。
侵入経路を塞ぐ対策
ランサムウェアの感染経路は多岐にわたります。主体的に狙われるのは、メールの添付ファイルだけでなく、VPN機器やリモートデスクトッププロトコル(RDP)までも含まれます。そのため日頃からの基本的な対策が重要です。
- ソフトウェアのアップデート
パソコンやサーバーのOS、アプリケーション、VPN機器などは常に最新の状態に保ち、脆弱性を悪用されないようにします。 - パスワードの強化と認証
安易なパスワードを避け、長く複雑なものに設定し、できれば多要素認証も導入して不正ログインを防ぎます。 - セキュリティソフトの導入
ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを常に最新に保つことで、既知のランサムウェアの侵入を防げます。
【偽の警告に注意】突然画面に現れるサポート詐欺

サポート詐欺は、インターネット閲覧中に突然「ウイルスに感染しました」などの偽の警告画面を表示し、利用者の不安を煽って金銭を騙し取る手口です。多くはマイクロソフトなどの大手企業を名乗り、問題解決のために表示された電話番号への連絡を促します。
電話をかけてしまうと、片言のオペレーターが遠隔操作ソフトのインストールや費用の支払いを要求してくることがあります。
偽の警告画面の特徴
サポート詐欺の警告画面には、以下のような共通点があります。職員が業務中に遭遇する場合もあるため、特徴を知って冷静に対処できるようにしましょう。
- けたたましい警告音が鳴る
受信者を驚かせ、正常な判断を奪うために、ビープ音や警告メッセージの音声が大音量で流れ続ける場合があります。 - ポップアップが消せない
「閉じる」ボタンを押しても消えず、まるでパソコンが乗っ取られたかのような印象を与えます。 - 偽の電話番号が表示される
マイクロソフト認定サポートなどを装い、電話をかけるよう促すIP電話番号(多くは050から始まる)が大きく表示されます。
正しい対処法
サポート詐欺の画面が表示されても、指示に従わず、電話やインストール、金銭の支払いは絶対にしてはいけません。
まずはブラウザを終了し、それができなければ「Ctrl」+「Alt」+「Delete」でタスクマネージャーを起動し、ブラウザのプロセスを終了させます。最終手段としてパソコンの電源を長押しして強制終了し、再起動してください。
【取引先も標的に】見えにくい脅威、サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、狙った企業へ直接攻撃するのではなく、関連会社や取引先などのセキュリティが比較的弱い組織を踏み台にして内部ネットワークへ侵入する巧妙な手法です。
福祉事業所も、給食業者やシステム開発会社、清掃業者など多くの外部委託先と関わりがあります。自社の対策だけでは防ぎきれないリスクがあるため、サプライチェーン全体での意識と対策が必要です。
取引先選定時のセキュリティチェック
新しい業者やSaaSを導入する際は、委託先のセキュリティ対策が十分かを確認することが重要です。プライバシーマーク(Pマーク)やISMSの取得有無、個人情報管理体制などを必ず確認し、契約書にもセキュリティやインシデント対応の条項を盛り込みましょう。
委託先管理の重要性
契約後も、委託先への定期的な管理や教育、連携体制の整備が不可欠です。特に個人情報へのアクセス権限は最小限にし、万が一のインシデント時には速やかに報告・対応できる仕組みが必要です。
- 契約内容の見直し
定期的に契約書の内容を見直し、情報セキュリティ条項や監査受け入れなどを明記しておきましょう。 - 委託先の教育・啓発
自事業所のセキュリティポリシーを委託先とも共有し、理解を求めることが理想です。 - インシデント発生時の連携
インシデント発生時に即時報告・連絡できる体制を契約時に定めておきます。
外部だけではない「内部不正」というリスクへの備え
情報セキュリティ上のリスクは、外部からの攻撃だけでなく、内部職員や退職者などによる情報漏洩・改ざんといった「内部不正」にもあります。内部の人間は正規権限でシステムや情報にアクセスできるため、外部攻撃よりも発見が難しい場合があります。
利用者の個人情報流出は、組織の信頼失墜に直結します。信頼を前提としつつも、抑止力と仕組み作りが不可欠です。
技術的な対策
「不正ができない、しにくい」環境を技術的に整備することが有効です。アクセスログの取得・監視や、USBメモリ・外部デバイスの利用制限などが抑止力となります。
- アクセス権限の最小化
職員ごとに業務に必要な範囲でのみ情報にアクセスできるよう、権限を厳格に設定します。 - 操作ログの監視
データ印刷や外部メディアへのコピーなどの操作ログを取得し、不審な行動がないかを監視します。 - 外部デバイスの利用制限
許可していないUSBメモリやスマートフォンの接続を業務用パソコンで制限します。
組織的な対策と退職者管理
全職員との秘密保持契約や定期的なセキュリティ研修の実施、内部不正のリスクと結果の周知が大切です。退職者のアカウントは速やかに削除・無効化し、退職後の不正アクセスも防ぎましょう。
組織的・技術的な両面から内部不正対策を徹底することが、利用者や事業所を守るために重要です。
まとめ

福祉・障がい者事業所におけるセキュリティ対策は、ランサムウェアやサポート詐欺、サプライチェーン攻撃、内部不正など多様化・巧妙化しています。日頃からのバックアップや認証強化、委託先の管理、職員教育の徹底が重要です。
技術的対策と組織的対策を両立し、幅広いリスクに備えることで、利用者の情報と事業所の信頼を守り、安心して活動できる環境を築くことが求められます。
あとがき
この記事を書きながら、福祉や障がい者に関わる事業所にとって、セキュリティ対策がどれほど重要かを改めて実感しました。デジタル化が進む一方で、脅威は日々巧妙化し、現場の負担も大きくなっています。
特に、利用者情報を守るためには、日常的なバックアップや認証強化、委託先管理など、地道な対策の積み重ねが不可欠です。
安心して支援に集中できる環境づくりのために、今後も現場で活かせる情報を発信していきたいと感じました。
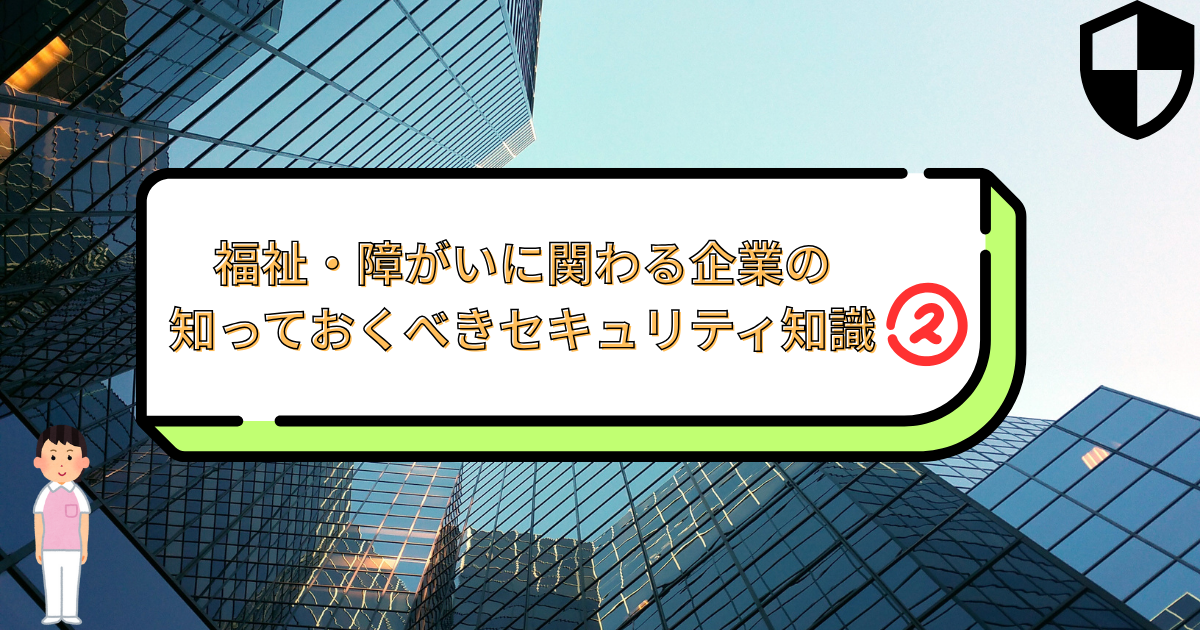

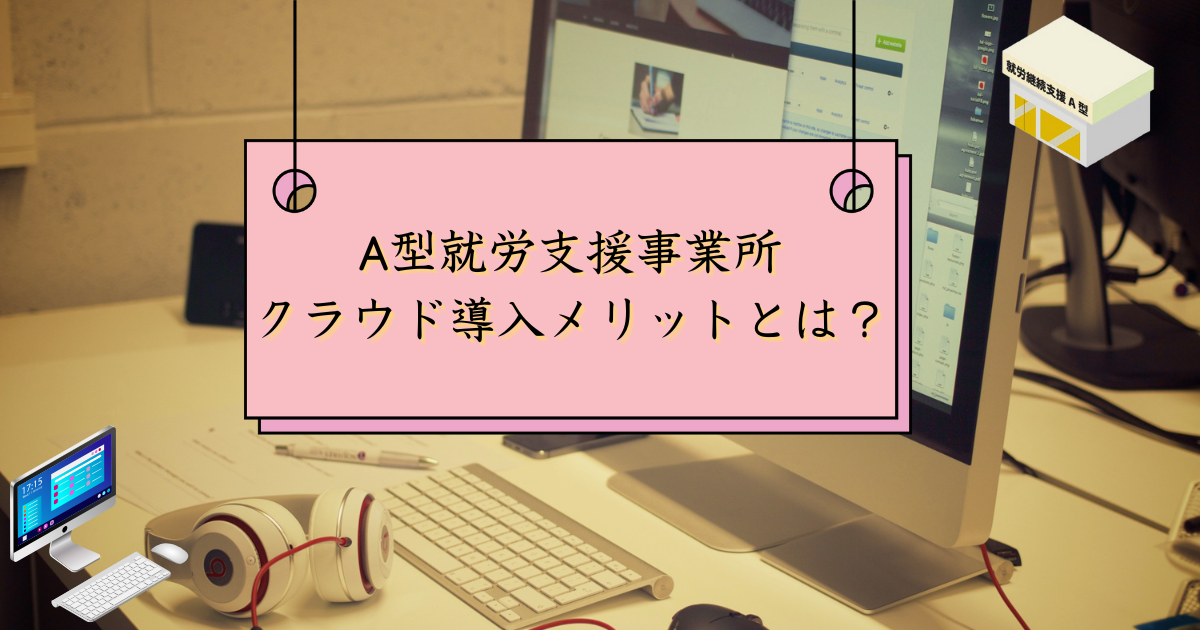
コメント