私はA型事業所に利用者として勤めながら、日々の子育てもしているワーママです。最初は仕事と家庭の両立に悩むことも多くありましたが、少しずつコツをつかみ、今では自分なりのペースで無理なく続けられるようになりました。この記事では、私が実践している工夫や時間の使い方、心の持ち方など、リアルな体験をもとにした両立の秘訣をご紹介します。
1. 完全在宅リモートワークを選択する
子供がまだ小さいうちは沖縄の宮古島に住んでいた事もあり、初めから完全在宅を考えていました。現在は、ご縁があって今のA型事業所で完全在宅で働いています。
在宅のメリットは通勤がないことです。子育て中で体力がない私にとって、この通勤ゼロは本当に助かります。朝の準備や移動に追われず、その分を子どもの支度や自分の心の余裕に回せるのが大きな利点です。
また、自宅という安心できる環境で作業ができるため、周囲の目を気にせず、自分のペースで集中しつつリラックスして仕事ができます。
私の場合「今日は少し体が重いな」と思う日でも、無理せず自宅でできる業務なら継続可能なので、体調管理との両立がしやすくなります。
2. 朝の換気と掃除

部屋の汚れは心の乱れという言葉の通り、部屋の状態が心の状態に影響しているのは、とても実感しています。
部屋が散らかっていると、なんだか気持ちまでソワソワして落ち着かなくなるんです。ストレスや不安を感じやすくなることも。反対に部屋をスッキリ整えると、不思議と心もスーッと落ち着いて、気分が前向きになるのでお勧めです。
私は、いつも出勤前に5分ほど仕事部屋に掃除機をかけています。子育て中だと、朝から体力が無い日も多いですが、そんな時は窓をあけて換気するだけでも気分をリフレッシュできるので、やってみて欲しいです。
3. 音楽を小さく流す
最近取り入れているのが、音楽を小さめの音で流しながら仕事をすることです。以前は静かな方が集中できると思い込んでいたのですが、ある日ふと気分転換に音楽を流してみたら、意外にも作業がスムーズに進みました。
それ以来、集中したいときは静かなBGMを流すのが習慣になりました。音量はあくまで小さめに、邪魔にならない程度がポイントです。
4. こまめに報連相(週一面談・月一面談)
子育てと仕事を両立していると、どうしても突発的な予定変更がつきものです。子どもの急な発熱や幼稚園からの呼び出しなど、計画通りにいかないこともしばしばあります。
そんな中でも私が安心して働き続けられているのは、A型事業所でのこまめな報連相の仕組みがあるからです。私の事業所では、週に一度の面談や月に一度の振り返り面談があり、日々の悩みや不安をこまめに相談できます。
さらに、いつでも話を聞いてくれる職員さんが常にいるので、仕事のことはもちろん、家庭の状況も含めて柔軟に対応してもらえるのが本当にありがたいです。
こまめなコミュニケーションを通じて、一人で抱え込まなくていいという安心感が生まれ、結果的に心にも余裕が持てるようになりました。仕事と子育て、どちらも大切にしたい私にとって、この環境は本当に心強い存在です。
5. どうしても寝不足の時の必殺技
子育て中は、夜中に何度も起きたり、朝早くから子どもの世話があったりして、どうしても寝不足になる日があります。
そんなときは、まずコーヒーで頭をスッキリさせたり、軽くストレッチをして体を目覚めさせたりするのが私の定番です。
でも、それでも眠気が取れない極限の眠さの日は、奥の手を使います。それが立ち作業です。昇降デスクの高さを上げて、立ったまま作業すると不思議と頭がシャキッとします。
姿勢もリセットされて、集中力も持ち直せるので、どうしても眠いときの必殺技として重宝できるので是非試してみてくださいね。
6. 片耳イヤフォンで家事&育児
子どもは本当に可愛い存在ですが、0歳〜3歳頃までは目が離せず、四六時中気を張っているので、心も体もクタクタになっていました。
少しずつ自立してくる4歳以降も油断はできず、現在5歳のわんぱく息子は「ママー!ママー!」と一日中呼び続けてくれるので、休まる時間がなかなかありません。
そんな日々の中で私が取り入れているのが、片耳イヤフォンの活用です。子どもの声や気配に気を配りつつ、自分の世界も大事にできるこの方法は本当におすすめです。
YouTubeや音楽、育児系のラジオなどを聴くことで、家事や育児の合間にも小さな楽しみや癒しが生まれます。
また、家事のやる気が出ないときは、片耳で掃除や断捨離系の動画を流すと、自然とちょっとやってみようかなという気持ちになれたりします。自分のペースでながら時間をうまく使うことで、気持ちに余裕が持てるようになりました。
7. 日記でアウトプット!どんな感情にもOKを出す

子どもを出産してから、私の障害の症状は一時的に不安定になり、日々の生活を回すだけでも精一杯でした。その頃は、ヘルパーさんや訪問看護の力を借りながら、なんとか毎日をこなしていた状態でした。
そんな中、訪問看護師さんに勧められて始めたのが日記を書くという習慣です。当時は赤ちゃん連れで外出もままならず、家にこもりがちで人と話す機会もなく、孤独感が募るばかりでした。
私の中で、日記は誰にも言えない本音や、不安、そして子育ての小さな喜びまでを吐き出す大切な場所になっています。
最初のうちは「ちゃんと書かなきゃ」「前向きなことを書かないと」と自分を縛ってばかりで、素直な感情を書くのが難しかったのですが、A型事業所に通い始めて変化がありました。
職員さんたちが「自分のペースでいいんだよ」と声をかけてくれたり、周りのメンバーさんたちが一生懸命自分と向き合いながら働く姿に勇気をもらったりして、できない自分も弱い自分も、少しずつ受け入れられるようになっていきました。
今では日記に、良いことも悪いこともそのまま書けるようになり、こんな感情があってもいいと自分にOKを出せるようになりました。
心のモヤモヤを紙に書くだけで、ゆっくりと気持ちが軽くなり、生きるのが前より少し楽になった気がします。日記は心のメンテナンスにも、自分を見つめる大切な時間にもなる、そんな習慣になりました。
8. SNSデトックス(デジタルデトックス)
子どもが5歳になり、自分の時間が少しずつ持てるようになってきました。その貴重な隙間時間、つい習慣のようにSNSを見てしまっていた私。
一時的には楽しくても、気づけば時間が過ぎていたり、目や頭がどっと疲れていたり…。そんなときに知ったのがSNSデトックス(デジタルデトックス)という考え方です。
試しに寝る前のスマホ時間をやめてみたら、心が落ち着き、夜もぐっすり眠れるようになりました。また、空いた時間で読書をしたり、自分の趣味に使えたりと、充実感が増していきました。
全部をやめるのは難しくても、少し距離を取るだけで、毎日の心地よさが変わってきます。
9. 30点でも許す。最初から30点を目指す
昔の私は完璧主義で、なんでも100点を目指さなきゃと自分を追い込んでいました。でも、子どもが生まれてからは、思うように家事も進まないし、自分の体調も以前とは違いました。
そのたびにできない自分が許せず、つらい気持ちを抱えていました。そんな中で学んだのが、30点でいいという考え方です。
最初から100点を目指さず、まずは30点取れれば合格をあげます。たとえ今日は掃除ができなくても、食事が手抜きでも、それでもOKとします。
無理せずベビーステップで進めば、いずれゴールに近づける。子育て中で障害と向き合っている今の私には、このゆるめる思考が何よりの支えになっています。時には今日は5点!と笑える余裕も、大切なんだと思います。
10. 「完了をゴールにしない」まず始めたら合格◎
前の章でも、家事との向き合い方について少し触れましたが、もうひとつ私なりの工夫をお伝えします。
仕事に育児に毎日がバタバタ。家事に手が回らず、つい後回しにしてしまうこともありますよね。
私もよく「今日はもう無理…」という日があります。けれど、洗濯や片づけをサボった翌日は、倍以上に家事が膨れ上がり、気持ちがさらに重くなる悪循環に…。
そんな時、私が心がけているのが完了をゴールにしないという考え方です。全部やろうとするとしんどいので、とりあえず取りかかれたらOK!と自分に声をかけます。
不思議と最初の一歩さえ踏み出せれば、自然と体は動くもの。完璧を目指さず、少しでも動けた自分を褒める。それだけで、気持ちもラクになります。
まとめ

記事を読んで頂き、ありがとうございます。障害を抱えながら、仕事と育児の両立は決して簡単ではありませんが、小さな工夫と心の持ち方次第で、毎日はもっと穏やかに、前向きに変えられます。
完璧じゃなくていい、自分らしいペースでOK。この記事が、誰かのちょっとやってみようのきっかけになれたら嬉しいです。
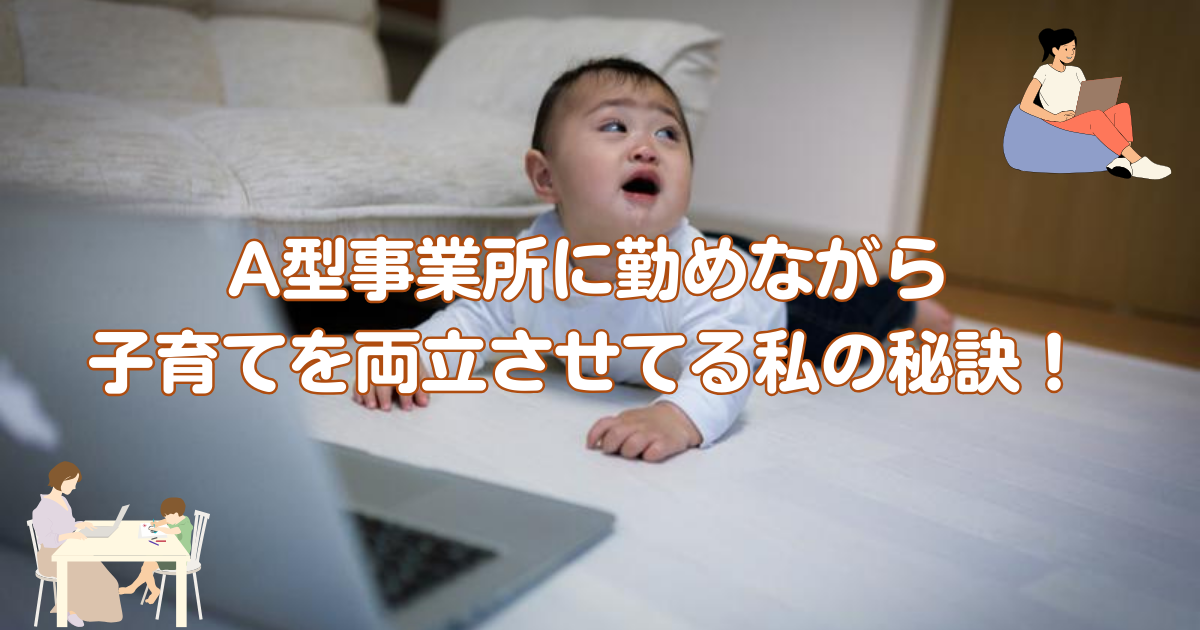


コメント