インターネットを利用していると、私たちの目に見えないところで、大切な情報を盗み取ろうとする様々な脅威が存在します。この記事では、福祉施設や事業所のパソコンを利用する際に特に注意したい、3つの代表的なサイバー攻撃の手口を解説します。キーロガー、ドライブバイダウンロード、そして中間者攻撃。これらの脅威の正体と、自分たちでできる簡単な対策を知ることで、安心してパソコンを使える環境を一緒に作っていきましょう。
あなたのキーボード入力、盗み見られている?「キーロガー」の恐怖
キーロガーとは、パソコンに忍び込み、キーボードで入力した文字情報をすべて記録してしまうスパイのようなプログラムです。これはマルウェア(悪意のあるソフトウェア)の一種で、一度感染してしまうと、非常に厄介な存在となります。
もしキーロガーに感染した場合、あなたが入力したIDやパスワード、ネットショッピングで使ったクレジットカード番号、メールの内容などが筒抜けになります。記録された情報は、攻撃者の元へ自動的に送信され、不正利用されてしまう危険性が高いのです。
このマルウェアの怖いところは、パソコンの動作が少し遅くなる程度で、感染していることに気づきにくい点です。知らないうちに、あなたの個人情報がリアルタイムで盗まれ続けているかもしれません。
不審なメールの添付ファイルを開いたり、怪しいサイトからファイルをダウンロードしたりすることで感染するケースが多く報告されています。
ただサイトを見ただけで感染?「ドライブバイダウンロード」の手口
ドライブバイダウンロードとは、ウェブサイトを閲覧しただけで、利用者が気づかないうちにマルウェアを自動で送り込む攻撃手法です。
普段見ている企業の公式サイトや、有名なニュースサイトが改ざんされ、この攻撃の罠として利用されることもあり、非常に巧妙で悪質です。
この攻撃は、お使いのパソコンのOS(Windowsなど)や、ブラウザ、PDF閲覧ソフトといったソフトウェアの古いバージョンの弱点(脆弱性)を狙ってきます。
利用者が何かをダウンロードしたり、クリックしたりしなくても、サイトを表示した瞬間に感染が始まってしまうのです。
自分は怪しいサイトには行かないから大丈夫、と思っていても、いつものお気に入りのサイトが攻撃者に乗っ取られている可能性もゼロではありません。この脅威から身を守るためには、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことが、何よりも重要な対策となります。
通信が乗っ取られる!「中間者攻撃」とは?
中間者攻撃とは、あなたとウェブサイトとの通信の間に、攻撃者が割り込んで情報を盗聴・改ざんする手口です。
例えるなら、あなたが送った手紙を、配達の途中で誰かがこっそり開封して中身を読み、また封をして相手に届けるようなものです。送った側も受け取った側も、その事実には気づきにくいのです。
特に、カフェや駅などで提供されている暗号化されていない公衆Wi-Fi(フリーWi-Fi)を利用する際は、この攻撃に遭うリスクが高まります。
同じネットワークに接続している攻撃者が、あなたの通信を簡単にのぞき見できてしまうからです。これにより、ログイン情報や個人情報が盗まれる可能性があります。
情報を盗むだけでなく、攻撃者が偽の情報を表示させることも可能です。例えば、ネットバンキングのサイトにアクセスしたつもりが、攻撃者が用意した偽サイトに誘導され、IDやパスワードを騙し取られるといった被害も発生しています。
これらの攻撃を受けるとどうなる?具体的な被害事例
これまで紹介したサイバー攻撃の被害に遭うと、個人だけでなく事業所全体に深刻な影響が及ぶ可能性があります。ここでは、実際に考えられる被害の例を具体的に見ていきましょう。自分には関係ないと思わず、もしもの場合を想像してみてください。
金銭的な被害
最も直接的で分かりやすい被害が、金銭的なものです。攻撃者は盗んだ情報を使い、様々方法でお金を騙し取ろうとします。
- キーロガーで盗まれたIDとパスワードを悪用され、ネットバンキングから勝手にお金が送金されてしまう。
- 中間者攻撃で盗まれたクレジットカード情報を使われ、身に覚えのない高額な請求が届く。
- ドライブバイダウンロードで感染したパソコンが身代金要求型ウイルス(ランサムウェア)に暗号化され、解除のために金銭を要求される。
個人情報の悪用
お金だけでなく、あなたの個人情報そのものが狙われ、悪用されるケースも後を絶ちません。その被害は、精神的にも大きな苦痛を伴います。
- SNSアカウントが乗っ取られ、あなたの名前で不適切な投稿をされたり、友人に詐欺のメッセージが送られたりする。
- 盗まれたメールアドレスやパスワードを元に、他の様々なサービスへの不正ログインを試みられる(パスワードリスト攻撃)。
- パソコン内に保存していた住所録や写真などのプライベートな情報が、インターネット上に流出してしまう。
事業所への被害拡大
福祉施設や事業所においてパソコンが攻撃を受けることは、パソコン1台だけの問題では済みません。被害は事業所全体へと波及する恐れがあります。
- 1台のパソコンへの感染が、施設内のネットワークを通じて他のパソコンやサーバーへ広がり、システム全体が停止してしまう。
- 事業所が管理する他の利用者さんの個人情報や、支援記録などがまとめて盗み出される。
- 情報漏洩の事実が公になると、事業所の社会的信用が失われ、運営そのものに大きな打撃を与える。
今日からできる!脅威から身を守るための基本対策
巧妙化するサイバー攻撃を100%防ぐことは難しいですが、基本的な対策を実践することで、被害に遭うリスクを大幅に減らすことができます。専門的な知識がなくても、今日から始められる簡単な対策を紹介しますので、ぜひ習慣にしてください。
ソフトウェアを常に最新の状態に保つ
ドライブバイダウンロード攻撃は、ソフトウェアの古いバージョンの弱点を狙います。この弱点を塞ぐために、開発メーカーは修正プログラム(アップデート)を配布しています。
- パソコンのOS(Windows Updateなど)は、自動更新を有効にしておく。
- ウイルス対策ソフトは常に最新の状態に更新し、定期的なスキャンを実行する。
- ブラウザやAdobe Reader、Javaなど、よく使うソフトも最新バージョンになっているか確認する。
怪しいメールやサイトに注意する
キーロガーなどのマルウェアは、メールやウェブサイトを通じて侵入してくることがほとんどです。少しでも「おかしいな」と感じたら、慎重に行動することが大切です。
- 心当たりのない送信者からのメールや、不自然な件名のメールに添付されているファイルは絶対に開かない。
- メール本文に記載されているリンクを安易にクリックしない。
- サイトのURLが公式なものと少しだけ違っていたり、日本語の表現が不自然だったりするサイトは、すぐに閉じる。
安全な通信(HTTPS)を確認する
中間者攻撃から身を守るためには、通信が暗号化されているかどうかを確認する癖をつけましょう。特に個人情報を入力するサイトでは、必ずチェックしてください。
- ブラウザのアドレスバーを見て、URLが「http://」ではなく「https://」で始まっていることを確認する。
- アドレスバーに鍵のマークが表示されていることを確認する。
- 公衆Wi-Fiなど、安全性が不明なネットワークでは、個人情報の入力やログインを避ける。
事業所として取り組むべき組織的なセキュリティ対策
個人の対策に加えて、事業所全体で組織的に取り組むことが安全な環境づくりにつながります。利用者さんと職員が一体となりルールを守る意識を持つことが大切で、管理者は仕組みや環境を整える役割を担います。
まずは定期的に研修やポスターなどで情報提供を行い、攻撃手口や対策を分かりやすく共有しましょう。
さらに、すべてのパソコンにウイルス対策ソフトを導入し更新を管理すること、そして報告ルートを明確に周知しておくことが被害拡大を防ぐために重要です。
まとめ
インターネット利用時にはキーロガー、ドライブバイダウンロード、中間者攻撃といった脅威が潜んでおり、情報盗難や金銭被害、事業所全体への影響につながる恐れがあります。
被害を防ぐには、OSやソフトを最新に保つ、怪しいメールやサイトを避ける、HTTPSを確認するなど基本的な対策が有効です。さらに事業所として研修や情報共有を行い、利用者と職員が協力してセキュリティ意識を高めることが安全な環境づくりにつながります。
あとがき
この記事を書きながら、改めてサイバー攻撃の巧妙さと身近さに驚かされました。キーロガーや中間者攻撃はニュースの中だけの出来事ではなく、福祉施設や事業所でも起こり得る現実的な脅威です。
特に、何気なく利用している公衆Wi-Fiや日常のメールのやり取りが、攻撃者にとっては格好の入り口になるという点は強く意識すべきだと感じました。
技術的な知識がなくてもできる基本的な対策を続けることが、自分自身と事業所を守る最初の一歩になるのだと実感しています。

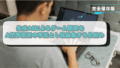

コメント