福祉施設やA型就労継続支援事業所など、人と深く関わる現場でも情報セキュリティは決して他人事ではありません。大切な個人情報を守るためには、サイバー攻撃の手口を知り、適切な対策を講じることが不可欠です。この記事では、特に注意すべき3つのセキュリティ脅威、「サプライチェーン攻撃」「内部脅威」「セッションハイジャック」について、その手口と具体的な対策を分かりやすく解説します。職員も利用者も一丸となって、安全な環境を築いていきましょう。
サプライチェーン攻撃とは?取引先を踏み台にする巧妙な手口
サプライチェーン攻撃とは、直接企業や施設を狙うのではなく、取引先や委託会社などを経由して侵入を試みる手口です。部品やサービスを供給する関連会社を狙うことから、この名が付けられました。
福祉施設の場合、食材の納入業者、清掃・警備会社、部品の仕入れ先、利用中のクラウドサービスなどが対象となります。攻撃者はまず関連組織のシステムに侵入し、そこを足がかりに施設のネットワークへ侵入して情報を盗んだりシステムを破壊したりします。
自施設が直接狙われていないため気づきにくいのが大きな特徴です。例えば、普段利用している業務システムの開発会社が攻撃され、ウイルス入りのアップデートが配布されると、気づかぬうちに施設へ感染が広がる危険があります。
このように、自施設の対策だけでは限界があるため、取引先も含めたサプライチェーン全体でセキュリティ意識を高めることが重要です。
サプライチェーン攻撃から身を守るための具体的な対策
サプライチェーン攻撃を防ぐには、自施設の対策だけでなく取引先も含めた視点が必要です。
信頼関係を大切にしつつ、セキュリティ面での確認や対策を重ねることで、双方を守ることにつながります。日々の業務の中で基本的な対策を継続することが、攻撃者に狙われにくい環境づくりに役立ちます。
委託先や取引先のセキュリティを確認する
まず重要なのは、委託先や取引先がどのようなセキュリティ対策をしているかを確認することです。新しい取引先だけでなく、既存の相手についても定期的にチェックするのが望ましいでしょう。
契約書にセキュリティ条項を盛り込んだり、対策状況をまとめたチェックシートを提出してもらったりする方法があります。
管理体制や連絡体制を明確にしておけば、リスクを減らせます。これは疑うのではなく、協力して守るための体制づくりだという意識が大切です。
ソフトウェアやシステムを最新に保つ
施設で使うOSやソフトウェアを常に最新の状態にしておくことも基本的で重要です。脆弱性が発見されると開発元から修正プログラムが配布されますが、攻撃者はその隙を突いてきます。
更新を後回しにせず速やかに適用することで、万が一取引先経由でウイルスが入り込んでも被害を広げにくくなります。更新通知が来たらすぐ適用するルールを徹底しましょう。
内部脅威とは?最も身近に潜む情報漏洩のリスク
内部脅威とは、組織の職員や元職員、業務委託先の従業員など、内部の人間が原因で発生するセキュリティ上の脅威のことです。この脅威は、大きく分けて二つの種類があります。
一つは、組織に対して恨みを持つなどの理由で、意図的に情報を盗んだり、システムを破壊したりする「悪意のある脅威」です。もう一つは、悪意はないものの、不注意や知識不足から情報を漏洩させてしまう「過失による脅威」です。
実際には後者の「過失」によるインシデントが非常に多く、例えば「個人情報が入ったUSBメモリを外出先で紛失してしまった」「宛先を間違えて、利用者の個人情報を含むメールを外部に送ってしまった」といったヒューマンエラーがこれにあたります。
福祉施設では、利用者の氏名、住所、病歴、障がいの状況など、特に配慮が必要な個人情報を多く取り扱っています。これらの情報が万が一漏洩すれば、利用者本人に多大な迷惑がかかるだけでなく、施設の信頼を大きく損なう事態に発展しかねません。
外部からの攻撃だけでなく、最も身近な内部にこそ大きなリスクが潜んでいることを常に意識しておく必要があります。
内部脅威による被害を防ぐための職員・利用者双方の心構え
内部脅威は、技術的な対策だけで完全に防ぐことは困難です。なぜなら、その原因が「人」にあるからです。そのため、職員一人ひとりのセキュリティ意識の向上が不可欠となります。
また、A型就労継続支援事業所などでは、利用者も業務の一環として情報に触れる機会があるため、利用者に対する分かりやすい説明とサポートも同時に重要となります。
組織全体で情報セキュリティの重要性を共有し、ルールを守る文化を醸成することが、内部脅威から大切な情報を守るための最も確実な道です。
情報セキュリティ教育の徹底とルールの明確化
内部脅威を防ぐための第一歩は、全職員に対する情報セキュリティ教育の徹底です。どのような行為が情報漏洩につながるのか、具体的な事例を交えながら定期的に研修を実施し、危険性を自分事として捉えてもらうことが重要です。
同時に、情報の取り扱いに関するルールを明確に定め、それを全員で遵守する体制を構築します。
例えば、個人情報を含むデータの持ち出しを原則禁止にする、私物のUSBメモリやスマートフォンの業務利用に関するルールを定める、退職する職員には情報保持に関する誓約書を提出してもらう、といった対策が考えられます。
ルールは作成するだけでなく、なぜそのルールが必要なのかを丁寧に説明し、理解を促すことが定着の鍵となります。
アクセス権限の適切な管理
職員がアクセスできる情報の範囲を、その職員の業務内容に応じて必要最小限に制限することも、内部脅威対策として非常に有効です。これを「最小権限の原則」と呼びます。例えば、経理担当の職員が利用者の詳細な個人情報にアクセスする必要はありません。
万が一、ある職員のアカウントが不正利用されたり、その職員が悪意を持ったりした場合でも、アクセス権限が適切に設定されていれば、被害を最小限に食い止めることができます。
また、異動や退職によって不要になったアカウントは、速やかに削除または停止することも忘れてはなりません。放置されたアカウントは、不正アクセスの温床となる危険性があります。
セッションハイジャックとは?ログイン状態を乗っ取る危険な攻撃
セッションハイジャックとは、Webサイトやサービスにログインしている利用者のセッションを乗っ取り、本人になりすまして不正行為を行う攻撃です。
ログイン時に発行される「セッションID」は、一時的な通行手形のようなもので、これがあることで毎回パスワードを入力せずに利用できます。攻撃者はこのセッションIDを盗み、自分のブラウザに設定することで利用者として振る舞うのです。
一度乗っ取られると、パスワードを知らなくてもシステムにアクセスされてしまいます。
例えば、勤怠管理システムや利用者データベースが狙われれば個人情報の流出や改ざんの危険があり、ネットバンキングでは不正送金、SNSでは不適切な投稿など、深刻な被害につながります。
セッションハイジャックを防ぐための基本的なセキュリティ対策
セッションハイジャックは、利用者のセッションIDをいかにして守るかが対策の鍵となります。攻撃者は、通信を盗聴したり、利用者を偽サイトに誘導したりと、様々な方法でセッションIDを狙ってきます。
しかし、これから紹介するような基本的なセキュリティ対策を日頃から心がけることで、そのリスクを大幅に低減させることが可能です。
特別な専門知識が必要なわけではなく、利用者一人ひとりの少しの注意が、自身と組織の情報資産を守る上で大きな力となります。これらの対策を習慣化し、安全にインターネットを利用しましょう。
公共Wi-Fiの利用には注意する
カフェや駅の無料Wi-Fiは便利ですが、特に暗号化されていないパスワード不要のWi-Fiは通信が盗聴されやすく危険です。この状態でログインすると、セッションIDを盗まれる恐れがあります。
業務関連の利用は避け、必ず安全なネットワークを使いましょう。やむを得ず使う場合は、通信を暗号化できるVPNの利用を検討してください。
URLが「https」で始まっているか確認する
Webサイトを利用する際は、URLが「https」で始まっているかを確認しましょう。「https」はSSL/TLSで通信が暗号化されており、盗聴されても内容を解読されにくくなります。
ログインページや個人情報入力の場面では、必ず「https」と鍵マークを確認することが、セッションハイジャック防止につながります。
まとめ
福祉施設やA型事業所でも情報セキュリティの脅威は身近に存在します。サプライチェーン攻撃は取引先を経由して侵入し、内部脅威は職員や利用者の不注意や悪意で情報が漏れる危険があります。
さらにセッションハイジャックはログイン中の通行手形であるセッションIDを盗まれ、本人になりすまされてしまう攻撃です。
これらを防ぐには取引先の対策確認、ソフト更新の徹底、教育と権限管理、公共Wi-Fi回避やhttps利用など日常的な意識と行動が欠かせません。
あとがき
この記事を書きながら、福祉施設やA型事業所の現場における情報セキュリティの重要性を改めて実感しました。外部からの攻撃だけでなく、内部の不注意や悪意、そしてログイン状態を狙う手口まで、多くのリスクが潜んでいます。
しかし、難しい知識がなくても、更新を怠らない、ルールを守る、公共Wi-Fiを避けるといった日常の小さな意識が、大切な利用者や職員の安心を守る大きな力になると感じました。


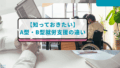
コメント