「もっと主体的に動いてほしい」「自信を持って仕事に取り組んでほしい」──そんな想いを抱えながらも、支援の方法に悩むA型事業所の職員の方は多いのではないでしょうか。従来の指示型支援では引き出せなかった利用者の力を伸ばすカギとして、いま注目されているのがコーチング的支援です。本記事では、専門知識がなくてもすぐに活用できる対話を通じたサポートの基本と、A型支援における活用のヒントをわかりやすく解説します。
第1章:従来の支援とコーチング的支援の違いとは?
A型事業所における従来の支援は、どちらかといえば支援者が主導し、利用者に対して「こうしてください」「次はこれをやりましょう」といった指示型の関わりが中心でした。
この方法は一定の安定性がある一方で、利用者の自ら考える力や自発性を育むには限界があるとも言われています。
そこで注目されているのがコーチング的支援です。コーチングとは、相手にアドバイスを押しつけるのではなく、問いかけや対話を通じて本人の気づきを促し、自分で答えを見つけられるよう支援する関わり方です。
もともとはビジネスやスポーツの分野で活用されてきた手法ですが、福祉現場でも応用されるようになり、特に就労支援の領域では注目が高まっています。
利用者が自分でどうしたいか、どうすればよいかを考える力を持つことで、支援者がいなくても前向きに行動できるようになり、結果的に就労定着にもつながると言われています。
従来の支援とコーチング的支援との違いは、まさに支援者主導から利用者主体への転換にあるのです。
第2章:利用者のやる気を引き出す「傾聴」と「問い」

支援の現場で利用者のやる気を引き出すために重要な技術として傾聴が挙げられます。傾聴とは、相手の話を途中で遮らず、評価や否定をせずにそのまま受け止める姿勢を指します。
利用者が安心して話せる環境を作ることで、自分の気持ちや考えを整理しやすくなり、自己理解が深まります。これにより、利用者自身が自分の課題や目標に気づきやすくなるのです。
さらに、傾聴とセットで用いられるのが問いかけです。単なる質問ではなく、利用者の思考や感情を深める効果的な問いかけが求められます。
例えば「どうしたいと思っている?」という問いは、相手に自分の意思や目標を明確にさせ、行動を起こすきっかけになります。コーチング的支援においては、このような問いかけが利用者の主体性を促進し、前向きな変化を引き出す大きな力となります。
傾聴と効果的な問いかけを組み合わせることで、利用者が自分自身の気持ちや目標に気づき、自律的に行動する意欲が高まるのです。
これが、単なる指示型支援と異なる、コーチング的支援の大きな特徴と言えるでしょう。さらに、こうした対話を繰り返すことで信頼関係が築かれ、長期的な支援の質も向上していきます。
第3章:目標設定と行動促進〜主体性を育てる対話術〜
利用者の主体性を育てる支援では、具体的かつ達成可能な目標設定が欠かせません。ここで役立つのが「SMART」目標設定法です。
SMARTとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)の5つの条件を満たす目標のことを指します。
この手法を用いることで、利用者が自分の目標を明確に理解し、達成に向けて取り組みやすくなります。
さらに、大きな目標をいくつかの小さな行動計画に分解することも重要です。これにより、達成感を得やすくなりモチベーションを持続させやすくなります。例えば、週に1回職場に遅刻しないという具体的な小目標を設定することで行動の習慣化につながります。
また、自分で決めたことという意識はやる気を持続させる大きな原動力です。支援者は利用者との対話を通じて、目標を一方的に押し付けるのではなく、本人が納得して選択できるよう促します。
このプロセスにより、目標が単なる課題ではなく自分ごととなり、行動への主体的な姿勢が生まれるのです。
このように、対話を軸にした目標設定と行動計画は、利用者の主体性を育て、就労支援の成功に不可欠な要素となっています。
第4章:「答えは本人の中にある」を信じる支援者の姿勢
支援者にとって重要なのは答えは支援者ではなく、本人の中にあると信じる姿勢です。支援現場では、つい正解を提示したくなる場面がありますが、支援者が一方的に正解を押し付けることは利用者の主体性を奪い、自立の妨げにもなりかねません。
特に障害福祉の分野では、自己決定の尊重が基本的な支援原則とされており、利用者が自分の価値観に基づいて選択できるよう促すことが求められています。
また、利用者の可能性を信じる姿勢は、支援者の関わり方に大きな影響を与えます。支援者の期待や信頼は、本人の自信や行動意欲に直結します。
これはピグマリオン効果としても知られており、教育や心理学の分野でも広く実証されています。
さらに、失敗を成長のプロセスと捉える視点も不可欠です。失敗を恐れずに挑戦し、それを次の行動に活かす経験を支援者が肯定することで、利用者は学びながら前に進む力を養うことができます。
このような姿勢の支援こそが、利用者の本当の自立を支えるものとなります。
第5章:A型職員が実践できる3つのコーチングスキル

A型事業所の支援において、利用者の自立と成長を促すためには、単なる指導ではなく対話的な関わりが欠かせません。そこで注目したいのが、コーチングに基づく3つの基本スキルです。
まず1つ目はリフレクションです。これは、利用者の発言や行動に対して、「そう感じたんですね」「そのとき○○と思ったんですね」と気持ちや考えを言葉で返す技術です。相手が自分の内面に気づく手助けになり、自己理解や自己決定を深めることができます。
2つ目は承認です。できたことや努力した過程を具体的に認めることで、利用者の自己効力感を高める効果があります。「毎日通所できていることは立派なことです」といった声かけが自信につながります。これは心理学でも肯定的フィードバックが行動継続を促すと実証されています。
そして3つ目は沈黙を恐れないことです。すぐに言葉を返そうとせず、利用者が自分の言葉を探す時間を尊重する姿勢が、自分の気持ちや考えを見つめ直す事と主体的選択を引き出します。沈黙は対話の一部であり、焦らず待つことも立派な支援スキルです。
この3つのスキルを意識的に使うことで、A型職員は利用者の自ら気づき、決める力を育てる支援が実践できます。
第6章:株式会社さちなび:コーチングで働く意義を再発見し、個人の成長を支援
すでにA型事業所でコーチングを取り入れている会社をご紹介しましょう。株式会社さちなびの就労継続支援A型事業所は、働くことを単なる生計維持の手段ではなく、自己表現の場と捉え、準従業員の働く意義の再発見に焦点を当てています。
ここでは、コーチング手法を積極的に活用し、一人ひとりの価値観や得意なことを丁寧に引き出すことで、仕事への内発的なモチベーション向上と、周囲との良好な関係構築を後押ししているのです。
この個別ニーズに合わせたきめ細やかな支援は、準従業員が安心して自分らしく働ける環境を提供し、個々の成長とキャリア形成を強力に支援しています。提供される成長を促すコーチングは、準従業員が自身の能力や可能性を再認識し、目標達成へ向かうための強力なツールです。
個々の特性に応じたオーダーメイドのコーチングを通じて、自己理解を深め、必要な職業スキルを効果的に伸ばせるようサポートします。このプロセスにより、働く上での不安や自信のなさを乗り越え、ポジティブな変化を実感できるでしょう。
具体的な目標設定と定期的なフィードバックにより、努力が適切に評価される環境を構築し、一人ひとりのユニークな能力を最大限に引き出すことで、より充実した人生の実現に貢献しているわけです。
コーチングを通じて、働くことへの新たな視点を見つけ、あなたの可能性を広げてみませんか?
まとめ:コーチングは“技術”より“信じる力”から始まる

コーチング的支援は、特別なテクニックよりもこの人ならできると信じるまなざしから始まります。
支援者が一歩引き、利用者に問いかけ、耳を傾ける事が大切です。その積み重ねが、自立や企業就労への道を開くでしょう。
A型事業所が気づきの場となれば、利用者はもっと前向きに、自分らしく働くことができるようになります。
あとがき
私は今回コーチングについて調べてみて、確かに、正解を教えてもらうより、自分で考えた答えの方が、責任感もさらに生まれると思いました。
こうしなさいよりも、どう思う?と聞かれる方が、心も動くかもしれません。コーチングは小さな問いかけが、大きな変化につながると感じました。

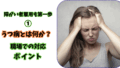

コメント