就労支援A型事業所では、利用者の働く場を守るためにも、新たな業務の立案が重要です。でも「何から考えたらいいの?」と悩む職員も多いはず。そんなときに役立つのが、情報を整理しながらアイデアを引き出す「KJ法」という思考法です。本記事ではその基本と活用法を、わかりやすくご紹介します。
第1章:そもそも就労支援A型事業所ってどんなところ?
新しい業務のことを考える前に、まずは就労支援A型事業所がどんな場所で、どんな役割を担っているのかをしっかり押さえておきましょう。制度的な背景から、日々行われている作業内容までを簡潔にご紹介します。
福祉と雇用を両立する「就労支援A型」
就労支援A型事業所は、障がいのある方が「働くこと」を通じて自立を目指す福祉サービスです。一般就労が難しい方でも、雇用契約を結んで最低賃金を保証された形で働くことができるのが特徴です。つまり、福祉的な支援と雇用の仕組みが組み合わさった場所なのです。
一般企業との違いと提供される業務内容
一般企業と異なり、就労支援A型では作業の内容や量が利用者の特性や体調に配慮して設定されます。実際の業務には、軽作業、清掃、農作業、ECサイトの発送業務など比較的取り組みやすい内容が多く採用されています。
新しい業務が必要とされる理由
近年では障がい者のニーズが多様化し、地域とのつながりを重視した取り組みが求められるようになってきました。そのため、従来の業務に加えて、新たな業務の導入が事業所の継続的な運営や成長のカギとなってきています。
第2章:業務を増やしたいけど、何から考えればいいの?

いざ新しい業務を導入しようと思っても、「何をどう考えればいいのか分からない」と感じた経験はありませんか?この章では、A型事業所でよくある業務立案の悩みと、乗り越えるための発想のヒントをご紹介します。
思いつきでは続かない…新業務立案の壁
「新しい仕事を始めたいけど、なかなか良いアイデアが出てこない…」と感じる職員の方も多いのではないでしょうか。
実際、新たな業務を検討する場面では、「職員の主観で方向性が偏ってしまう」「利用者のニーズとズレがある」「形にはなったけど現場に定着しない」といった悩みが多く聞かれます。
こうした課題に共通するのは、アイデアの出し方や情報の整理方法が曖昧なまま進めてしまっている点です。感覚だけで「良さそう」と思っても、あとから矛盾や無理が出てきて、結局うまくいかない…そんなケースは決して珍しくありません。
業務づくりに必要なのは「考える力」と「見える化」
だからこそ、新しい業務を考えるときには、「どう考えるか」というプロセスがとても重要です。ただアイデアを出すだけでなく、バラバラの意見を整理して本質を見つける力が求められます。そのために必要なのが、「情報を可視化して、共通点や意味を見つけていく」手法です。
KJ法というロジカルな思考法に注目
そこで注目されているのが、KJ法という考え方です。もともとは研究者がフィールドワークの中で使っていた方法ですが、今では企業の企画会議や教育現場でも活用されています。
KJ法は複雑な情報を整理しながら、チーム全体で納得感のある方針をつくりあげていくのにぴったりの思考法です。就労支援A型の現場でも、利用者や職員の声を活かしながら新たな業務を検討する際に大きな助けになるはずです。
第3章:KJ法ってなに?やさしく解説!
「いいアイデアが出ない」「話がまとまらない」そんな場面で効果を発揮するのが、KJ法という思考法です。この章では、KJ法の基本的な考え方とその特徴をやさしくご紹介します。
生みの親は文化人類学者・川喜田二郎氏
KJ法は、日本の文化人類学者・川喜田二郎さんによって開発されました。もともとは、現地調査で集めた情報をどう整理し、意味のある結論を導き出すかを考える中で生まれた手法です。
グルーピングで「見えないものを見える化」する
KJ法の最大の特徴は、「言葉で書き出した情報をグループ化することで、共通点や本質を発見する」点です。アイデアや意見をカードや付箋に書き出し、それを仲間同士で分類・整理することで、ばらばらだった思考が視覚的にまとまっていきます。
A型事業所にもぴったりな理由
KJ法は、言葉で考えをまとめるのが難しい人でも「書いて並べる」ことで参加しやすくなります。これは、利用者や支援者の多様な視点を活かしたいA型事業所にとって、大きな強みになるのです。
第4章:KJ法の基本ステップを覚えよう

KJ法は専門知識がなくてもすぐに取り入れられる思考法です。ここでは、就労支援A型事業所でも実践しやすいよう、KJ法の基本的な5つのステップをご紹介します。
Step1:テーマに沿って自由に書き出す(ブレインストーミング)
まずは「どんな業務ができるか」など、テーマを決めて、それに関する思いつきや意見を1枚ずつカードや付箋に書いていきます。このように発想を思いつくままに挙げていく手法をブレインストーミングといいます。
文字数は短くても構いません。とにかく、頭に浮かんだことをどんどん出すのがコツです。
Step2:似たもの同士をグループに分ける
次に、ブレインストーミングで書き出したカードを机の上などに広げ、内容が似ているものや、関連があるもの同士で集めていきます。そうすることで、「何が話題の中心なのか」が自然と見えてきます。
Step3:それぞれのグループにラベルをつける
グルーピングが終わったら、そのまとまりに名前をつけます。たとえば「利用者が得意な作業」「地域のニーズに合うもの」など、わかりやすい言葉で分類しましょう。
Step4:全体像を図にして整理する
今度は、グループとグループの関係性を図で整理します。ホワイトボードや模造紙を使って、どこが中心になりそうか、どの項目がつながるかを線で結ぶと、全体の構造が見えてきます。
Step5:アイデアの核を深掘りして方向性を決める
図の中から「これは可能性がある」「現実的にできそう」と思えるグループを掘り下げて、具体的な業務内容や進め方を考えていきましょう。ここまでくれば、漠然としていた新業務の姿がかなり具体化されているはずです。
このように、KJ法はカードや付箋、ホワイトボードがあれば誰でもすぐに始められるシンプルな手法です。特別な道具やスキルは必要ありません。あとは実際にやってみるだけです!
第5章:KJ法を使って「チームで育てる業務づくり」へ
KJ法を使って立案した業務は、初期案で完成するとは限りません。むしろ、実行してみてからの調整や改良がとても重要です。この章では、業務を「育てる」視点から、KJ法の継続的な使い方をご紹介します。
一度きりで終わらせないのがKJ法の真価
KJ法の良さは、「その場かぎりの発想」で終わらないことです。いったん業務案ができても、数カ月後に実施状況を振り返り、再度カードを追加・再整理することで、現場に合った形へと自然に進化させていくことができます。
こうした継続的な見直しにより、「利用者のスキルに合っていない」「予想より工数がかかる」といったズレにも柔軟に対応できるようになります。まさに、業務そのものを「育てていく」感覚です。
利用者と職員、どちらの声も活かせる
KJ法は、利用者の声を「書いて・見て・話し合う」形で拾いやすくなるため、意思表示が苦手な方の気持ちにも気づきやすくなります。それと同時に、職員間の共有も深まり、一体感を育てる効果も期待できます。
経営と福祉をつなぐ「思考の道具」
就労支援A型の業務は、福祉的価値と経済的持続可能性の両方を満たす必要があります。KJ法は、バラバラに見えていた視点を整理し、その中から実行可能な方針を導き出す「思考の道具」です。
個人のひらめきだけに頼らず、チームで取り組む姿勢が、これからのA型事業所には求められています。
まとめ

就労支援A型事業所で新しい業務を計画するとき、アイデアを整理し全員の意見を活かせるKJ法はとても役立ちます。複雑な情報をカードに書き出しグループ分けすることで、本質的な方向性が見えてきます。
KJ法は一度で完璧な計画をつくるものではなく、繰り返し見直しながら育てていくことがポイントです。これにより、福祉と経営の両立を目指すチームづくりが進み、持続可能な業務づくりにつながるのです。
あとがき
KJ法は様々な分野に使える「汎用性の高い思考法」とも言えるでしょう。じつはこの記事作成においてもKJ法が活用されているのです。
まず、このサイトで扱われる記事のテーマは就労支援A型関連となっているのでそれに関する「ペルソナ」と「キーワード」を考えていきます。この2つそれぞれについてブレインストーミングを行うわけです。その際AIを活用しました。
AIが提案したアイデアとして、ペルソナでは「事業計画に携わる職員」、キーワードでは「KJ法」というものがありました。この2つを組み合わせて「事業計画作成に使えるKJ法」という事柄を記事の内容とし、それについてAIに記事作成を依頼しました。
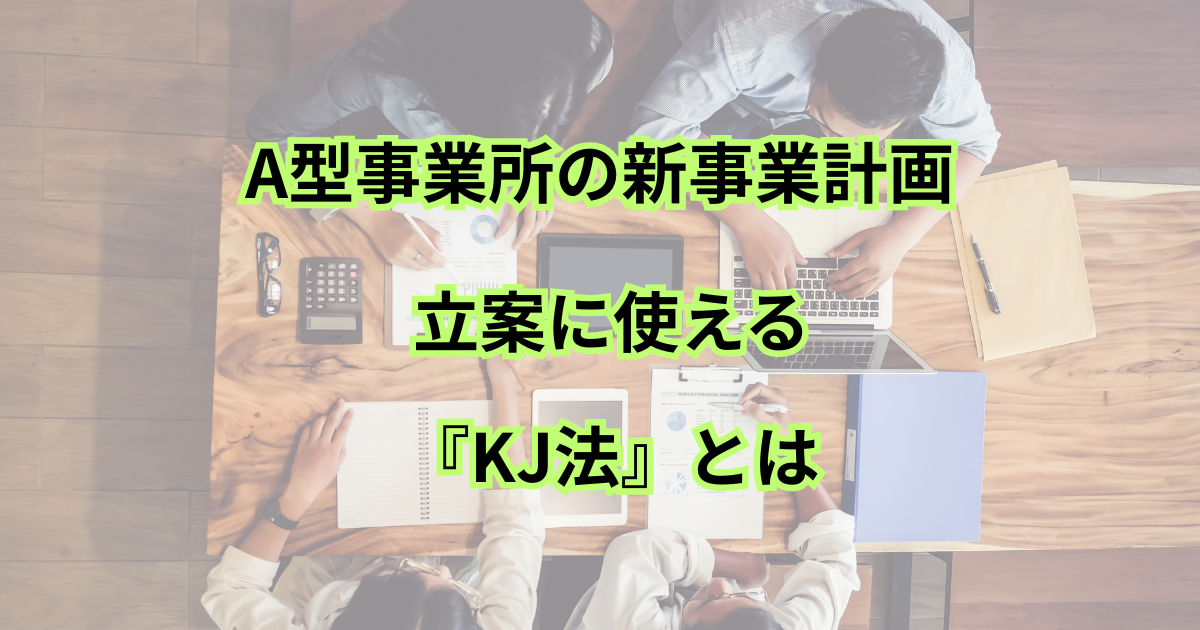
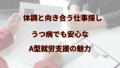

コメント