統合失調型パーソナリティ症の特性を持つ方が、職場で安心して働くためには自分の特性を理解し、周囲とのコミュニケーションを工夫することが大切です。この記事では職場でのトラブルを避ける具体的な方法をわかりやすく解説します。
第1章:統合失調型パーソナリティ症とは?統合失調症や他の障害との違い
統合失調型パーソナリティ症(Schizotypal Personality Disorder、略してSTPD。以下、STPDと表記します。)は、名前が似ている統合失調症とは異なりながらも、独特の思考や行動パターンが見られるパーソナリティ障害の一つです。
ここではSTPDの特徴や、統合失調症との違いについてわかりやすく解説します。
STPDの特徴について
STPDの方は妄想的な考え方や奇妙な言動が見られやすく、対人関係での不安や被害的な解釈をしがちです。周囲の言葉を悪く受け取ったり、疑い深くなったりすることがあります。こうした特徴は本人に自覚がない場合も多く、周囲との距離感にズレが生まれることがあります。
統合失調症との違い
統合失調症とSTPDは似た名前ですが別の症状です。STPDでは統合失調症に似た状態が見られますが、傾向的に穏やかであり、統合失調症の診断基準を満たしません。
しかし思考や行動に独特の奇妙さがあり、周囲からは誤解されやすい特徴があります。奇妙な信念や言動が強く現れ、これが職場での誤解やすれ違いの原因となることが多いのです。
”傾向”としての理解が重要
STPDは性格の傾向として理解することが大切です。正しく理解し、配慮された環境であれば、十分に仕事を続けることが可能です。自分の特性を知り、無理のない働き方を見つけることが安心につながります。
第2章:STPDの人が職場で直面しやすい誤解やトラブル
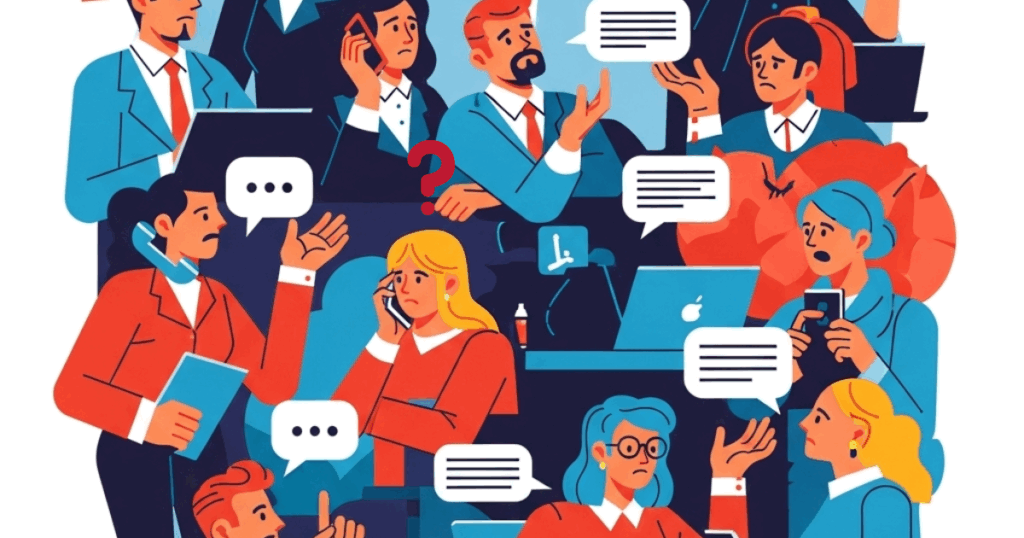
STPDの特性は職場で誤解されやすく、トラブルにつながることがあります。ここでは、よくある誤解やトラブルの内容について具体的に説明します。
”言動が変わっている”と思われること
本人は自然に話したり行動したりしていても、周囲からは「変わっている」と見られてしまうことがあります。このため、敬遠されたり距離を取られたりする場合があります。
過剰に被害的・疑い深く解釈してしまうこと
周囲の言葉や態度を悪意があると感じやすく、過剰に疑ったり被害的に考えてしまう傾向があります。その結果、誤解が生まれトラブルに発展しやすくなります。
意図の読み違いによる孤立やトラブル
相手の言葉の裏を深読みしすぎたり、場の雰囲気を読み取るのが苦手だったりして、意図を誤解しやすいです。これが職場での孤立や摩擦につながることもあります。
”空気を読まない” ”距離感が変”と思われやすい
対人関係における距離感が一般的なものと異なるため、周囲から空気が読めない、距離感が変と評価されがちです。
職場内でのサポートが届きにくいことも
こうした誤解が積み重なると、本人が困っていても周囲が気づきにくく、必要なサポートが受けられないことがあります。その結果、ストレスや不安が増すこともあるため、早めの理解と配慮が重要です。
第3章:誤解を減らすための自己理解と伝え方の工夫
職場での誤解やトラブルを減らすためには、まず自分自身の特性をしっかり理解することが大切です。自分がどんな場面で周囲とズレを感じやすいのかを知ることで、対処の仕方が見えてきます。
ズレが生じやすい場面を知る
たとえば、相手の言葉の意図を読み間違えたり、会話の細かいニュアンスを捉えられなかったりすることがあります。こうした場面では誤解が起きやすいので、気づいたときに「自分はこう感じたけれど本当はどういう意味?」と相手に確認する習慣をつけることが効果的です。
疑いや不安を感じたら確認を心がける
感情的にすぐ結論を出すのではなく、一歩立ち止まって話の内容や状況を丁寧に見直すことが大切です。疑いや不安を抱いたときは、そのままにせずに確認する姿勢を持つことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
伝え方に安心感を添える
自分の特性を職場の人に伝えるときは、ただ「こういう傾向があります」と話すだけでなく、「こういうことがあっても安心してください」といった言葉を添えると、相手も理解しやすくなります。安心感を持ってもらうことが、良いコミュニケーションの土台になります。
書く・メモ・事前伝達の工夫
言葉だけのやりとりが難しい場合は、書面やメモを使う方法も効果的です。特に重要なことは事前に伝えておくと、誤解を減らすことができます。こうした非対面的な工夫はストレスを軽減し、スムーズなコミュニケーションを助けます。
特性を”自分の説明書”としてポジティブに伝える
自分の特性を説明する際は、ネガティブにとらえず自分の説明書のようにポジティブな視点で伝えると、周囲も受け入れやすくなります。そうすることで、自分らしさを大切にしながら職場での理解を深められます。
第4章:人間関係の苦手さを補う職場での行動パターン

人間関係に苦手意識がある場合でも、ちょっとした行動の工夫で周囲との信頼関係を築くことができます。ここでは、日常の中で実践しやすいポイントを紹介します。
基本の”笑顔”と”あいさつ””の力
難しい話をしなくても、笑顔であいさつをするだけで相手の印象は大きく変わります。第一印象が良いと、その後のコミュニケーションもスムーズに進みやすくなります。
会話が苦手でも”聞く姿勢”を見せる
自分から話すのが苦手でも、相手の話をしっかり聞く姿勢を見せることで、信頼を得ることができます。相手が話しやすい環境を作ることが人間関係を良好に保つ秘訣です。
”疑う前に確かめる”習慣で摩擦を防ぐ
誤解からトラブルになるのを防ぐため、疑いを持ったらすぐに決めつけず、確認する習慣をつけましょう。冷静に事実を確かめることで、対人摩擦を減らせます。
トラブル時は”一度深呼吸から相談”を大切に
もしトラブルが起きたら、慌てずにまず深呼吸をして気持ちを落ち着けることが重要です。その上で信頼できる人に相談すると、解決に向けて動きやすくなります。
”味方を1人”つくる感覚で職場に臨む
全員とうまくいかなくても、ひとりでも味方を作ることが安心感につながります。誰か一人でも理解者がいることで、心強く感じられ、仕事を続けやすくなります。
第5章:長く働き続けるために大切な環境との付き合い方
仕事を無理なく続けていくためには、自分の特性や体調に合わせた働き方を見つけ、環境と上手に付き合っていく力が求められます。この章では、働き続けるうえでのヒントをご紹介します。
自分に合った働き方を見つける”自己調整力”
全ての場面で完璧にこなそうとせず、自分にとってやりやすいやり方や関わり方を見つけていくことが長く働くポイントです。「これは自分に合っている」「このやり方なら続けられる」という視点で日々調整していきましょう。
苦手な場面は”逃げる”ではなく”対応を変える”
苦手な業務や人間関係があると、どうしても避けたくなる気持ちは自然です。ただし、それを逃げととらえる必要はありません。対応の仕方を工夫することが、自分を守りながら働く上でとても大事です。
信頼できる一人に特性を伝える
職場全体に理解を求めるのは難しくても、信頼できる一人に自分の特性を伝えておくだけで気持ちはぐっと楽になります。困ったときに相談できる「よりどころ」があるだけで安心感が違います。
小さな成功体験の積み重ねが自信に
大きなことを一度に成し遂げる必要はありません。今日できたこと、昨日より楽にできたこと。そうした小さな成功を積み重ねることで、自信が少しずつ育ちます。
”無理しない働き方”という視点の大切さ
働くこと=がんばり続けることと思いがちですが、それでは長続きしません。自分のペースを大切にしながら、無理なく働くことが、結果的に長く職場にいられる秘訣です。
まとめ

統合失調型パーソナリティ症(STPD)の特性を持つ方が職場で安心して働き続けるためには、まず自分の特性を正しく理解し、それを伝える工夫や行動のパターンを身につけることが大切です。
誤解を防ぐための伝え方や、無理のない業務の進め方、信頼できる人とのつながりをつくることで、働くうえでの不安を減らすことができます。完璧を目指さなくても大丈夫。自分らしいやり方で、少しずつ職場に慣れていきましょう。
あとがき
STPDという特性がもたらす奇抜かつ奇妙な言動というのは、人との誤解をもたらしやすいものです。誤解を恐れるあまり、コミュニケーションを避けてしまいがちにもなるでしょう。
この特性を持ちつつ、かつコミュニケーションを取る方法としては、自分の特性を見つめ直しながら、良好な人間関係を保つにはどうすればいいか、考え続けることではないか、と筆者は思います。
その道程でさまざまな失敗が生じることでしょう。しかし失敗を立て直すリカバー力こそお仕事を続けていく上で最も有効な能力であり、それによって失敗から学び大きく成長を遂げられるのではないでしょうか。
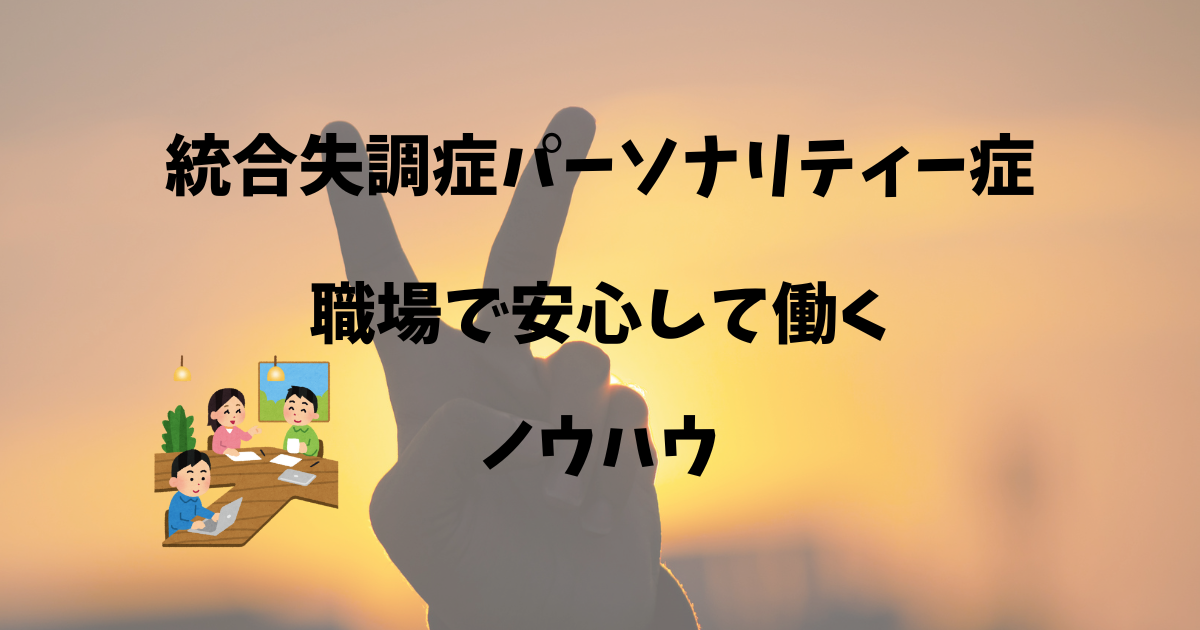
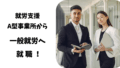
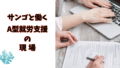
コメント