「働いてみたいけれど、いきなりは不安…」そんな想いを抱える障害のある方と、「雇いたいけれど、うまくサポートできるか不安」という企業をつなぐ制度が障害者トライアル雇用です。企業にとっても、制度活用によりリスクを抑えて人材と出会えるメリットがあります。この記事では、障害者トライアル雇用の仕組みや活用方法、メリット、導入の流れまでわかりやすく解説していきます。
1. 障害者トライアル雇用とは?
障害者トライアル雇用制度は、障害のある方が安心して働き始められるように、国(厚生労働省)が設けた支援制度です。
企業が障害のある求職者を一定期間「試しに」雇用し、その後に正式な雇用につなげることを目的としています。働く側も雇う側も、お互いに無理のない形で仕事を始められるように考えられた仕組みです。
この制度には、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2つの種類があります。
対象となる人の条件や働く時間の長さなどに違いがありますが、どちらも共通して、制度を利用した企業には助成金が支給されます。経済的な支援を受けながら、障害者雇用に安心して取り組めるよう工夫されています。
最近では、精神障害や発達障害など、就職に不安を感じやすい方への支援がとくに重視されています。初めて障害者雇用を行う企業にとっても、短い期間から始められる点は大きなメリットであり、安心して導入できる制度といえるでしょう。
また、障害のある方にとっても、自分に合った職場や仕事内容を実際に体験しながら選ぶことができるため、働くことへの自信や安心感につながります。一般就労へとスムーズに進むための大切なステップにもなる制度です。
2. 障害者トライアルコースとは?

障害者トライアルコースは、就職が困難とされる障害者の方を企業が一定期間雇い、職場に合うかどうかをお互いに確認できる制度です。
働く側と雇う側、双方が実際に働く中で適性や働き方を確認できるため、ミスマッチを防ぎやすいのが特徴です。
制度の対象となるのは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定されているすべての障害者です。したがって、障害の種類や原因による制限はありません
ただし、この制度を利用して企業が助成金を受け取る場合は、以下のような条件を満たす必要があります。
- 継続的に働くことを希望し、トライアル雇用制度を理解したうえで利用を希望していること
- 障害者雇用促進法に基づく障害者であり、かつ次のいずれかに該当すること
- 未経験の職種に就職を希望している
- 直近2年以内に離職または転職が2回以上ある
- 6か月以上の離職期間がある
- 重度の身体障害・知的障害・精神障害のいずれかに該当する
助成金については、精神障害のある方を雇用した場合、月額最大8万円を3か月間、その後は月額最大4万円を3か月間、最長6か月間の支給が受けられます。
それ以外の対象者を雇用した場合には、月額最大4万円が最長3か月支給されます。
このように、障害者トライアルコースは、障害のある方にとって職場に慣れるための大切な一歩であり、企業にとっても雇用への理解を深める機会となる制度です。
3. 短時間トライアルコースとは?
障害者短時間トライアルコースは、体調や生活リズムなどの理由から、まずは短時間から働き始めたいという障害者の方のために設けられた制度です。特に、精神障害者または発達障害者を対象としています。
この制度では、週の所定労働時間を10時間以上20時間未満からスタートし、働きながら徐々に職場に慣れ、最終的には週20時間以上の勤務を目指していくことが前提となっています。これは、無理のないペースで就労経験を積んでもらうための設計です。
企業が助成金を受けるためには、以下のような条件を満たして雇用を行う必要があります。
- 対象者が継続的に働く意志をもち、制度の内容を理解したうえで利用を希望していること
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者からの紹介により雇い入れていること
- 雇用期間が3か月から12か月の範囲であること
助成金は、支給対象者1人あたり月額最大4万円が、最長12か月間支給されます。これにより企業は、雇用にかかる負担を抑えながら、障害のある方の職場適応を丁寧に支援することができます。
また、求職者にとっても、いきなりフルタイムで働くことに不安を感じている場合でも、自分のペースで職場に慣れることができるのは大きな安心材料です。
トライアル期間終了後、企業はその方を正式に採用するかどうかを判断します。この制度は、精神障害や発達障害のある方にとって、一般就労への第一歩を踏み出すための心強い支援となっています。
4. 企業にとってのメリットとは?
障害者トライアル雇用制度は、障害者にとっての支援になるだけでなく、企業側にも多くのメリットがあります。
最大の利点は、「実際に働く姿を見てから判断できる」という点です。履歴書や面接だけでは分かりにくい適性を、現場で確認できる機会となるのです。
また、雇用に対する不安を和らげる支援策として、以下のような制度的な後押しがあります。
- 助成金制度の活用:月額最大8万円の支援でコストを抑えられる
- ハローワークのサポート:マッチングから契約、フォローアップまで支援
- トライアル期間の活用:教育・業務訓練期間として位置づけられる
さらに、企業の障害者雇用率の達成にも役立ちます。法定雇用率を満たすためには、安定した雇用が不可欠ですが、いきなりの採用には心理的・実務的なハードルがあります。
トライアル雇用を通じて、職場環境や受け入れ体制の整備が進むことで、長期雇用にもつながりやすくなります。
結果として、企業の多様性の推進や職場の活性化にも寄与し、社会的信用の向上にもつながるといえるでしょう。
5. 障害者本人にとっての安心な一歩に!

制度の恩恵を受けるのは、企業だけではありません。障害のある求職者にとっても、この制度は大きな助けとなります。まず何よりトライアルという期間があることで、「続けられるか不安」という気持ちに余裕が生まれます。
この期間は、自分にとっての働きやすさを探るチャンスです。仕事内容、人間関係、通勤時間、職場の雰囲気などを実際に体験できるため、ミスマッチを防ぐことができます。
また、週10時間からのスタートも可能なため、体力や生活リズムに合わせて段階的に就労できます。
トライアル期間中は、実際に職場の雰囲気や仕事の進め方、人間関係などを体験しながら働くことができます。そのため、いきなり本格的に働くことに不安を感じていた方にとっても、「この職場なら続けられそう」といった安心感を得やすくなります。
わからないことや不安なことがあっても、職場とのコミュニケーションを通じて確認しながら進められるため、自分に合った働き方を見つけるきっかけにもなります。
無理なく働き始められる入口として、障害者トライアル雇用は心強い制度といえるでしょう。
6. 制度を活用するまでの流れと注意点
障害者トライアル雇用を導入するためには、いくつかのステップと注意点があります。企業と求職者双方がスムーズに進められるよう、事前に流れを把握しておくことが重要です。
まず、企業側はハローワークに求人申込を行い、トライアルコースの利用を希望することを伝えます。次に対象となる求職者とのマッチングが行われ、面接による選考や実地計画書の提出などを経て、雇用が始まります。
雇用開始後は、決められた就労時間や業務内容に沿って業務が行われます。必要に応じて職場内でのサポート体制を整え、適応を支援します。
注意すべき点としては、「トライアルだから何でもOK」ではなく、労働法や契約条件の遵守が前提であることを忘れてはいけません。加えて、トライアル期間終了後に必ずしも採用義務があるわけではありませんが、誠実な判断と記録が必要とされます。
制度を正しく理解し、活用することで、障害者の可能性を広げるきっかけになります。
7. まとめ

障害者トライアル雇用は、誰かの「働きたい」という気持ちと、「支えたい」という思いを結ぶ制度です。制度を知り、活用することが、新たな働く未来を開く一歩になります。
迷いや不安があっても大丈夫です。小さな一歩が、大きな変化を生むこともあります。あなたのその一歩を、応援しています。
8. あとがき
制度の説明だけでは、なかなか「働く」ことの実感は湧きにくいものです。でも、トライアル雇用なら、実際の職場で過ごすことで、自分に合うかどうかを肌で感じることができます。
いきなり本格的に働くのではなく、「体験してから決められる」という仕組みがあるのは、障害のある方にとってとても大きな安心材料です。
それは、誰かに合わせるのではなく、自分のリズムを大切にできるスタートでもあります。焦らず、自分らしく働ける場所を見つけていけることを願っています。
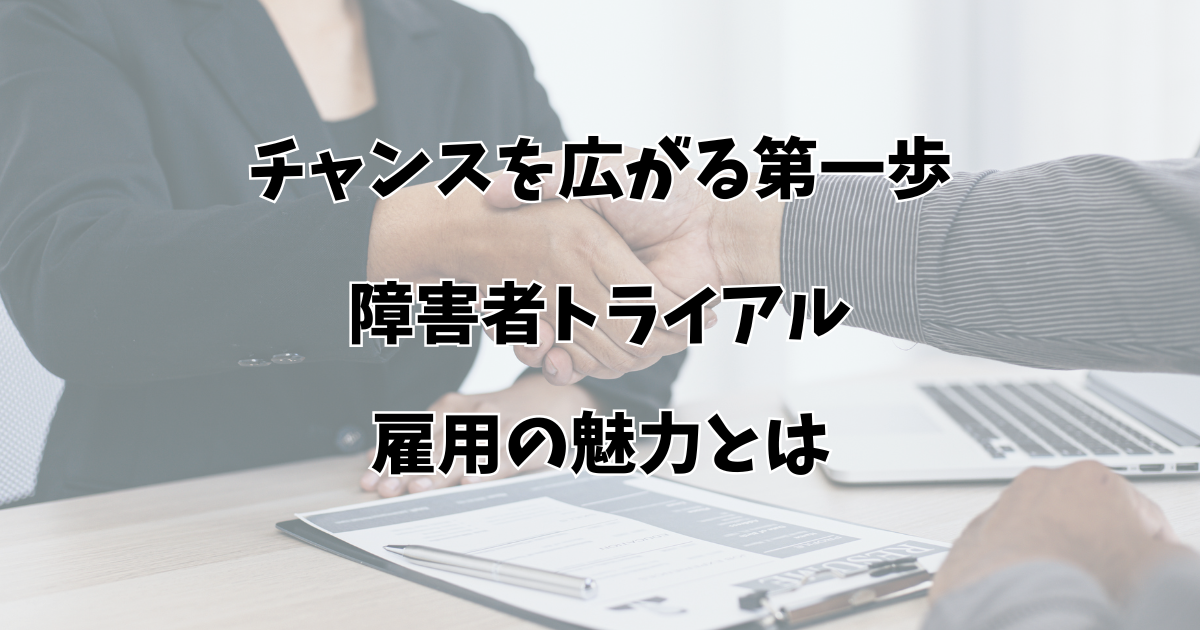
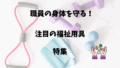
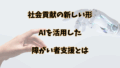
コメント