障がいのある方の就労を支援する専門職である障がい者支援員にとって、関連法規の理解は不可欠です。中でも「障がい者雇用促進法」は、支援の根幹をなす最も重要な法律と言えるでしょう。この法律は、障がいのある方の雇用機会を確保し、その能力を社会で発揮できるよう支援するためのものです。この記事では、障がい者支援員が現場で活かすために知っておきたい障がい者雇用促進法の重要なポイントを、わかりやすく解説していきます。
障がい者雇用促進法の基本理念と目的
障がい者の雇用の促進等に関する法律」は、「障がい者雇用促進法」とも呼ばれています。すべての国民が障がいの有無にかかわらず、その能力と適性に応じて職業に就き、社会の一員として自立した生活を送ることを目指す、という基本理念に基づいて定められました。
この法律の目的は、単に障がいのある方の雇用者数を増やすことだけではありません。職業リハビリテーションの推進や、個々の能力を最大限に発揮できる環境整備を通じて、誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社会」を実現することにあります。
この理念を理解することは、支援員が日々の業務において、利用者一人ひとりの尊厳を守り、その可能性を信じて支援を行う上で、非常に重要な土台と言えます。
障がい者雇用促進法では、雇用における機会均等を確保し、障がいを理由とする不利益な取り扱いをなくすための具体的なルールが定められています。そのため、支援員は法律の目的を深く理解し、利用者の権利を守る代弁者としての役割も担っていると言えるでしょう。
支援員が押さえるべき!法定雇用率とは?

障がい者雇用促進法の中核をなす制度の一つが「法定雇用率」です。これは、事業主に対し、その常時雇用する労働者の数に一定の率を乗じて得た数以上の障がい者を雇用することを義務付けるものです。
支援員として、この法定雇用率の仕組みを正確に理解しておくことは、企業へのアプローチや利用者への説明において極めて重要になります。
法定雇用率は、共生社会の実現という理念が具体的な形で企業に求められるものであり、定期的に見直しが行われています。現在の法定雇用率は以下の通りです。
- 民間企業: 2.5%
- 国、地方公共団体など: 2.8%
- 都道府県などの教育委員会: 2.7%
この比率は、社会情勢や障がいのある方の就労希望者の状況などを踏まえて決定されます。例えば、民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられており、今後もこの傾向は続くと考えられます。
支援員は、この法定雇用率の存在を背景に、企業に対して障がい者雇用の意義やメリットを具体的に説明することが求められます。
また、利用者が就職活動を行う際には、法定雇用率を達成している企業、あるいは達成しようと努力している企業の情報を提供することも、大切な支援の一つとなります。
常用労働者数が40人以上の企業が、この雇用義務の対象となることも、基本的な知識として必ず押さえておきましょう。
合理的配慮の提供義務と支援員の役割
事業主に義務化された「合理的配慮の提供」は、障がい者支援員が最も深く関わるべき重要な項目です。合理的配慮とは、障がいのある方が職場で働くにあたって直面する障壁を取り除くために、事業主が過重な負担にならない範囲で、個々の状況に応じて行う必要な配慮のことです。
これは、単なる「思いやり」や「親切」ではなく、法的に定められた義務であるという点が重要になります。合理的配慮の具体例は多岐にわたります。
物理的環境への配慮
具体的な合理的配慮として、机や椅子の高さを調整する、通路の幅を確保する、段差にスロープを設置する、といった物理的な環境整備が挙げられます。
他にも、車椅子を利用する方のために、デスクの配置を変更したり、通勤しやすいように駐車スペースを確保したりすることも含まれます。
業務遂行に関する配慮
図やイラストを用いた業務マニュアルを作成する、口頭での指示と合わせてメモを渡す、作業手順を一つずつ明確に伝える、といった情報伝達の方法を工夫することも重要です。
また、その方の特性に合わせて、休憩時間の取り方を柔軟に調整したり、本人の集中力が保てるような業務量を設定したりすることも、この配慮に含まれます。
心理的なサポート体制
定期的な面談の機会を設け、業務上の悩みや不安を相談できる体制を整えることも、大切な合理的配慮の一つです。上司や同僚が障がいの特性について正しく理解するための研修を実施することも、働きやすい環境づくりに繋がります。
支援員の役割は、利用者本人と企業の間に立ち、どのような配慮が必要かを具体的に調整することです。利用者の障がい特性や本人の希望を丁寧にヒアリングし、それを企業側が実現可能な形に翻訳して提案する橋渡しとしての機能が求められます。
差別禁止とプライバシー保護の重要性

障がい者雇用促進法では、障がいを理由とする「差別の禁止」が明確に定められています。これは、募集・採用、賃金、配置、昇進など、雇用に関するあらゆる場面において、障がいのあることを理由に不利益な取り扱いをしてはならないという原則です。
例えば「障がいがあるから」という理由だけで採用面接の機会を与えなかったり、他の従業員よりも低い賃金を設定したりすることは、明確な法律違反です。支援員は、このような差別的な取り扱いが行われていないか、常に注意を払う必要があります。
万が一、利用者が不利益な扱いを受けたと感じた場合には、相談に乗り、適切な対処法を一緒に考える擁護者としての役割が期待されます。差別の禁止と並んで、支援員が徹底しなければならないのが「プライバシーの保護」です。
利用者の障がいに関する情報は、非常にデリケートな個人情報です。支援員は、業務上知り得た利用者の障がい名やその特性、通院状況などを、本人の明確な同意なくして企業や第三者に漏らしてはなりません。
企業に障がいに関する情報を提供する際は、どの情報を、どの範囲で、誰に伝えるのかを、必ず利用者本人と事前に話し合い、同意を得るプロセスが不可欠です。本人の意思を最大限に尊重し、プライバシーを守ることは、利用者との信頼関係を築く上で最も重要な基盤となります。
障がい者雇用納付金制度の仕組み
法定雇用率を達成していない企業に対しては、一定のペナルティが課せられます。これが「障がい者雇用納付金制度」です。この制度は、障がい者雇用に伴う経済的な負担を社会全体で調整し、雇用機会の均等化を図ることを目的としています。
支援員としては、この制度の基本的な仕組みを理解しておくことで、企業に対するアプローチの幅が広がります。
具体的には、常用労働者数が100人を超える企業で、法定雇用率を達成できていない場合、不足している障がい者一人あたり月額50,000円の「納付金」を国に納める義務があります。
この納付金は、罰金という位置づけではなく、障がい者雇用を社会全体で支えるための費用として扱われます。集められた納付金は、財源として活用されます。
法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に対して、その超過人数に応じて「障がい者雇用調整金」や「報奨金」が支給されるのです。
支援員は、この納付金制度の仕組みを企業に説明することで、「雇用しないことによるコスト」と「雇用することによるメリット(助成金の活用など)」を具体的に提示できます。
これにより、単なるお願いではなく、経営的な観点からも障がい者雇用を検討してもらうきっかけを作ることが可能になります。企業の理解を促進するための有効なツールとして、この制度の知識は必ず持っておきましょう。
まとめ

障がい者雇用促進法は、障がい者の社会参加と職業自立を支える重要な法律です。支援員は、法定雇用率や合理的配慮、差別禁止、プライバシー保護などの制度を正しく理解し、現場で活用することが求められます。
納付金制度や助成金など、経済的な仕組みも企業への説得材料になります。利用者の尊厳を守りながら、雇用の拡大と安定を目指しましょう。
あとがき
この記事を作成するにあたり、障がい者雇用促進法の本質や、支援員としての現場での役割の重みについて、改めて深く考える機会となりました。
法律や制度の知識を持つことはもちろん大切ですが、最も大事なのは利用者一人ひとりの尊厳を守り、その可能性を信じてサポートし続ける姿勢だと感じます。
支援員として、今後も変化する社会や企業のニーズに寄り添いながら、障がいのある方の「働く」を支える力になりたいと強く思いました。
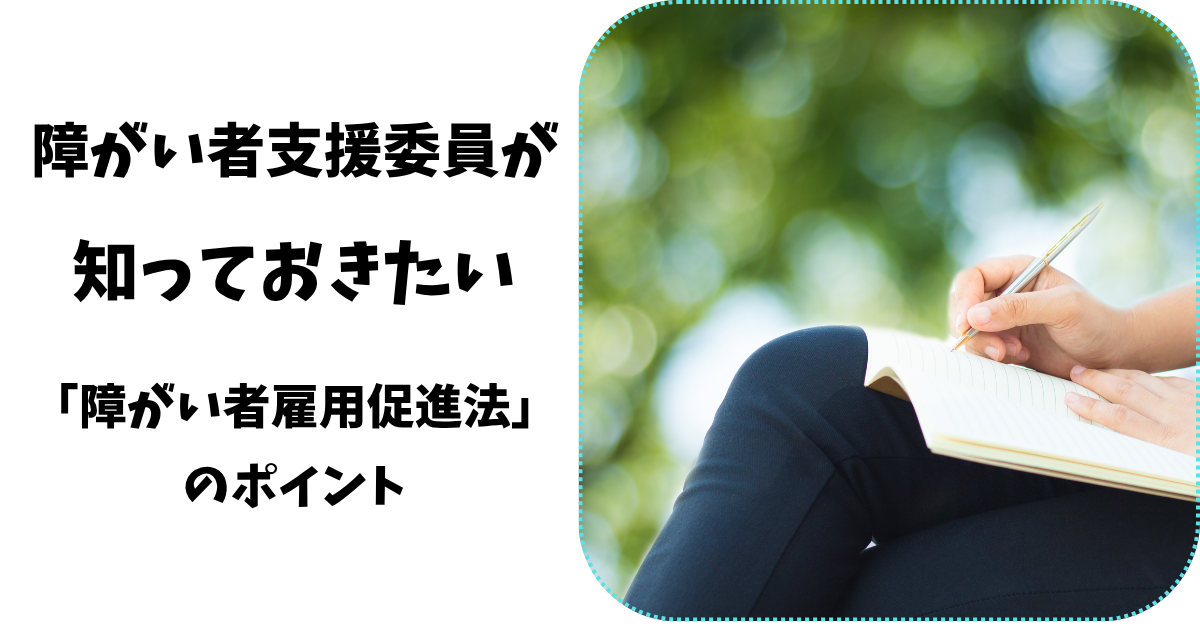

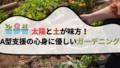
コメント