モニタリングって、ただ記録するだけの作業になっていませんか? 本記事では、サビ管として「最初の一歩」に役立つモニタリングの基本と活かし方を丁寧に解説します。利用者さんに寄り添い、行動や気持ちの変化を見逃さず、支援の質を高めるヒントが満載です。 「何を、いつ、どのように確認すればいいか」がクリアになります。 実際の例も交えているので、明日からすぐに現場で使えます。 まずはモニタリングを“支援の力”に変えていきましょう。
第1章:モニタリングの基本とは?(モニタリングってそもそも何?)
モニタリングとは個別支援計画の進捗や利用者の状況を定期的に振り返り、評価・記録する面談形式の作業です。A型事業所では、個別支援計画を6か月に1回以上見直す義務があり、進行に伴いモニタリングが必要になります。
サビ管が担うべきポイントは、単なる記録ではなく「支援を改善するための材料」にすることです。相談支援専門員ではなく、事業所内ではサビ管がこの役割を担います。
まずは目的を整理し、目標達成度→課題把握→支援方法の見直しという一連の流れを確認しましょう。
例:目標「作業Aを完成できるようになる」に対し、進捗の有無や利用者の気持ちを確認します。
このように、モニタリングは「支援プランのピント合わせ」です。ただの報告ではなく、気づきと改善へと繋げるキーとなる活動になります。
モニタリングの記録は次回の個別支援計画の見直し時に役立つだけでなく、実地指導の際にも必要な根拠資料として活用されます。そのため、記録には日付や具体的な行動、利用者の発言などを丁寧に残すことが大切です。
例:「4月10日、作業中に疲れを訴える。10分間の休憩後に再開し、最後まで取り組めました。」
第2章:モニタリングのタイミングと流れ(いつ・何を確認するの?)

最初のモニタリングは事業所の運用で1~2か月以内が一般的です。生活リズムや職場への不慣れを見逃さないようにしましょう。
通常期は最低6か月ごとの計画見直しに合わせて定期実施になります。利用者の変化やトラブル発生時は臨時モニタリングを実施すると良いです。
流れとしては、事前準備→面談→記録→振り返り→支援計画への反映をします。面談の前には、利用者の目標や前回の記録をあらかじめ確認しておきましょう。
当日は「何がどう変わったか」を中心に話を進めることで、より具体的な支援の方向性が見えてきます。
例えば、作業中の集中力の低下が見られる場合は、その原因や日常生活における変化などを丁寧に掘り下げていくことが重要です。
「定期と臨時」の両方を使い分けて、つねに利用者への理解と支援の精度を保つことを心がけましょう。
| 種類 | 実施タイミング | 主な目的・ポイント |
|---|---|---|
| 最初の モニタリング |
事業所利用開始後 1~2か月以内 |
生活リズムや職場への 不慣れを見逃さない |
| 定期 モニタリング |
最低6か月ごとの 計画見直しに合わせて |
利用者の変化の把握・ 継続的な支援方向の確認 |
| 臨時 モニタリング |
利用者の変化・ トラブル発生時など 必要に応じて |
変化や課題への 迅速な対応 |
第3章:見るべきチェックポイント
モニタリングでは、①実施日、②全体状況(生活や家族の様子含む)、③本人の感想・満足度、④支援目標の達成度、⑤今後の課題と解決策、⑥計画変更の必要性、⑦その他留意事項を記録します。
特に本人や家族の声を丁寧に聞き取り、主語を明確に記述することが大切です。達成度は具体的に書き、必要に応じて「変更あり・なし」に〇を付ける形式にすると判断がしやすくなります。これらの情報は次回の支援計画に直接活用されます。
これらに目を配ることで、支援の「抜け」や「課題」を見逃さず、多面的に改善へ進められます。記録はできるだけ主観を避け、「誰が読んでも同じ解釈ができる」よう意識しましょう。
例:「表情が暗い」ではなく「会話時に目を合わせない」「発言数が少ない」など具体的な観察を書く。これが、質の高い支援に直結します。
| 項目 | 内容 | コツ |
|---|---|---|
| 実施日 | モニタリングを行った日付 | 日付を正確に記載 |
| 全体状況 |
|
|
| 感想 | 利用者本人の声や感想、満足度 |
|
| 達成度 | 目標に対しての進捗や到達度 |
|
| 課題 | 今後の課題や対応案 | 課題・対策を分かりやすく記述 |
| 変更要否 | 現行計画を変える必要の有無 | 「変更あり・なし」に〇を付ける |
| 留意事項 | 特記事項・注意点など | 重要なことを簡潔に |
第4章:面談のコツ
聴く力をどう使うかが鍵になります。面談では、利用者の言葉だけでなく、表情や態度にも注意を向けて心情を汲み取る「傾聴」の姿勢が大切です。
話を広げる前に「そうだったんですね」などの共感の言葉で気持ちを受け止め、安心できる雰囲気をつくりましょう。
質問は「どう感じていますか?」「具体的には?」といった開かれた問いかけが効果的です。たとえば「その仕事、難しいと感じたんですね。何が一番大変でしたか?」と聞くことで、より深い本音を引き出せます。
また、記録用のメモに気を取られるよりも、対話に集中することが信頼関係の構築につながります。面談は情報収集だけでなく、関係性を深める大切な時間です。
利用者の気持ちに寄り添えば、自ずと信頼関係が育ち、小さな変化にも気づける面談になります。
第5章:記録のポイント

面談記録には「事実」「利用者の言葉」「感じ取ったこと」の3点に分けて記載することが良いでしょう。これにより、他スタッフとの情報共有が格段にスムーズになります。
まずは「事実」と「感じたこと」を整理しましょう。記録を取る際は、「事実」と「主観」を分けて記載することが重要です。
たとえば事実としては「3月5日、作業Aで2回ミスがあり、10分間の休憩を挟んだ」など、起きた出来事を客観的に記します。
一方、主観には「本人は『難しい』と話していた」「集中力が続いていない様子だった」といった、様子や本人の言葉を含めます。
具体的な数字や発言を記録に残すことで、後からの振り返りや支援の見直しがしやすくなります。
例えば「3/5、開始30分後に集中力が切れ、ミスが2回発生。『疲れた』と言っていた」といった記録は、支援会議や実地指導時にも活用でき、支援計画の変更根拠にもなります。
記録は支援の改善に繋がる「データ」です。整理と共有が質の向上に直結します。
| 記録の分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 事実 |
起きた出来事や 状況を客観的に記録する |
3月5日、作業Aで2回ミスがあり、 10分間の休憩を挟んだ |
| 利用者の言葉 |
本人が話した発言を そのまま記録する |
「難しい」と話していた、 「疲れた」と言っていた |
| 感じ取ったこと (主観) |
様子や態度など、 支援者が感じたことを記録する |
集中力が続いていない 様子だった |
第6章:チームで共有しよう(みんなで支援を“ひとつ”にする)
記録は、朝礼や週次のミーティングなどでチーム全体に共有することで、利用者の状況を全員で把握できます。
情報共有ツールやホワイトボードなどを活用して、要点を簡潔にまとめるのも効果的です。共有の際は「変化」「課題」「支援アイデア」の3点に注目しましょう。
たとえば、集中力の低下が見られた場合には「環境を調整する」「作業時間を短縮してみる」といった支援アイデアを出し合うことが大切です。
個人対応に留まらず、チーム全体で支援の質を高めていく文化を育てることが、事業所全体の支援力向上につながります。
第7章:モニタリングがもたらす良い循環
支援の質が事業所の“強み”になります。利用者の定着は、安心して働ける環境づくりにつながり、結果として離職率の低下にも貢献します。
こうした安定した職場環境は、新たな利用者に対しても信頼感を与え、利用者数の増加も期待できます。また、監査や実地指導の場では、日々の記録と改善のプロセスがきちんと整っていることが高評価に繋がります。
さらに、支援の質が向上することで、職員自身のやりがいや定着率にも良い影響があると予想されます。
このように、“良い支援=職員も利用者もハッピーな職場”という好循環が生まれ、事業所全体の力を底上げしてくれるのです。
作者の体験
私は現在、在宅ワークのA型事業所で働いています。月に1度は事業所に訪れ、そして3か月に一度は相談員さんも同席して自宅にてモニタリングを行ってもらっています。
事業所と自宅、それぞれでモニタリングがあるのは、きめ細かくサポートしてもらえていると感じているのでとても安心です。
月に一度の事業所でのモニタリングでは、その月の作業の振り返りや困っていることを気軽に相談できています。目標の進捗状況も確認できるので、モチベーション維持にも繋がっています。
そして、3か月に一度、相談員さんにも同席いただいて自宅で行うモニタリングは、事業所では見えにくい日常生活での困りごとや、体調の変化なども伝えられる貴重な機会です。
自宅での様子を相談員さんにも知ってもらえるので、より具体的なアドバイスをもらえたり、生活全般のサポートについて一緒に考えてもらえたりと、とても心強いです。
いつも親身になって話を聞いてくださるサービス管理責任者さん、そして定期的に自宅まで足を運んでくださる相談員さんには、心から感謝しています。
どちらのモニタリングも、私が安心してA型事業所を利用し、自分らしく働くために欠かせない時間だと感じています。本当に感謝しています。
まとめ
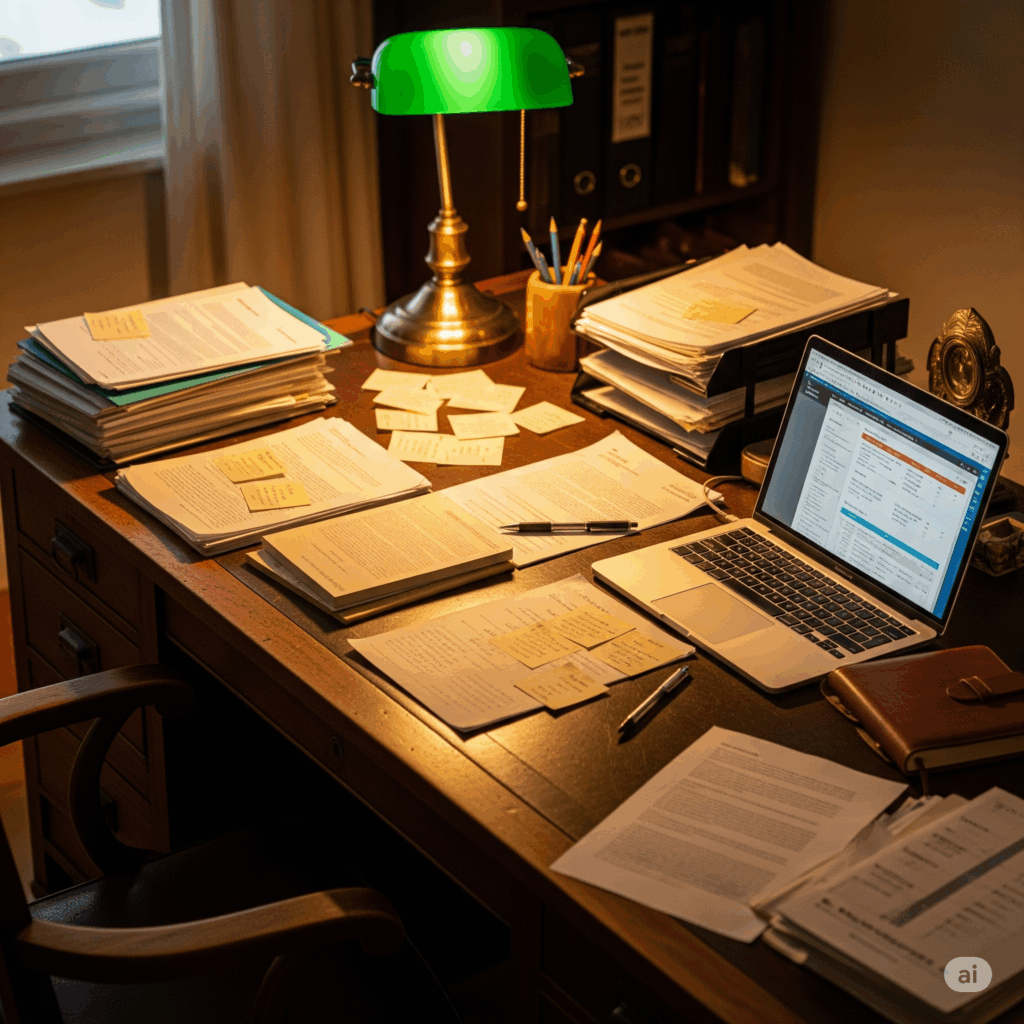
モニタリングは記録ではなく支援の基盤です。傾聴・共有・整理を通じて質を高め、柔軟な対応と改善へつなげましょう。まず一歩、小さな見直しから始めてください。継続的な取り組みが、利用者の安心や定着、事業所全体の信頼向上にもつながります。

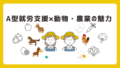
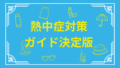
コメント