障害年金を受給しながら働く人が増えています。 特にA型事業所などで就労する方にとって気になるのが「家族の扶養に入れるかどうか」という点です。 実は、年収が180万円以下であれば、扶養に入れる可能性があります。 でも「年収の考え方ってどうなってるの?」「年金と給与の合計はどう扱われるの?」など、分かりづらい点も多いですよね。 この記事では、障害年金、A型事業所、扶養条件の関係をわかりやすく解説します。
第1章:障害年金とは?仕組みと種類を知ろう
障害年金は、障害のある方が生活を安定させるために国から支給される公的年金制度です。年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けた時、国民年金加入中なら障害基礎年金を、厚生年金加入中なら障害厚生年金を受給できます。障害等級が1級・2級の場合は、厚生年金に加えて障害基礎年金も受給可能です。
受給には、初診日の証明や障害等級の判定が必要になります。等級は1級、2級、および3級に分類されており、障害の重さによって支給額が異なります。
受給者の中には、仕事に就くことができる人も多く、障害年金は「働いたらもらえなくなる」ものではありません。
ただし、生活が安定するためには年金だけでなく働くことも大切です。そのため、A型事業所のような福祉的就労の場で働く人が多くなっています。働くことで収入が増えると、家族の扶養に入れるかどうかが気になってきますね。
そのカギを握るのが「収入180万円」という基準です。
第2章:A型事業所とは?働き方の特徴を解説

A型事業所は、障害のある人が就労訓練をしながら、安定した収入を得ることができる福祉サービスの一つになります。特徴的なのは「雇用契約」があるという点です。利用者は事業所と労働契約を結び、最低賃金以上の報酬が保証されます。
つまり、一般企業と同じように働きながら、福祉的な支援も受けられる仕組みになっているのです。A型事業所では、軽作業やパソコン業務、清掃、製造など、本人の障害特性に合った仕事が提供されます。
働き方は、事業所により異なりますが、1日4~6時間勤務が一般的です。令和4年度の厚生労働省の調査では、利用者の9割近くが週20時間を超えて働いており、その中でも1日4時間以上4時間30分未満の勤務がほぼ半数を占めます。
フルタイム勤務が可能な事業所は少ないものの、残業はほとんどなく、定時で終業できるため、体調管理もしやすいのが特徴です。
月収の平均賃金に関しては、令和5年度の厚生労働省の調査によると、全国平均月収は約86,752円でした。無理のない範囲で、働く意欲を持ち続けられるのが魅力でしょう。
働いて得られる収入が増えてくると、健康保険や扶養などの制度も気がかりです。特に、年金を受けながらA型事業所で働く場合、「扶養内で働き続けられるか?」という点がポイントとなります。その判断基準のひとつが「年収180万円」というラインなのです。
第3章:障害年金受給者が知っておくべき社会保険の扶養制度
障害年金を受給しながら仕事をしている方、あるいはこれから働こうと考えている方にとって、社会保険の扶養制度は非常に重要なポイントです。
この制度を理解していなければ、知らず知らずのうちに扶養から外れてしまい、予期せぬ家計の負担増に直面する可能性があります。
ここでは、障害年金受給者が社会保険の扶養に入るための具体的な条件、税法上の扶養との違い、そして年金と給与収入のバランスをどう取るべきかについて、詳しく解説していきます。
社会保険の扶養とは?税法上の扶養との違い
まず、混同しやすいのが「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」です。税法上の扶養は、所得税や住民税の計算に関わるもので、扶養親族がいることで税金の控除が受けられる制度です。
ここでの収入には障害年金は含まれません。つまり、障害年金をいくら受給していても、それが直接税法上の扶養の判定に影響することはありません。一方、今回解説する社会保険上の扶養は、健康保険や年金保険といった社会保険の適用に関わる制度です。
この扶養に入ることができれば、自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要がなくなるため、経済的なメリットは非常に大きいと言えます。
そして、この社会保険上の扶養を判定する際には、障害年金の金額も「収入」として合算して計算されるという大きな違いがあります。この点を理解しておくことが、扶養内で働く上で最も重要な第一歩です。
第4章:障害年金受給者が社会保険の扶養に入るための条件

障害年金を受給している方が社会保険の扶養に入るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。収入の合計が年間180万円未満であることです。ここでの収入とは、障害年金の受給額と給与収入(パート・アルバイトなど)の合計額を指します。
他の収入がある場合はそれらも合算されます。この180万円という基準は、一般的な扶養の基準である130万円とは異なり、障害年金受給者や60歳以上の方に配慮された特例的な基準です。
扶養者との関係性による収入条件
あなたを扶養に入れる方(例えば配偶者や親など)との関係性によって、さらに以下の条件が加わります。
- 扶養者と同居している場合: あなたの年間収入が、扶養者の年間収入の半分未満である必要があります。
- 扶養者と別居している場合: 扶養者からの仕送り額よりも、あなたの年間収入が少ない必要があります。
これらの条件のうち一つでも満たせなくなると、あなたは社会保険の扶養から外れてしまいます。そうなると、ご自身で住んでいる市区町村の国民健康保険に加入し、健康保険料を納める義務が生じます。加えて、国民年金保険料も自分で支払う必要が出てくるため、家計への負担は避けられません。
第5章:具体的な計算例:年金と給与収入のバランス
実際に障害年金を受給しながら働いている場合、具体的にどのくらいの収入までなら扶養に入れるのでしょうか。
例えば、令和7年度に障害基礎年金2級を受給している場合を考えてみましょう。 障害基礎年金2級の年間受給額は831,700円です。
社会保険の扶養に入れる収入の合計上限が180万円ですから、給与収入として得られる上限額は以下の計算で求められます。
1,800,000円(社会保険の扶養限度額)− 831,700円(障害年金年間受給額)=968,300円
つまり、このケースでは、給与収入を年間968,300円以内に抑える必要があります。これを月額に換算すると、968,300円 ÷ 12ヶ月 = 約80,691円となります。 したがって月々の給与収入の目安は約80,691円ということになります。
第6章:働き方の注意点と調整
月々の給与収入の目安が分かると、ご自身の働き方を具体的にイメージしやすくなります。しかし、注意したいのは、月々の収入が一時的に変動する可能性があることです。
例えば繁忙期には勤務時間が長くなり、月収が目安を超えてしまうこともあるかもしれません。そうした場合は、閑散期の勤務時間を減らす、あるいは残業を控えるなどして、年間を通して収入が968,300円を超えないように調整することが重要です。
もし、ご自身で調整が難しい場合は、勤務先に相談し、年間の収入が扶養の範囲に収まるようにシフトや勤務時間を調整してもらうことも検討してみてください。
まとめ

障害年金を受給しながらA型事業所で働くあなたへ。扶養内で働き続けるには、「年収180万円」の壁を正しく理解することが鍵です。この「年収」には障害年金も合算されるため、給与収入との合計を常に意識する必要があります。
不安な時は、各市町村の障害福祉課や年金相談窓口へ迷わず相談を!賢く制度を活用して、安心して働き続けましょう。
あとがき
私は、障害年金を受給しながら働くなら、就労継続支援A型事業所が選択肢の一つだと思います。特に扶養内での働き方は、体調に無理なく、仕事と家庭のバランスを保ちやすいメリットがあると感じるからです。
長く働き続けたいと願うなら、福祉のサポートを積極的に活用することは賢い選択です。A型事業所は、それぞれの障害特性に合わせた支援を提供し、安心して仕事に取り組める環境を整えています。
自分らしい働き方を見つける一歩として、A型事業所の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

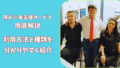

コメント