新生活や環境の変化で、気づかないうちに疲れがたまる5月。 「やる気が出ない」「体がだるい」そんな時は、5月病のサインかもしれません。しかし、心と体にやさしいケアを取り入れることで予防することができます。ポイントは、「無理なく続けられる」こと! 今回は、毎日できる簡単なストレッチとウォーキング方法をご紹介します。 自分のペースでできる習慣で、元気な5月を過ごしましょう。
1. 5月病ってなに?気づかないうちに心と体が疲れてるかも
春の暖かさが心地よくなる一方で、「なんとなく気分が落ち込む」「朝起きるのがつらい」と感じていませんか?それはもしかしたら、5月病のサインかもしれません。
5月病とは、新年度の始まりによる緊張やストレスが、ゴールデンウィーク明け頃にどっと出てくることによって起こる不調のことを指します。医学的な病名ではありませんが、心と体のバランスが崩れる状態を示す言葉として、広く使われています。
症状としてはたとえば、なんとなく気分が落ち込みやすくなったり、やる気が出なかったり、普段よりも疲れやすくなったりすることが挙げられます。夜になっても眠れなかったり、反対に眠っても疲れが取れないことも。
また、食欲がわかず、何を食べても味がしないと感じるケースもあるかもしれません。
こうした症状が長く続いてしまうと、日常生活に支障が出てしまう可能性があります。特に、真面目で責任感が強い人ほど「自分だけ頑張れていない」と思い込みやすく、誰にも相談できずに1人で抱え込んでしまいがちです。
大切なのは、疲れをため込む前にケアを始めること!無理せず自分のペースで過ごすことが、5月病を防ぐ大きな一歩になるでしょう。
2. 朝イチ1分!スッキリ目覚める簡単ストレッチ

1日の始まりを快適にするために、朝のストレッチはとても効果的です。
寝ている間に硬くなった筋肉をゆるめることで、血行がよくなり、脳にも酸素が行き渡ります。結果として、気持ちよく目が覚め、活動的な気分になれるでしょう。
ストレッチと聞くと難しそうに思えますが、たった1分でもOK。ベッドの上でもできる簡単な方法から始めて、少しずつ慣れていきましょう。
以下のような動きを取り入れてみてください。
伸びのポーズ:
手足をまっすぐに伸ばし、大きく深呼吸しながら全身をリラックスさせ、筋肉をほぐします。しっかりと伸びを感じることで、1日の活力が湧いてくるでしょう。
首まわし:
ゆっくりと左右に首を回し、肩まわりや首筋をほぐすことで、血行が良くなります。首を柔らかくするだけでも、肩こりの予防につながります。
背中丸めストレッチ:
膝を抱えて背中を丸め、ゆっくり体を揺らすことで背中の緊張を解消します。深い呼吸とともに行うと、リラックス効果も高まります。
これだけでも、体の中がポカポカと温かくなり、気持ちが前向きになるかもしれません。ストレッチは特別な器具もいらず、時間もかからないので、毎朝の習慣にしやすいのが魅力です。
最初は「これだけでもOK」と思えるシンプルな動きから始めてみましょう。続けていくうちに、体が軽く感じ、気分もスッキリしていきます。
3. 通勤や買い物ついでにできる!5分ウォーキング術
外に出るのは少々おっくうかもしれませんが、歩くことは手軽なリフレッシュ法です。特に、何も考えずにスマホを見ながら過ごすより、少し歩くだけで気分転換になることも。
歩くことで、体を軽く動かすだけでなく、自然とリフレッシュでき、心も体もリセットされるのが実感できます。気負わずに「ついでにやる」感覚で続けることが大切です。
通勤中や買い物帰り、バスや電車を一駅手前で降りるなど、生活の中に自然と取り入れてみましょう。どんな日常的な瞬間も、気分を切り替えるチャンスです!
ウォーキングの際に意識したいポイントは以下の通りです。
背筋を伸ばし、目線は前へ:
スマホを見ながら歩くのは危険です。周りの景色を楽しみながら歩くことが、リラックス効果を高めてくれるでしょう。
腕を自然にふる:
肩の力を抜いて、リズムよく歩くと、腕や肩の筋肉もほぐれ、疲れにくくなるでしょう。
呼吸を深く意識する:
鼻から吸って、口からゆっくり吐くことで、リズムよく呼吸ができ、体全体に酸素が行き渡ります。
これらを意識することで、ただの移動が「リラックスタイム」に変わります。もちろん、毎日きっちり歩く必要はありません。天気がいい日だけでも、気分が向いたときだけでもOK。
自分のペースで少しずつ取り入れることが、長続きのコツです。歩くことで、心身ともに軽くなり、1日の活力を生み出せるので、無理なく続けることが大切です。
4. スマホ時間を見直そう!心の休憩も大切に

5月病の予防には、体のケアだけでなく心の休憩も大切です。特に、スマホやパソコンなどのスクリーンを見る時間が長くなると、脳が休まらず、知らないうちにストレスがたまってしまいます。
SNSやニュースを眺めているだけでも、意外と心が疲れてしまうこともあるのです。
現代の生活では、スクリーンに触れる時間がどうしても長くなりがち。しかしそれが日常的になってしまうと、リラックスする時間がどんどん減少し、心の疲れが蓄積されてしまいます。
そんな時におすすめしたいのが、意識的に「スマホオフ時間」を作ることです。たとえば、就寝1時間前にはスマホを見ないようにして、夜の睡眠に備えることが効果的です。
食事中や家族との会話中はスマホを置いて、直接的なコミュニケーションに集中することで、心の安らぎが得られるでしょう。
また、朝起きてすぐにスマホを確認する代わりに、少しの間、静かな時間を過ごすだけでも心が落ち着くでしょう。
これらの習慣を取り入れることで、心の緊張が緩みやすくなり、リラックスする時間が増えます。
また、スマホを置いた時間には、深呼吸をしたり、ゆっくりお茶を飲んだりすることで、さらに心が休まるでしょう。
特別なことをする必要はなく、意識的に自分だけの「ほっとできる時間」をつくることが大切です。毎日の忙しい生活の中にも、少しでも自分を大切にする時間をつくること。それが心と体の健康を守るうえで欠かせません。
5. 毎日ちょっとだけ、が続くコツ!習慣化のヒント
どんなに良いことでも、続けなければ意味がありません。しかし、「毎日ちゃんとやらなきゃ」と思うと、どうしてもプレッシャーを感じてしまうことがありますよね。
そんな時に大事なのは、小さなことを無理なく積み重ねることです。続けるためのコツは、まず続けやすい環境を作り、気持ちのハードルを下げることにあります。
習慣化を目指すためには、まず自分に合った方法を見つけることが大切です。たとえば、毎朝歯を磨いた後にストレッチをする習慣をつけたり、帰宅後に軽く歩く時間を設けたりすることから始めてみましょう。
時間と場所を決めることで、自然に習慣に組み込みやすくなります。
また、毎日続けることができなくても、無理せず「1分だけでもOK」と自分に優しく設定するのがポイントです。どうしてもやる気が出ない日でも、短時間ならできるというラインを設けておくと、無理なく続けやすくなります。
そして、何より大切なのは、自分が達成したことをしっかりと認めることです。たとえば、「今日は5分歩けた!」と自分をほめることで、次も頑張ろうという気持ちが湧いてきます。
人は「やったこと」よりも「できなかったこと」に目を向けがちです。しかし、小さな達成感を積み重ねることで、自然と自信がついてくることでしょう。
「続けること」が目的であれば、その方法は自分に合ったものでOKです。無理せず、自分のペースで心地よく続けられる方法を見つけていきましょう。
まとめ

日々の忙しさに追われがちな5月。心と体をリフレッシュするためには、無理なく続けられる方法を取り入れることが大切です。ストレッチやウォーキングを少しずつ習慣にして、心地よいペースで元気を取り戻していきましょう。
毎日のちょっとした習慣が、大きな変化を生むことを忘れずに。心と体をリフレッシュして、笑顔で5月を過ごしてくださいね!
あとがき
この記事を読んでいただき、ありがとうございます。5月病は、思った以上に身近な問題ですが、少しの工夫で予防することができます。
無理なく、そして自分のペースで実践できる方法を取り入れれば、心と体をリフレッシュし、毎日を元気に過ごせます。
ストレッチやウォーキングなどの習慣を少しずつ始めることで、5月病の予防に繋がります。ぜひ、毎日のちょっとしたケアで、心身ともに健やかな日々を送りましょう!
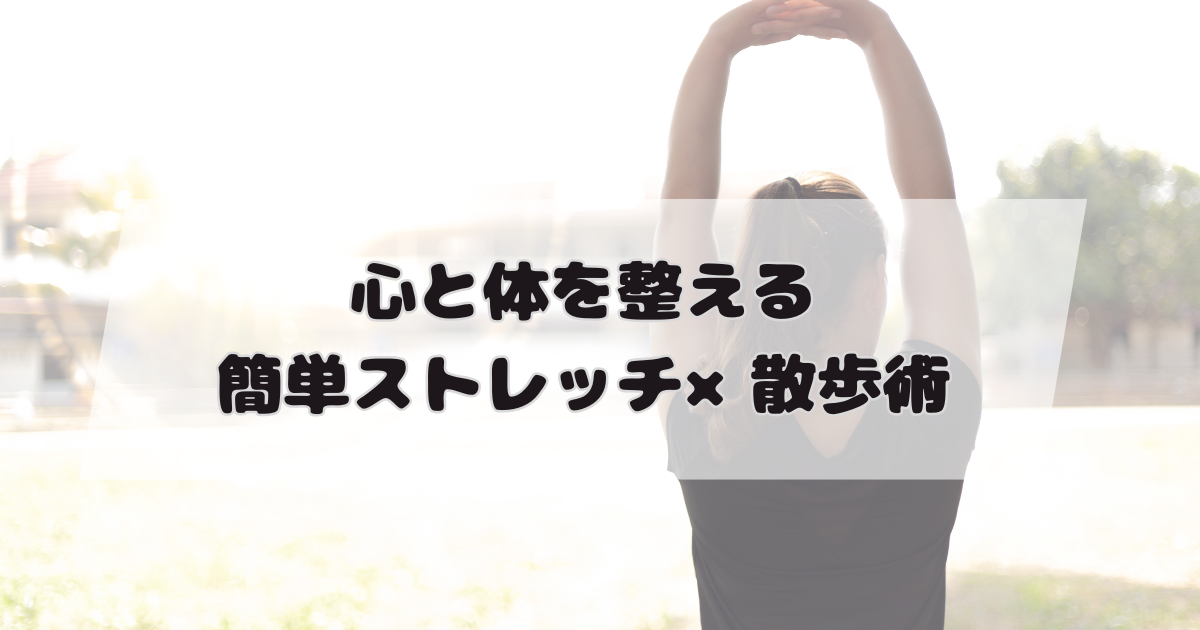


コメント